
建設現場には、高所作業や重機操作など、常にリスクを伴う業務が存在します。現場での「万が一」を防ぐために欠かせないのが、安全教育です。
この記事では、建設業における安全教育の法的義務からその具体的な内容、効果を上げる方法までを網羅的に解説します。災害ゼロの現場づくりの実践ガイドとして、ぜひお役立てください。
建設業で特に安全教育が必要な理由
まずはなぜ建設業で安全教育に注力する必要があるのか、その背景となる客観的事実を確認しておきましょう。
建設業で高い労働災害の発生状況
建設業は、国内の全産業の中でも、死亡につながる労働災害の件数が最も多い業種です。厚生労働省の「労働災害動向調査」によると、建設業における2023年(令和5年)の死亡災害は223件で、これは製造業(138件)や運輸業(111件)を大きく上回る水準です。
高所作業や重量物の取り扱い・重機との接触など、日常的に大きなリスクと隣り合わせの作業が多いことがその背景にあります。
建設業に多い事故
建設現場で最も多く発生している労災は、「転落」や「墜落」によるものです。足場や屋根、脚立などからの転落は身体への衝撃が大きく、命に関わる重大事故につながりやすく、特に注意が必要です。
ちなみに転落とは、階段などの足が接地する環境で転げ落ちることを指し、墜落は完全に足が付かない状態で落下する事故のことを意味します。
転落・墜落は、作業員の「慣れ」や「油断」、そして安全対策の不徹底によって引き起こされることも少なくありません。
建設業に特有の職業性疾患
建設業では、事故だけでなく職業性疾患(いわゆる職業病)にも注意が必要です。特に多いのが「腰痛」「振動障害」「じん肺」などです。
また、屋外での長時間作業や高温多湿な現場での業務が多いため、夏場の熱中症も深刻な問題となっています。
建設業の労働災害事例
実際に起きた建設業の事故事例は、どのような場面に危険が潜んでいて、どのような対策を取るべきであったかを検討するのに有効です。ここでは3つの災害事例を紹介します。
建設業の労働災害事例①墜落・転落
2階建て店舗の新築工事現場にて、鉄骨組み立ての作業中、資材の運搬中の労働者が高さ8メートルの梁からバランスを崩して墜落。安全帯を装着していたものの、親鋼に接続するフックが未使用で、死亡に至った。墜落防止用の安全ネットも未設置だった。
◆原因
- 安全帯を適切に使用させていなかった
- 墜落防止措置を未設置のまま作業を行わせた
- 作業主任者が安全管理職務を怠った
- 新たに作業に就いた被災者に、教育を実施していなかった
◆対策
- 安全帯の使用を徹底
- 墜落防止措置は事前に実施
- 主任者による安全管理を徹底
- 新規入場者教育を確実に実施
建設業の労働災害事例②熱中症
炎天下の資材置場および現場で足場解体作業を行っていた労働者が、体調不良に。休憩後も作業を再開したが、吐き気などの症状が悪化して入院、熱中症による多臓器不全で死亡した。
◆原因
- 猛暑日に炎天下で作業を行わせた
- 水分塩分の適切な補給がされていなかった
- 安全管理者が熱中症対策を怠った
- 事前の作業打合せや健康確認を行わなかった
- 熱中症への認識不足
◆対策
- 休憩所・休憩時間の確保
- 炎天下作業の短縮と服装への配慮
- 水分・塩分補給設備の設置
- 事前指示と注意喚起の徹底
- 速やかな応急処置と病院搬送
近年の熱中症による労災の増加を受け、2025年4月からは熱中症対策の実施が企業に義務付けられました。
参照:中小建設業特別教育協会【第4章】第1節 熱中症の災害事例(1)
建設業の労働災害事例③下敷き
2024年3月、岡山市の再開発工事現場で、建設作業中に足場と型枠が倒壊。作業員6名が下敷きとなり、1名が死亡 、5名が負傷しました。
この事故を受け、岡山労働局は企業に対し、以下のような対策を緊急要請しました。
◆対策
- 型枠を支える仮設の骨組みに関する組立作業計画の作成と周知
- 組み立て及びコンクリート打設前の点検の実施
- 構造耐力の確保
- 安全衛生教育と危険予知活動の徹底
- 作業主任者による直接指揮と安全管理の実施
建設業の安全教育の種類・ガイドライン
 建設業には、さまざまな安全教育が義務づけられたり、教育の必要水準が設けられたりしています。ここでは、代表的な教育の種類やそのガイドラインを整理します。
建設業には、さまざまな安全教育が義務づけられたり、教育の必要水準が設けられたりしています。ここでは、代表的な教育の種類やそのガイドラインを整理します。
特別教育など、労働安全衛生法で義務付けられる安全衛生教育
建設業で最も重要なのは、特定の危険性・有害性のある作業に従事する労働者に対して行われる「特別教育」です。
これは、労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則第36条以下に基づき、企業に実施が義務付けられています。
- 特別教育が必要な作業例としては、
- 足場の組み立て、変更、解体
- 高所作業車の操作
- チェーンソーの使用
などが挙げられます。
特別教育は、各作業ごとに学科・実技の時間数が法定で定められているため、定められたカリキュラムを満たす必要があります。
主な実施団体は、全国建設業労働災害防止協会(建災防)などです。
建設業労働災害防止協会(建災防)の安全衛生教育ガイドライン
建災防は、建設業に特化した安全衛生教育体系を整備しており、ガイドラインの中で以下の教育区分を提示しています。
- 新規入場者教育(現場入場前に基本ルールを教育)
- 職長・安全衛生責任者教育(管理監督者向け、労働安全衛生法第60条に基づく)
- 特別教育(特定作業従事者向け)
- 能力向上教育(技能向上・事故防止のため)
- リスクアセスメント教育(リスクの事前把握・低減策検討)
事業規模や作業内容に応じて、企業がこれらを適切に組み合わせて実施することが推奨されています。
なお、「職長・安全衛生責任者教育」は特別教育とは別枠であり、現場の管理監督者に対して法律上必須とされる教育です。
建設業の安全教育に必要な時間
「建設従事者教育」は法的な義務ではなく、主に元請企業や業界団体によって自主的に実施されるもので、建災防は「6時間以上」の教育を推奨しています。そのため現場では、一般的に「6時間教育」と呼ばれています。
6時間教育には、法律上の必須項目だけでなく、現場で役立つ具体的な安全行動や災害事例も含まれています。
建設業の安全教育・5つのカリキュラム
建設業の安全衛生教育は、主に次の5つのテーマを軸に構成されています。目的や内容について説明しましょう。
1.労働安全衛生関係法令
まずは、労働安全衛生法(安衛法)や労働安全衛生規則(安衛則)について学びます。
これらの法令では、企業への義務や実務に直結する具体的な作業ガイドラインが定められています。基礎知識として習得し、法令順守を徹底します。
2.安全施工サイクル
「安全施工サイクル」とは、1日や1週間、1カ月などの単位で繰り返し実施する、安全衛生管理の仕組みです。
作業前の朝礼、危険予知(KY)活動や作業中の巡視、作業後の片付け・報告などを日常に組み込み、安全と施工を一体化させ、現場全体への安全文化の定着を目指します。
3.現場での安全衛生行動
現場では法令や計画だけでなく「その場でどう行動するか」の判断が安全に直結します。
現場での安全管理体制や安全点検の手順を踏まえ、有害な物質や作業、場所に関してどのようにその健康上のリスクを回避するかという観点から、具体的な行動について学びます。
4.過去の災害事例とその対策
実際に起きた災害事例のエピソードは、理論をテキストで学ぶ以上に作業員に響くでしょう。
墜落や熱中症、重機接触事故などの事例をもとに「なぜ起きたのか」「防ぐにはどのような準備・確認・行動が必要だったのか」など、実際の現場でも応用可能な対策を学びます。
5.保護具装着や合図などの実践訓練
知識習得だけではありません。保護具(安全帯・ヘルメット・防じんマスクなど)の装着や、合図・玉掛けといった、現場で求められる技能の実践も含まれます。
座学だけではなく、体を使った訓練を通じて、知識を確実に行動へと落とし込むパートです。
建設業の安全衛生教育の実施方法
それでは、実際の現場ではどのような方法で安全衛生教育を進めていけば良いのでしょうか。ここでは、建設現場で広く行われている4つの方法をご紹介します。
安全朝礼
 安全朝礼は、建設現場では毎日行われています。安全教育の基本的施策です。
安全朝礼は、建設現場では毎日行われています。安全教育の基本的施策です。
朝礼では、その日の作業内容に応じた注意事項や、当日の天候・体調の確認なども含め、作業上のリスクを全員で確認します。
安全朝礼は安全施工サイクルにおける「実施」「点検」にも直結します。
安全大会
安全大会は、企業や現場単位で年1回程度実施する集合型の教育です。
建設業界では特に7月の安全週間に合わせて行われています。
厚生労働省でも積極的な開催を推奨しています。災害事例の共有や表彰などを通じ、参加者一人ひとりの安全意識を高めることが目的です。
全社員・全協力会社が参加する大会も多く、現場全体の安全文化を醸成する貴重な場です。
研修・講習
特別教育や職長教育など、法令に基づく安全衛生教育の多くは、研修・講習形式で実施します。
安全管理に関する幅広い知識やスキルを組織的・体系的に学べ、修了証の発行などによって教育履歴が明確になるのがメリットです。
オンライン講座や動画教材・PDF資料の活用
最近は、eラーニングや動画教材、PDF形式の資料を活用する企業も増えています。
動画教材は集合型教育に参加する前の予習や、繰り返し視聴による反復学習にも向いています。別の教育方法と組み合わせると効果が高まるでしょう。
また、厚生労働省などが公開している災害事例のPDF資料を活用するのもおすすめです。
建設業の安全教育講師の選び方
安全教育の効果は、講師の質によって大きく左右されます。最後に、社内講師と社外講師の違いのほか、選定時のポイントを確認しておきましょう。
社内講師
社内講師は、自社の事情に精通していることから、現場の状況に即した実践的な教育ができるのがメリットです。対象者にとって「自分ごと」と感じられる災害やヒヤリハット事例の知識も豊富でしょう。
日常的な指導やフォローがしやすい反面、講師の知識や指導力に個人差があるのが課題です。
社外講師
一方、社外講師には、専門知識や最新事例に基づく、体系的で説得力のある指導が期待できます。他社事例や最新の法令情報にも詳しく、受講者に新たな気づきを与えられる可能性が高いです。
講師料として費用が発生するほか、自社向けに内容を調整するのに手間がかかる場合もあります。その点で、講師派遣の専門サービスを活用するのもおすすめです。
建設従事者教育の講師選定基準
建災防のガイドラインでは、講師の選定に関する基準も明確にされています。特に「建設従事者教育」においては、以下のような基準を参考にすると良いでしょう。
- 安全衛生教育に必要な知識や経験を有する
- 関係法令やガイドラインを正確に理解している
- 受講者の実態に合わせた指導ができる
この基準は、社内・社外講師とも共通です。選定する際は「知識・経験・指導力」の3点を重視してください。
システムブレーンおすすめの安全教育の講師陣
外部講師を検討する際には、講師派遣サービスを活用するのもおすすめです。
システムブレーンでは、建設業に特化した安全大会・安全教育向けの講師が多数在籍しており、自社のニーズや課題に合う専門性・経験を持つ講師を提案可能です。
以下のページで、弊社で人気の安全教育・安全大会講師をご紹介していますので、こちらも合わせてご覧ください。
【合わせて読みたい】
安全管理・コミュニケーション・笑いなど幅広いジャンルから! ~…
人気講師から選択したいとお考えの皆様へ。眠らせないのは当たり前…
コロナ禍で一気に普及したオンライン講演。遠隔地から参加しやすい…
建設業における安全教育は、深刻な労働災害を防ぐために必ず実施しなければならない、組織の基盤です。法令順守だけを目的とした教育では、不十分な可能性もあります。即効性の高い外部サービスの活用も考慮のうえ、現場の実態に即した教育を継続しましょう。
あわせて読みたい
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
他の記事をみる









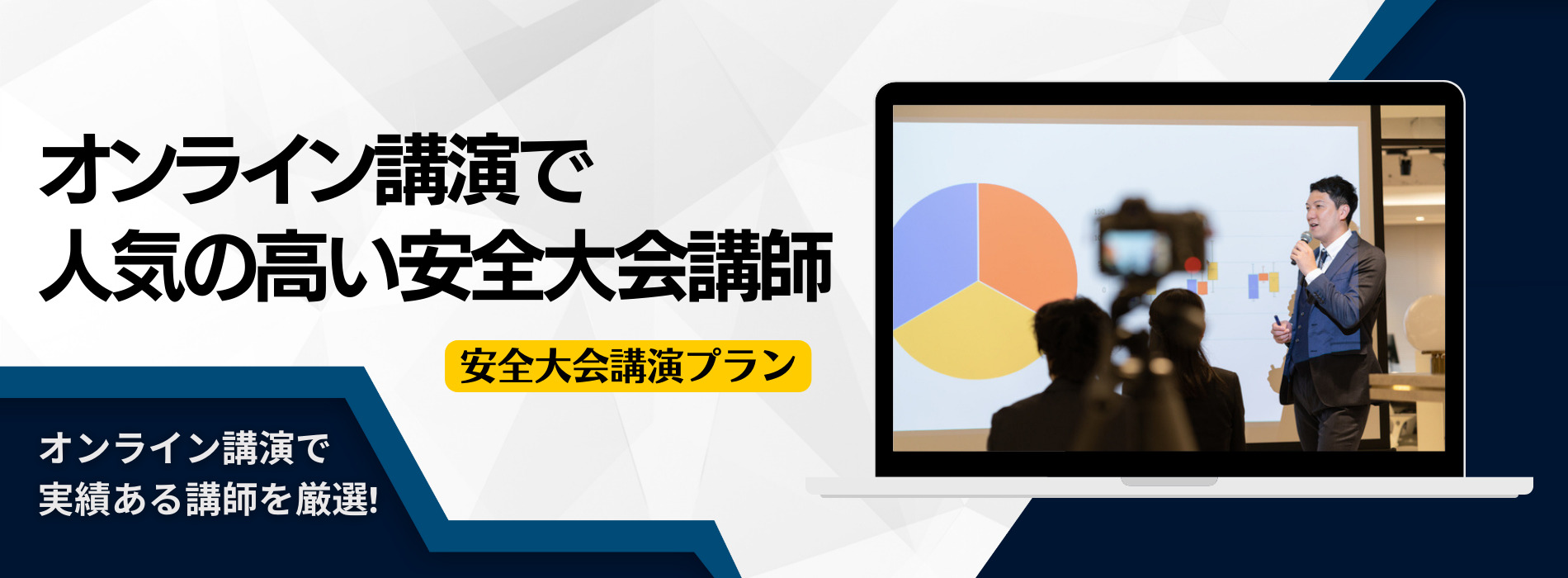












業務外の講師への取次は対応しておりません。