
「ドル安が進んでいるのに、なぜ円高にならないのか?」
2025年7月、ドル指数は3年4か月ぶりの安値水準まで下落しました。本来なら円高に振れそうな局面ですが、実際には円インデックス(円の総合的な強さ)はわずかな上昇にとどまり、むしろユーロなどに対しては円安が進んでいます。
この「ドル安でも進まぬ円高」は、企業経営者や投資家、そして日々の生活を送る私たちにとって大きな意味を持ちます。
今回は、長年にわたり市場を分析してきた経済アナリストの村田雅志さんに、日本経済が抱える構造的な課題を整理し、ビジネスパーソンが実践的に取りうる戦略について解説していただきます。
※本記事の内容は2025年9月時点のものです。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
村田雅志氏
経済ナビゲーター
円安が止まらない理由:「トリレンマ」の呪縛
 為替市場を理解する上で欠かせないのが「金融政策のトリレンマ」です。これは、一国が同時に達成できない三つの条件を示しています。
為替市場を理解する上で欠かせないのが「金融政策のトリレンマ」です。これは、一国が同時に達成できない三つの条件を示しています。
- お金の自由な出入りを認めること(資本移動の自由)
- 自国に合った金利政策をとること(独立した金融政策)
- 為替相場を安定させること(為替の安定)
日本は長年にわたり、景気刺激のためにゼロ金利やマイナス金利といった極端な金融緩和を続けてきました。これは2番目の「独立した金融政策」に該当します。同時に、日本は世界経済の一員として、資本移動の自由も確保しています。つまり1と2を選んだために、3の「為替の安定」を犠牲にしているのです。
その結果、米国がインフレ抑制のために積極的に利上げを進める一方で、日本が低金利を維持すれば、投資家は金利の高いドルを買い、低い円を売ります。これがドル安でも円高が進まない構造的な理由、すなわち「トリレンマの呪縛」なのです。
日銀の難しい舵取り:「三つ巴」の課題
この「トリレンマの呪縛」により、日本銀行も難しい判断を迫られています。
- 円安を抑えるための利上げ
利上げをすれば円安は抑えられますが、企業や家計の借入負担が増え、景気を冷やすリスクがあります。 - 景気を支える金融緩和
緩和を続ければ円安が進み、輸入インフレを悪化させます。 - 国債市場の安定
日本政府は膨大な借金を抱えています。利上げを行うと国債利払い負担が増え、財政への懸念が高まります。
この3つを同時に満たすことはできず、日銀は「次悪の策」で時間を稼ぐしかありません。口先介入や小幅利上げといった小出しの対応が続くのはそのためです。
「良い円安」から「悪い円安」へ
「トリレンマの呪縛」の結果、日本の経済市場では今”悪い円安”が起きています。
かつての円安は「日本経済にプラス」とされてきました。例えば2010年代前半のアベノミクス期、円安は輸出企業の競争力を高め、自動車や電機メーカーの収益を押し上げました。国内工場の稼働率も高まり、雇用の増加につながったのです。これが「良い円安」の典型例です。
しかし今は状況が一変しています。製造業の多くが生産拠点を海外に移し、国内での輸出量はそれほど伸びません。円安で恩恵を受けるのは、海外子会社の利益を円に換算したときの見かけ上の数字に過ぎないケースが多いのです。
一方で、エネルギーや食料の多くを輸入に頼る日本では、円安は輸入品の価格上昇を招きます。ガソリン代や電気代、食費が上がるのはまさにこの影響です。
次章でこの「悪い円安」への影響について、家計と企業の視点からみていきたいと思います。
家計への影響:「輸入インフレ」と「実質賃金の減少」
 かつての円安は輸出企業を潤し、国内に雇用と投資を呼び込む「良い円安」でした。しかし現在は構造が変わり、私たちの生活に逆風となっています。
かつての円安は輸出企業を潤し、国内に雇用と投資を呼び込む「良い円安」でした。しかし現在は構造が変わり、私たちの生活に逆風となっています。
輸入インフレのリスク
日本はエネルギーや食料を海外から輸入しています。円安が進むと、ガソリン・電気代・食料価格が上昇。ドル安でも円高が進まないため、国際商品の値上がりがそのまま生活費の増加につながります。
実質賃金の減少
物価が上がっても、賃金がすぐに増えるわけではありません。2025年に行われた春闘では大手企業を中心に賃上げが進んだものの、中小企業や非正規労働者には波及が限定的でした。結果として、名目賃金は上がっても物価上昇率に追いつかず、「実質賃金」は減少を続けています。
実質賃金が下がると、外食を控える、旅行を見送るといった消費抑制につながります。日本のGDPの約6割を個人消費が占めることを考えると、この影響は極めて大きいと言えるでしょう。
企業に与える影響:輸出企業は有利、内需企業は苦戦
為替の変動は企業活動にも大きな影響を及ぼします。
輸出企業(自動車・精密機械など)
円安はトヨタやソニーなど、グローバルに展開する企業にとって追い風となります。特にユーロ圏に強い企業は、ユーロ高・円安の恩恵を大きく受けます。精密機器や医療機器、工作機械メーカーは欧州市場でのシェアを拡大しやすく、業績にプラス要因となっています。
内需企業(食品・小売・エネルギーなど)
一方で、食品メーカーや小売業、エネルギー関連企業は輸入コスト増に苦しみます。パンメーカーが小麦価格の上昇をすべて販売価格に転嫁できなければ利益は圧迫されます。電力会社も燃料費高騰を料金に反映させざるを得ず、消費者の負担を増やします。
このように、円安は「輸出企業にプラス、内需企業にマイナス」という二極化をもたらし、株式市場でも業種ごとの明暗をくっきり分けています。いわゆる「ワニの口現象」(輸入コスト増と収益低下の乖離)は、業績格差をさらに広げています。
円資産だけに頼るリスク
このような”悪い円安”に対して、私たちはどう行動すべきでしょうか。
答えはシンプルです。円という一つの通貨に依存した資産形成から脱却し、国際的に資産を分散させることです。
ここで強調したいのは、「高いリターンを狙うための投資」ではなく、「資産を守るための投資」という視点です。円の価値が下がり続ければ、たとえ銀行に預金をしていても実質的な資産価値は減っていきます。
悪い円安に対抗するための資産防衛術「グローバル投資戦略」
 資産防衛の基本戦略は、通貨を分散することです。
資産防衛の基本戦略は、通貨を分散することです。
1.ドル建て資産
アメリカは世界経済の中心であり、安定的な成長が見込めます。ドル建て債券や株式は、資産づくりの基本となる柱にしておくと安心です。
2.ユーロや新興国通貨
ヨーロッパは経済が安定していて、リスクが比較的少ない市場です。一方で、東南アジアやインドなどの国々は、これから大きく成長していく可能性があります。そうした国のお金で運用される資産を持つことも、リスクを分散させる意味で検討の価値があります。
3.暗号資産やフィンテック関連
ビットコインのような仮想通貨は、これまでの金融商品とは違う動きをします。価格の変動が激しいためリスクは大きいですが、その分、円やドルといった通貨だけに依存せずに済む効果もあります。さらに、最新の技術を活用した新しい金融サービス(フィンテック関連商品)を一部組み込むことも、資産を分散させる上で有効です。
これらをバランスよく組み合わせることで、円安が長期化しても資産の実質価値を守ることができるのです。
未来に向けた布石を打つ
今の円安は一時的な現象ではなく、日本の金融政策や経済構造の変化という大きな要因に根ざしています。この「悪い円安」は、今後も続く可能性が高いと考えるべきです。
だからこそ私たちは、現実から目をそらさず、早めに資産防衛の行動を起こす必要があります。円に頼らず、世界に目を向けた投資戦略を持つことが、これからの時代を生き抜く大切な鍵になるのです。
将来に備えるための第一歩は、「変化を直視すること」です。そして次の一歩は、自分の資産をどう守り、どう育てるかを真剣に考えることです。グローバルな視点を持つことが、未来に向けた最大の布石となるでしょう。
「未来を備える視点」をぜひ講演で
村田雅志さんの講演では、ここでご紹介した理論だけでなく、最新の市場データや具体的な企業事例を交えながら「経営判断」「資産運用」「家計管理」に役立つ実践的なヒントを得ることができます。複雑に見える為替や金融の動きも、村田さんの解説なら驚くほどわかりやすく、自社の経営戦略や個人の資産形成に直結させることが可能です。
ぜひこの機会に、村田さんの講演を通じて「未来に備える視点」を組織やチームに取り入れてみてはいかがでしょうか?
村田雅志 むらたまさし
経済ナビゲーター

東京工業大・コロンビア大で修士取得、政策研究大学院大学博士課程満期退学。三和総合研究所でエコノミスト、米銀で通貨ストラテジスト、堂島取引所で社長を歴任。政治・経済、金融市場に精通し、メディア出演・寄稿、個人投資家や経営者向けの講演で、市場動向や見通しを独自視点で分かりやすく解説。
|
講師ジャンル
|
ビジネス教養 | 時局・経済 |
|---|
プランタイトル
2為替市場の構造変動とグローバル投資戦略
~「悪い円安」時代を乗りこなし、資産を防衛する方法~
あわせて読みたい
電気・ガス、ガソリンなどの燃料や物価の高騰が家計を苦しめる一方…
これまでにない物価高が家計を直撃しています。少子高齢化で年金の…
これまでお金についてはあまり考えず、仕事をしていたという組合員…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






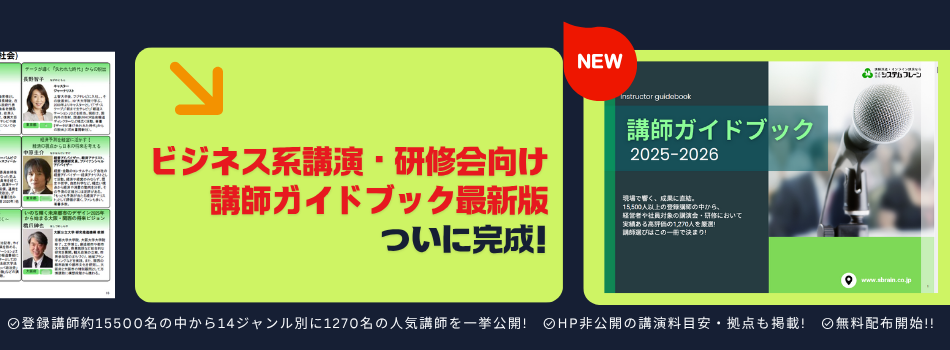
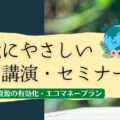










業務外の講師への取次は対応しておりません。