
食育とは「食」に関するさまざまな経験を通じて、子どもたちが生きる力を育むことを指します。保護者からの関心も高く、各教育現場や自治体主催の市民向けイベントでも人気のテーマです。
今回は、20年以上食育活動に携わり農林水産大臣賞を2度受賞した市原るり子氏に、食育の取り組み事例についてお聞きしました。これまで子どもから大人まで2万人以上の人々に「食」について伝え、現場で一緒に体験を作ってきた市原氏ならではの、実践のポイントも解説していただきます。
※本記事の内容は2025年7月時点のものです。
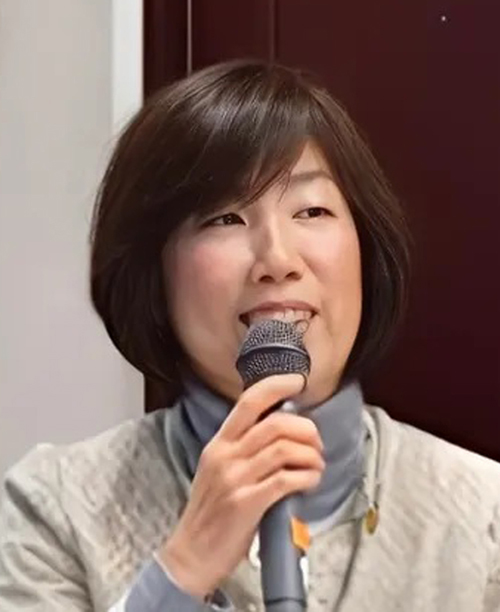 【監修・取材先】
【監修・取材先】
市原るり子氏
教育・子育て関係者
今の時代に食育の取り組みが重要な理由
 かつて当たり前にあった「食」というものが、なぜ今になって子どもの教育の観点から見直されることになったのでしょうか?そこには食生活の変化が大きく関わっています。
かつて当たり前にあった「食」というものが、なぜ今になって子どもの教育の観点から見直されることになったのでしょうか?そこには食生活の変化が大きく関わっています。
共働きが主流となった現代では、親が手をかけて作った料理を囲み、親子で会話をしながら一緒に食べるという光景は当たり前ではなくなってきました。冷凍食品やレトルト食品などのいわゆる「簡便食」と呼ばれる食品の割合が増え、食事風景もどこか慌ただしいものとなっています。
重要なのは、子どもにとって食事がもはや「心動かされる体験」ではなくなっているということです。
例えば、寒い冬の日に家族みんなでコタツに入りながらミカンを食べていたとき、母親に「みかんはビタミンCが豊富だから、風邪をひきにくくなるよ」と言われた記憶は、大人になっても心に残っているかもしれません。
冬の日のコタツの暖かさ、母親の優しい声、ミカンの皮をむく手の感触。こうした感覚が「心動かされる体験」を形作る要素です。そして「みかんはビタミンCが豊富で風邪の予防になる」という知識も、こうした体験と結びつくことで、子どもたちの中でしっかりと根付きます。
こうした体験が、現在の慌ただしい食卓では失われつつあります。。それは単に食べ物についての知識が乏しくなるだけでなく、発達や自己肯定感にも影響を及ぼしかねません。
次の章では、今必要とされる食育の取り組みと、そこで子どもたちはどのような力が身に付くのかを解説していきます。
食育の取り組みの成功事例と、そこで育まれる子どもたちの力
 「食育」には発想次第でさまざまな取り組みが考えられます。ここでは市原るり子氏が実際に地方自治体などに依頼を受けて実践した取り組み事例を紹介していきます。
「食育」には発想次第でさまざまな取り組みが考えられます。ここでは市原るり子氏が実際に地方自治体などに依頼を受けて実践した取り組み事例を紹介していきます。
①「手づかみ食べ」の実践
特に乳幼児のいる家庭を対象とする場合には、「手づかみ食べ」を体験できるイベントが効果的です。離乳食から幼児期にかけて、手づかみで食べるという行為は子どもの発達に大きな影響を与えます。
離乳食というと、親が液状にしたものや細かくしたものを子どもの口にスプーンで運ぶというイメージが強いかもしれません。しかし、そのスタイルはせっかくの食事が子どもにとって非常に受け身なものとなり、「自分で考えてやってみる」機会が失われてしまいます。
例えば柔らかく似た野菜を大きく切って目の前におくと、子どもはそれを自分から手を伸ばし、それを口へ運びながら、「どのくらいの大きさでかじるとよいか」を実践の中で学んでいきます。このとき子どもの脳は非常に活発に働いており、五感をフルに動かして自分の身体の操作方法を習得していきます。
「手づかみ食べ」は子どもがこぼしたり汚したりするため、家庭では敬遠されがちです。こうした背景をふまえ、その有効性を伝え、親子ともに楽しい雰囲気の中で試してみることができるイベントは喜ばれるでしょう。
②野菜の販売体験
小学生を対象した取り組みでは、野菜の選び方や栄養について学んだ後、実際に自分たちで野菜を販売するという体験もおすすめです。
商品棚に置くPOPを作ったり、売り文句を考えたり、ワクワクしながら「どうやれば自分の野菜が売れるか」を考え、実践することもまた「食に関する心動かされる体験」となります。
「絶対に売りたい」というモチベーションがあるとき、子どもたちは最初に学んだ知識を総動員して、売るための工夫を凝らします。インプットからのアウトプットの流れは、大人になってからも仕事で大いに求められる力です。
そして「早く売ろう」として能動的に動く中で、子どもたちは思いがけない能力を発揮することがあります。市原氏のイベントでは、予想もつかないような子どもたちのユニークな売り文句に大人が心動かされ、思わず買ってしまうというシーンが度々見られます。このような発想と実行力を発揮する場を作ることが、伸び盛りの子どもたちの成長には不可欠なのです。
③食についての〇✕クイズ
自治体が主催する取り組みの場合、幼児から大人まであらゆる年齢の参加者がいるケースも少なくありません。また、大規模なイベントの際には、「手づかみ食べ」や「販売体験」、「調理実習」のように個々の対応が必要な取り組みは難しい場合もあります。
そのようなときには、OXクイズなどのシンプルなゲームがおすすめです。食べ物についての問題を出して、参加者全員に〇かXか選んでもらうだけでも、子どもたちは十分「楽しい」と感じやすく、その体験に紐づいた知識がしっかり根付きます。
何よりも〇✕クイズに正解することは、子どもにとって小さな成功体験となり、自己肯定感が育まれます。「食育」の場は、学校の授業やテストではなかなか自己肯定感が育たない子にとっても、生きる力を身に付けるための機会にもなるのです。
食育の取り組みを成功させるポイントは?
 自治体などがイベントを主催して「食育」の取り組みを行うときには、その効果を高めるために3つのポイントを意識することが重要です。
自治体などがイベントを主催して「食育」の取り組みを行うときには、その効果を高めるために3つのポイントを意識することが重要です。
まず1つは、家庭でも無理なく実践できるように伝え方の工夫をすることです。
例えば、「乳幼児の手づかみ食べが発達に良い」としても「必ず毎日行うように」と伝えてしまうと、忙しい両親にとっては精神的にも負担となり、かえって敬遠されてしまう可能性があります。
それよりも「たとえ週末だけでも、手で食べることは子どもの発達にとって貴重な機会になる」と伝えることで、無理のない範囲で実践を促すことができます。
2つめは、イベントの参加者に対して必ず「食育は子どもの未来を作るための土台になる」という考えを共有することです。
ただ栄養や料理の知識を身に付けるためではなく、「子どもたちがあらゆる場面で自分の力で可能性を切り開いていくための取り組み」であることを伝えましょう。そうすることで、大人も子どもたちが見せるちょっとした工夫や主体性の発露に気づき、それらを認めてあげられるようになります。
そして3つめは、「どれだけ子どもたちに成功体験を積ませてあげられるか」という視点でイベントを企画することです。
減点方式といわれる日本の教育では、子どもが「成功を認めてもらう」経験に乏しく、自己肯定感の低さに悩む大人も少なくありません。
「食」という人間にとって必要不可欠であらゆる年齢にも通じる分野で成功体験を積むことで、子どもたちは自分を信じて様々なことに挑戦していく力を育むことができるでしょう。
食育に取り組んで、子どもたちの豊かな「食体験」を育む
 今回お話を伺った市原氏は、記事内で紹介したような食育イベントの運営に加え、茨城県内5か所の「子ども食堂」の立ち上げに携わってきました。
今回お話を伺った市原氏は、記事内で紹介したような食育イベントの運営に加え、茨城県内5か所の「子ども食堂」の立ち上げに携わってきました。
「子どもの貧困」が社会問題として注目される中、子ども食堂は、子どもたちにとっての地域の居場所として大きな役割を果たしてます。市原氏は、子ども食堂が単なる「食事を提供するだけの場」ではなく、「子どもたちの生き抜く力を育てる場所」として、地域社会の中でより重要な役割を担う存在となるよう活動を続けてきました。市原氏がまとめた子ども食堂の運営マニュアルは国からも認められ、農林水産大臣賞も受賞しています。
市原氏の研修では、子ども食堂の運営や地域の食育イベントに携わって得たノウハウや、現場でのエピソードなども紹介されます。現場目線に徹した実践的な内容で、食育の取り組みを深く学びたい方に大変おすすめです。
地域での食育イベントの企画をお考えのご担当者様は、ぜひ次回の研修としてご検討ください!
市原るり子 いちはらるりこ
教育・子育て関係者
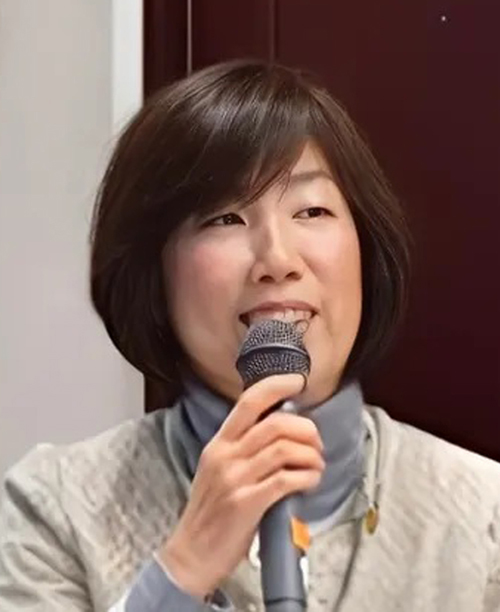
20年以上にわたる食育活動で約2万人に「食の大切さ」を伝え続ける。農林水産大臣賞を2度受賞するなど食育活動で高い評価を受ける。健康で豊かな心と体をつくるための食に関する知識を広く発信し、子どもの食育や地域の居場所づくり、食育教室運営や人づくり、話し方など講演テーマは多岐にわたる。
|
講師ジャンル
|
社会啓発 | 教育・青少年育成 |
|---|---|---|
| 文化・教養 | 健康 |
プランタイトル
子どもたちの生き抜く力を育む『食体験』のすすめ
あわせて読みたい
ゲーム、スマートフォン、インターネットなど、いつでも簡単にアク…
偏食やファーストフード、朝食をとらないなど、子どもたちの食生活…
2021年の総務省「社会生活基本調査」によると、男性の家事・育…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






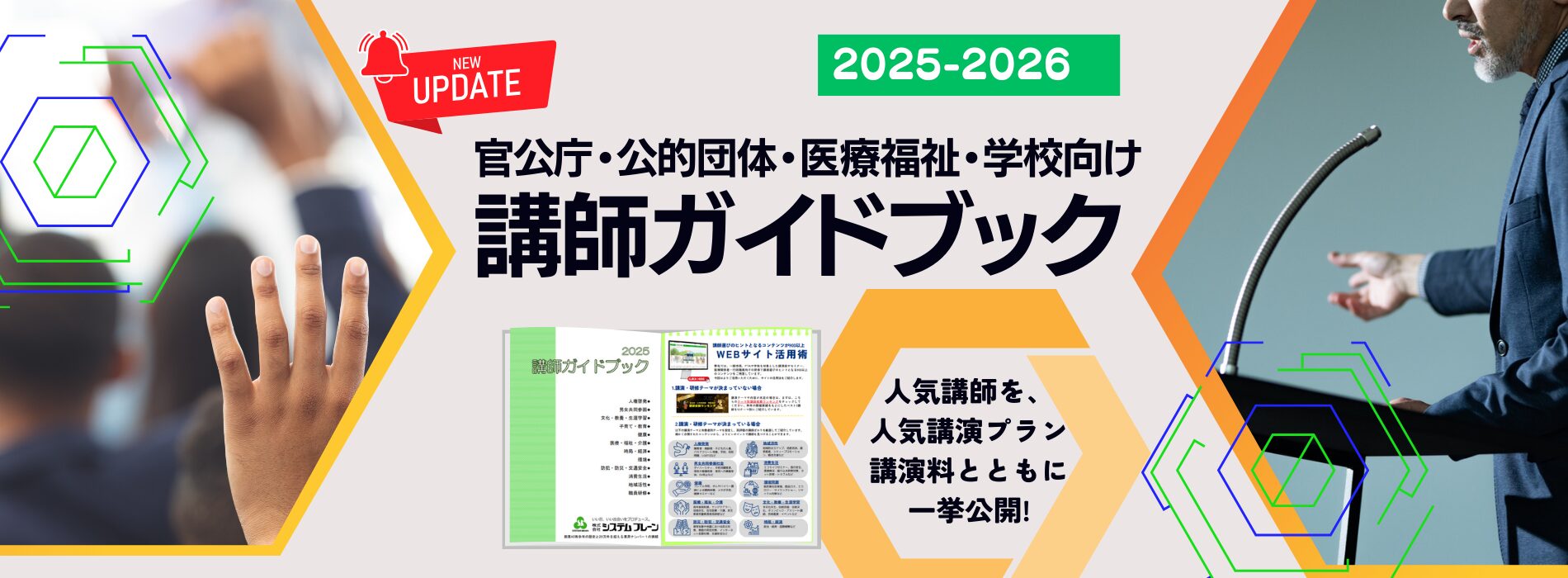

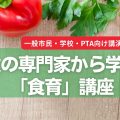









業務外の講師への取次は対応しておりません。