
がん・心疾患・脳血管疾患などの「三大生活習慣病」や、近年増加する認知症――。
これらを未然に防ぐカギは、毎日の「食」と「動き」にあります。
元NHK『きょうの健康』キャスターであり、医療現場の最前線を取材してきた久田直子氏は、「生活習慣病や認知症は、日々の積み重ねで予防できる」と語ります。
本記事では、久田氏の講演内容の一部をもとに、生活習慣病・認知症予防に直結する「食」「運動」「睡眠」についての知見を紹介。
市民向け講演を検討中の企画担当者の皆様にとって、注目を集める講演テーマを選ぶためのヒントとなる内容です。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
久田直子氏
元 NHK「きょうの健康」キャスター
なぜ今、生活習慣病予防が重要なのか
 厚生労働省の統計(※1)によれば、日本人の死亡原因の多くを「がん」「心疾患」「脳血管疾患」が占めており、これらはいずれも生活習慣と深く関わる病気です。また、要介護の主な原因(※2)としても1位「認知症」2位「脳卒中」3位「転倒・骨折」の順位となり、生活習慣病との関わりが指摘されています。
厚生労働省の統計(※1)によれば、日本人の死亡原因の多くを「がん」「心疾患」「脳血管疾患」が占めており、これらはいずれも生活習慣と深く関わる病気です。また、要介護の主な原因(※2)としても1位「認知症」2位「脳卒中」3位「転倒・骨折」の順位となり、生活習慣病との関わりが指摘されています。
これらの病気は年齢とともにリスクが高まりますが、見逃してはならないのは「予防が可能」だという点です。実際、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病は、食事や運動習慣を整えることで発症リスクを大きく抑えることができます。
加えて近年、企業における「健康経営」も注目されています。従業員の健康管理を経営戦略に組み込み、組織全体の生産性向上を目指す動きです。これは、働く世代の健康維持を「個人の責任」から「組織の責任」へと転換する考え方でもあります。
つまり、生活習慣病の予防は「高齢者の課題」だけでなく、「現役世代の課題」でもあり、地域や企業を問わず、多くの人にとって関心の高いテーマなのです。
※参照1:令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況
※参照2:2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況
今日から始める生活習慣病予防の食事術
食べ方を変えるだけでも健康への第一歩になります。ここでは、久田氏が提唱する具体的な食事術をご紹介します。
① 厚労省が提唱する「健康日本21」で示された野菜摂取目標
「野菜をもっと食べましょう」――そう言われても、具体的にどれだけ食べれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。久田氏が講演でまず伝えているのは、厚生労働省が進める健康増進施策「健康日本21」で定められている目標数値です。
「成人1人あたり、1日に野菜を350グラム摂ることが推奨されています。これは生野菜なら両手いっぱい、加熱野菜なら片手に山盛り一杯分くらいの量になります」と久田氏。野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維といった栄養素が豊富に含まれており、生活習慣病予防には欠かせません。
特に注目すべきは、“緑黄色野菜”と“淡色野菜”のバランスです。色の濃い野菜(ほうれん草、にんじん、ピーマンなど)には抗酸化作用を持つ栄養素が多く含まれ、淡色野菜(キャベツ、大根、もやしなど)には水分や食物繊維が豊富です。生で食べたり、炒めたり、煮たりと、調理法を変えることで飽きずに続けられます。
講演では、実際に350gがどれくらいなのかを写真付きで紹介し、参加者にイメージしてもらいやすくする工夫もされています。
② 血糖値の急上昇を抑える脂肪やたんぱく質の役割
「同じメニューでも、食べる順番や食べ合わせによって、体への影響は大きく変わります」。そう語る久田氏が注目するのが、「血糖値スパイク」の予防です。
血糖値スパイクとは、食後の血糖値が急激に上がり、その後急激に下がることを繰り返す状態。自覚症状がないまま進行し、動脈硬化や糖尿病のリスクを高めることが近年の研究でわかってきました。
この血糖値の急上昇を防ぐためには、糖質の前に“たんぱく質”や“脂質”をとるのが有効です。特に、ゆで卵や納豆、豆腐、魚、肉などを先にとると、糖質の吸収がゆるやかになり、血糖値が急上昇しにくくなります。
加えて、食物繊維も重要な役割を果たします。野菜を最初に食べる「ベジファースト」は、血糖コントロールの基本として広く推奨されていますが、最近ではたんぱく質や脂質を食事の最初に取ることで、血糖値の急上昇が抑制されることが注目されています。食事の食べ方、食べる順番に注目することは、久田氏の講演でも「簡単にできて続けやすい予防法」として紹介されています。
久田氏は「『何を食べるか』も大事ですが、『どう食べるか』にも注目することが、日常生活でできる大きな健康対策です」と、食の“順番”を意識することの重要性を強調しています。
③ 栄養素バランスを整える「定食スタイル」思考のすすめ
 栄養バランスが大切とはわかっていても、毎食それを意識するのは難しいですよね。そんなときに役立つのが“定食スタイル”の考え方です。
栄養バランスが大切とはわかっていても、毎食それを意識するのは難しいですよね。そんなときに役立つのが“定食スタイル”の考え方です。
久田氏が提唱する“定食スタイル”とは、和定食のように「主食・主菜・副菜・汁物」を基本構成とした食事法です。たとえば、白米(主食)、焼き魚(主菜)、ほうれん草のおひたし(副菜)、味噌汁(汁物)といった形にすると、自然と栄養バランスが整います。
このスタイルの利点は、外食やコンビニでも応用しやすいこと。単品の丼物や麺類よりも、“おにぎり+サラダ+スープ”のように組み合わせを工夫するだけで、体に優しい食事になります。
講演では、受講者が自分の食生活を見直せるよう、「コンビニで買える定食風メニュー例」なども紹介されています。「完璧を目指すのではなく、“少しずつ意識すること”が、生活習慣病予防にはとても大切なんです」と久田氏は語ります。
④ 健康なアルコールの適量とは?
最後に、多くの人が「まあ少しぐらいなら」と思いがちな“アルコール”について。久田氏は「適量を知ることが、長く楽しむコツです」と警鐘を鳴らします。
厚労省によると、健康的なアルコールの摂取量は「純アルコールで1日20gまで」が目安とされています。これは、日本酒で1合(180ml)、ビール中瓶1本(500ml)、ワイングラス2杯(240ml程度)に相当します。
“自分は強いから大丈夫”と思っている方ほど、習慣的な過剰摂取に陥りやすい傾向があります。飲酒量が多い人ほど、高血圧、肝機能障害、がん、認知症などのリスクが高くなることが知られています。
また、女性や高齢者、薬を服用している人は、同じ量でも体への影響が大きくなるため、より慎重な対応が求められます。
「お酒を完全にやめる必要はありません。でも、“適量”を知って、それを守ることが“健康的に飲み続ける”秘訣なんです」。
久田氏の語り口は、押しつけではなく、あくまで“より良い選択”を促すもので、多くの参加者から共感を得ています。
このように、「野菜を意識的に摂る」「血糖値の急上昇を防ぐ食べ方」「定食スタイルの導入」「アルコールとの付き合い方」など、どれも今日から始められる具体的な行動ばかり。
「何をどれだけ食べるか」よりも、「日々の積み重ねをどう工夫するか」が生活習慣病予防の鍵になる――。久田氏の講演には、その実践ヒントが満載です。
脳と体を同時に動かす!認知症・生活習慣病予防の運動とは
 「運動が大事なのはわかっているけれど、何をすればよいか分からない」という声も多く聞かれます。そんな市民に向けて、久田氏は「日常生活の中に運動を取り入れる方法」をわかりやすく伝えます。
「運動が大事なのはわかっているけれど、何をすればよいか分からない」という声も多く聞かれます。そんな市民に向けて、久田氏は「日常生活の中に運動を取り入れる方法」をわかりやすく伝えます。
たとえば、「メッツ(METs)」という運動強度の単位を用いれば、日常の活動が運動としてどの程度効果があるかがわかります。軽い掃除で2.5メッツ、早歩きで4メッツ、階段昇降は8メッツなど、意識次第で“運動”は身近なところにあります。
加えて、認知症予防の観点から注目されているのが「コグニサイズ(Cognicise)」です。これは国立長寿医療研究センターが開発したプログラムで、「認知(Cognition)」と「運動(Exercise)」を組み合わせた造語です。歩きながらしりとりをする、計算をしながら体操するなど、「頭と体を同時に使う」ことで脳と身体の機能を同時に高める効果があります。
このような運動は、年齢や体力に関係なく誰でも始められるのが魅力。地域の講演会で紹介されると、多くの参加者にとって「目から鱗」の内容となるでしょう。
合わせて読みたい
睡眠時無呼吸症候群に注意!運動と体重管理の重要性
「夜にしっかり眠っているはずなのに、日中眠くなる」「朝起きても疲れがとれない」といった症状を訴える人が増えています。その原因のひとつが、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」です。
これは、睡眠中に気道が塞がれて呼吸が止まる状態が繰り返される病気で、特徴的な症状として、大きないびき、呼吸停止の目撃、日中の強い眠気、夜間の頻尿などがあります。
放置すると、心筋梗塞や脳卒中、高血圧、糖尿病といった重大な病気のリスクを高めるため、早期発見と対処が重要です。原因の多くは「肥満」にあり、特に仰向けで寝ることで舌根や軟口蓋が気道をふさぎやすくなる構造もあります。
久田氏の講演では、こうした医学的な背景もわかりやすく解説され、参加者が「自分の生活を見直す」きっかけを得られる構成になっています。
市民を惹きつける講演スタイルとは?
久田直子氏の講演が高く評価されている理由には、「親しみやすさ」「具体性」「実践性」の3つがあります。
医療現場での豊富な取材経験を活かし、専門的な情報も「生活の言葉」で語るため、誰にでも理解しやすいのが特徴です。たとえば、「アルコールの適量を日本酒やビールの量で説明」「野菜摂取の目安を定食スタイルで表現」など、実生活と直結した表現が共感を呼びます。
また、講演後には「すぐに取り入れたくなる内容だった」「明日からやってみようと思える」といった感想が多く寄せられるのも特徴。これは単なる知識の提供ではなく、「行動変容」を促す力がある証です。
市民対象の講演では、「理解できた」で終わらず、「動いてみよう」と思ってもらえることが、最大の成果です。
行動変容を促す“生活習慣病予防”講演の決定版
高齢化社会が進む日本において、「健康寿命の延伸」は避けては通れない課題です。がんや心疾患、認知症などのリスクを軽減するためには、医療だけでなく、日々の生活に目を向けることが何より大切です。
久田氏の講演は、そうした市民の意識改革に最適な内容が詰まっています。「難しい話は苦手」「運動や栄養の話は専門的すぎて…」という人にも届く言葉で語られる講演は、まさに“健康講演のスタンダード”といえるでしょう。
地域イベント、自治体主催の健康教室、企業の健康経営セミナーなど、幅広いニーズに対応できる講演です。市民の健康意識を高めたいと考えている講演企画担当者の皆様、ぜひご検討ください。
久田直子ひさだなおこ
元 NHK「きょうの健康」キャスター

NHKの健康情報番組「きょうの健康」司会を15年間務める。話を聞いた医師、医療、介護関係者は700人以上。生活習慣病、認知症、がん、女性の健康、高齢者の食事と運動、セカンドオピニオンの取り方や医師からの話の聞き方、医療情報の取り方など、幅広いテーマで講演を行っている。
|
講師ジャンル
|
社会啓発 | 福祉・介護 | 男女共同参画 |
|---|---|---|---|
| 文化・教養 | 健康 |
プランタイトル
元NHK「きょうの健康」キャスターが伝授!
~病気の予防につながる食事と運動とは?~”
あわせて読みたい
ゲーム、スマートフォン、インターネットなど、いつでも簡単にアク…
偏食やファーストフード、朝食をとらないなど、子どもたちの食生活…
2021年の総務省「社会生活基本調査」によると、男性の家事・育…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






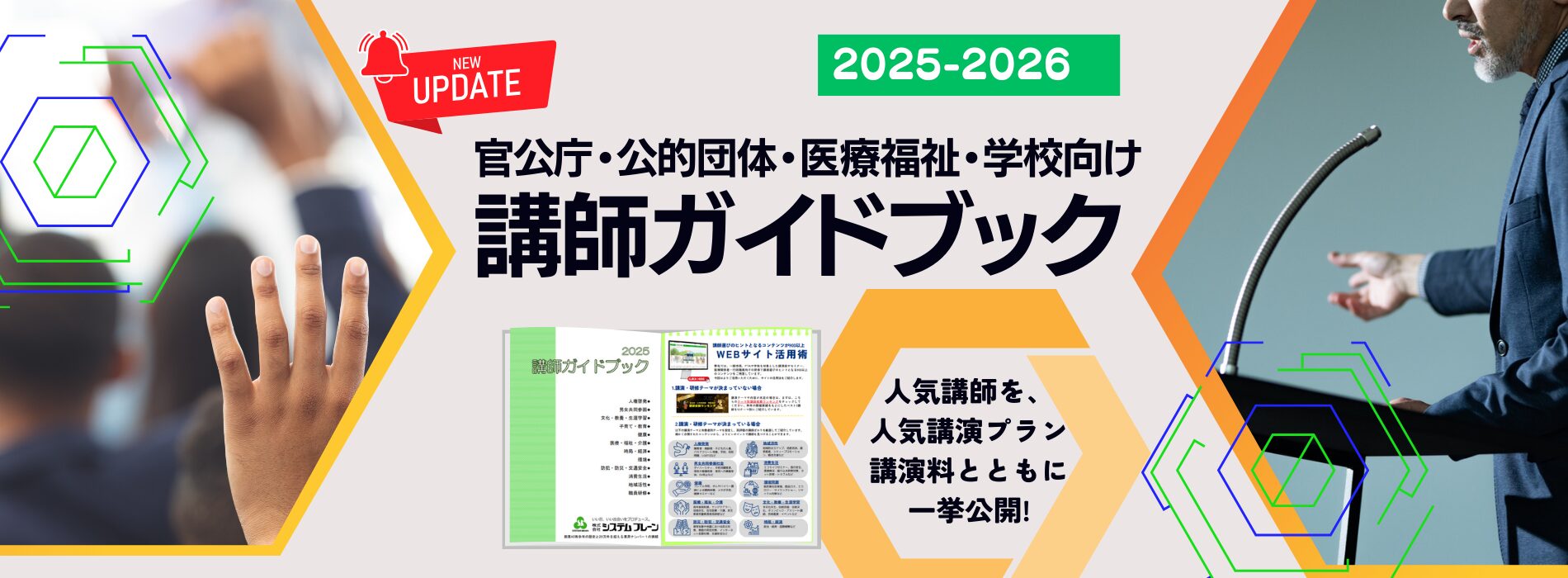

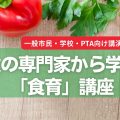









業務外の講師への取次は対応しておりません。