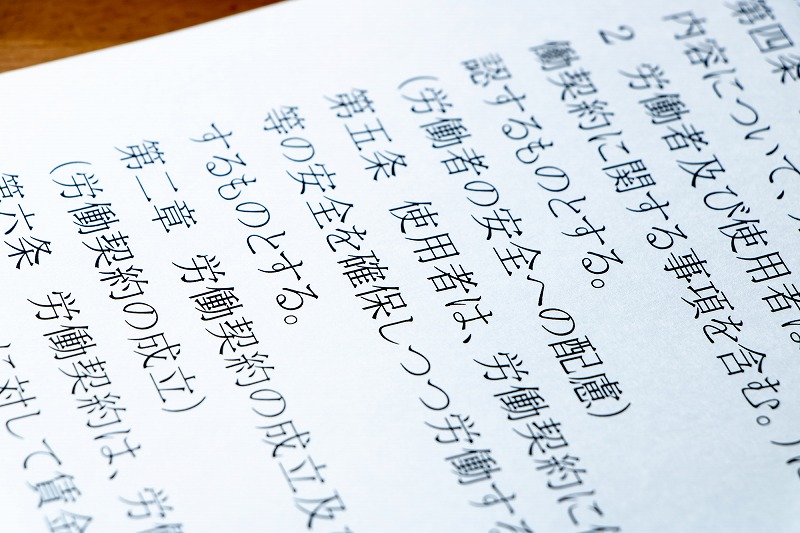
働くすべての人の安全と衛生は、厚生労働省が定める「労働安全規則」によって守られています。この規則は2025年にも改正があり、変更内容について企業から注目されています。
この記事では、2025年の改正ポイントや関連法令との違い、主な内容について解説します。安心して働きつづけられる職場づくりにぜひ生かしてください。
労働安全衛生規則(安衛規)の基本
労働安全衛生規則について、その位置付けや対象者、2025年の改正ポイントなどについて説明します。
労働安全衛生規則とは何か
労働安全衛生規則(略称・安衛則」は、労働者の安全と衛生を確保するために、1972年に厚生労働省が定めた「省令」です。
国会で審議され可決を経て試行される「法律」とは異なるものの、法律のもとで、事業者(企業・職場)に対して職場環境の安全基準を守る義務を課しています。
規則の4つの構成
安衛則は「通則」「安全基準」「衛生基準」「特別規制」の4つに分類されています。
法律ではないものの法的な拘束力を持ち、違反すれば罰則が科されることもあります。しかしながら、法的根拠にかかわらず、労働災害や従業員の健康障害を予防することは、企業の責任として重要です。
規則の対象者
安衛則のうち「通則」は、全業種に共通する項目を含んでいます。
このほか、労災発生件数の特に多い製造業や建設業、運送業などの現場業務に直結する規定が多くなっています。業務上の危険性に関する具体的な基準や対策について、業種ごとに定めています。
2025年の改正ポイント
 2025年4月の改正ポイントは主に2つです。
2025年4月の改正ポイントは主に2つです。
まず、建設業の企業に、企業の従業員のみならず「一人親方」や「他社の労働者」も危険箇所で作業のおいて保護対象とすることが義務化されました。退避や立入禁止措置の拡大、作業中の保護具使用や作業方法についての周知義務も伴います。「現場で働くすべての労働者が安全対策を受けられるようにする」というねらいがあります。
また、熱中症対策も義務化されました。対象は、暑さ指数など所定の基準を超える(特に屋外作業や高温環境下での作業を含む)職場です。温度管理や水分補給、休憩時間の設定などの施策で、作業員が熱中症にならないよう、企業側も配慮しなければなりません。
関連法令などとの違い
 労働安全衛生規則は、さまざまな労働関連法とも密接に関わっています。似た目的を持つ法律などとの違いはどこにあるのでしょうか。
労働安全衛生規則は、さまざまな労働関連法とも密接に関わっています。似た目的を持つ法律などとの違いはどこにあるのでしょうか。
労働安全衛生法(安衛法)との違い
労働安全衛生法(略称・安衛法)と安衛則は、いずれも「労働者の安全と健康を守ること」を目的とした重要な法令です。それぞれ1972年に制定されました。
安衛法は職場における安全衛生管理の基本的な枠組みと、企業の包括的な責任を定めています。一方安衛則は、安衛法に基づいて、具体的な作業方法、安全基準、衛生管理方法などを詳しく規定しています。
具体的には、安衛法では、健康診断を受けさせる義務や職場環境の管理、事業者が講じるべき安全対策の基本的な方針を明らかにしています。安衛則は、さらに実践的な指針として、機械設備の具体的な安全基準や作業場の環境基準、危険物質の取り扱い方といった事項を示しています。
労働基準法
労働基準法(略称・労基法)は、労働者の保護を目的としている点で共通していますが、目的や適用範囲に違いがあります。
労基法は賃金、労働時間、休暇、労働環境など、「労働条件全体」に関する基準を規定しています。安衛法および安衛則は、労働者の「健康と安全」に関する基準を示しています。
労働契約法(安全衛生配慮義務)
労働契約法では、企業に雇用者の生命や身体の安全を確保するための「安全配慮義務」が課されています。
重点を置いているのは、安全配慮義務では「従業員の心身の健康」であり、安衛法では「職場環境の安全と健康」です。働く人の心身の健康は、2つの法律で保護されているのです。
労働安全衛生規則の主な内容
労働安全衛生規則が具体的に定めている内容について、7つを紹介します。
1.安全衛生管理体制の確立
安衛則の第二章では「安全衛生管理体制」を規定しています。
企業はその業種や規模に応じて、社内に安全衛生管理体制を構築しないといけません。体制とは、安全衛生に関わる役割や組織を置くことです。
例えば「衛生管理者は50人以上200人以下の事業場に1人」など、業種や規模に求められる体制を細かく取り決めています。
2.従業員への安全衛生教育
従業員を労働災害から守るための安全衛生教育のガイドラインも、安衛則で明示されています。
例えば「雇入れ時・作業内容変更時の教育」もこれに含まれます。また「特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)」の対象業務も、安衛則で非常に細かく設定されています。
3.健康保持・増進のための措置
労働者の健康保持・増進に関して、企業が推進すべきことについても安衛則に含まれます。
特に作業環境や作業内容による健康リスクを正しく把握し取り除くことや、健康診断やメンタルヘルスケアによる管理、心身の健康を保持する活動の支援・指導を求めています。
4.就業制限
就業制限、すなわち「免許取得や技能講習を修了者などでなければその業務に就かせてはならない業務」についても安衛則で厳密に定められています。
例えば、発破作業やボイラーを取り扱う業務、所定の条件を満たした重機の運転や高所作業などがあります。
5.機械・危険物・有害物の取り扱い規制
安衛則では、危険な機械や有害物・化学物質については、製造や譲渡に関する規制を設けています。
一例として、特定の機械は、都道府県労働局長による検査や適切な安全装置が必要です。また有害物や危険物の製造には許可を受けることや、譲渡時の警告表示や情報提供も義務化されています。
6.安全基準・衛生基準
安衛則で決められた安全衛生の基準には、機械や化学物質に関する危険回避基準や衛生的な環境整備、保護具の使用などについての項目が含まれています。
その中で、例えば作業場所の照度・トイレの数や設計・室温などについても明確に基準が記載されています。
7.その他特別な規制
「特別規制」と題した条文では、特定の業種や作業に関わる人に対する危険防止措置などを規定しています。
対象は土石流や機械転倒のおそれがある場所での作業や、機械・建築物を貸し出す人に求められる対応を明文化しています。
引用:労働安全衛生規則
安全衛生規則順守のための企業の施策例
それでは、近年の安全衛生規則改正によって企業が実際に取り組んだ施策の例を、改正ポイント別に紹介しましょう。
例①健康診断報告書の提出
 現在では多くの企業が、従業員の一般健康診断や有害業務従事者の歯科健診について、実施後速やかに報告書を所轄労働基準監督署へ提出しています。
現在では多くの企業が、従業員の一般健康診断や有害業務従事者の歯科健診について、実施後速やかに報告書を所轄労働基準監督署へ提出しています。
これは2022年の規則改正により、以下の2つの点が変更になったためです。
- 歯科健康診断書の提出はそれまで「常時50人以上を雇用する職場」に限定されていたが、人数不問となった
- 特定の有害物質を業務で扱う職場に関して、従事者の歯科検診診断の実施・報告書提出が義務付けられた
この例では、診断の実施だけでなく、結果の提出についても規定の変更対象となっている点が重要なポイントです。
例②化学物質管理強化への対応
2022年には化学物質規制が強化され、2024年からはリスクアセスメント対象物を製造・取り扱う企業に「化学物質管理者」の選任が義務付けられました(一般消費者向け製品のみを扱う事業場は対象外)。対象企業は、以下のような施策を進めました。
- 化学物質のリスクアセスメント:職場で使用する化学物質に関するリスクを改めて特定・評価
- 管理者選任:管理者は厚生労働省の定める講習を受け、その後も継続的な教育で関連する知識を習得
- 安全対策強化:換気の頻度やルールの変更・保護具の着用徹底など
例③ 救急用具に関するルールの改正
2021年の改正では、職場に備えるべき救急用具のルールが変更されました。従来は「どんな物を置いておかなければならないか」を一律に定めていましたが、改正後は、各企業の実情に応じた柔軟な対応が可能になりました。
- そろえておくべき救急用具の内容を、規定から削除
- 産業医や衛生委員会の意見をもとに、職場で発生し得る労災に応じた救急用具を準備
労働安全衛生規則を守らないとどうなるか
それでは、労働安全衛生規則を守らなかった場合、企業にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。罰金・罰則の詳細と、違反事案を防ぐ方法についても解説します。
違反時の罰金・罰則
労働安全衛生規則に違反した企業は、罰金・罰則を科されることがあります。
内容は違反の種類や程度によって異なるものの、罰金は「50万円以下」から「300万円以下」、懲役は「6カ月以下」から「3年以下」まで、さまざまなケースがあります。
刑事罰はあくまで「違反に対する罰則」であり、労働基準監督署の是正指導(行政指導)を受けて従わなかった場合などに科されることが多いです。
労働基準監督署の指導・監査
労働基準監督署には、安全衛生課や労災課があります。安衛法・安衛則への違反行為があった場合、特に結果として労災を起こしてしまうと、企業は労働基準監督署の監査・指導を受けることになります。
健康診断の報告書提出について罰則は設けられていませんが、常時50人以上が働く職場では、実施後速やかに提出するようにしましょう。
事故や違反事案を防ぐには安全教育が重要
違反事案を防ぐには、全社的に安全衛生への意識を高めなければなりません。細かな規則の変更にも、漏れずに対応する必要があります。
「知らなかった」「甘く見ていた」ということのないよう、いま一度、社内の安全衛生教育について見直してみましょう。安全衛生の専門家の知見に相談するのも一案です。
安全衛生教育には専門家による研修・講習が効果的
安全衛生教育には、経験豊富な講師による、研修や講習がおすすめです。
「職場の安全衛生対策が形式化してしまい効果が出ていない」「社内に適切な講師人材がいない」「第三者視点からのアドバイスが欲しい」などのお悩みがあれば、ぜひプロによる研修・講習の実施をご検討ください。
以下のボタンから、弊社で人気の安全管理・労働災害防止の講師を閲覧できます。
安全衛生規則は、労働安全衛生法とともに、労働者が職場で安心して健康に働きつづけられる基盤を作るガイドラインです。時代にそくして規則も変化しています。自社の事業や業務に関わる改正動向をチェックし、職場の環境改善を進めましょう。
あわせて読みたい
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
他の記事をみる









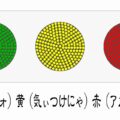









業務外の講師への取次は対応しておりません。