
「気をつけていたのに、なぜ事故が起きたのか」
現場で働く皆さんの中には、そんな経験をされた方もいるのではないでしょうか。
ヒューマンエラーは、決して能力が低い人だけが起こすものではありません。誰にでも起こりうるからこそ、私たちは“仕組み”と“コミュニケーション”で防いでいく必要があるのです。
本記事では、コミュニケーション講師の森川あやこ氏が、全国の現場でお伝えしている「思い込み」や「確認不足」を防ぐ具体策を、5つの視点から解説します。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
森川あやこ氏
人材育成コンサルタント
スマイル幸師®
RSTトレーナー
「確認したつもり」が一番危ない――“うっかり”の正体は習慣にある
 まず、最も多いヒューマンエラーの原因が、「確認したつもりになっていた」ことです。
まず、最も多いヒューマンエラーの原因が、「確認したつもりになっていた」ことです。
これは、能力の問題ではありません。人間の脳の仕組み上、「慣れた作業は無意識に行われる」からです。ルーティン化された動作ほど、チェックを省略しやすくなり、「やったつもり」が生まれてしまいます。
講演では「エラーパターン診断テスト」という簡単な自己診断を紹介しています。たとえば、こんな経験はありませんか?
- 待ち合わせをすっぽかした
- 電気を消し忘れた
- ポストに入れるはずの郵便物をかばんに入れたままにしていた
これらはすべて、脳の“習慣回路”が引き起こすエラーです。
このような“うっかり”を防ぐには、「自動運転」状態から意識を戻すことが必要です。そのために効果的なのが、「声かけ」と「一拍置く確認」。
たとえばチェックリストに書いてある作業でも、「指差し確認」をして「OK!」と声に出すだけで、脳が“意識的”な確認モードになります。
「これぐらい平気」が命取り――“MASOKU”という6つの思い込み
事故の背景には、“まさかこんなことで”という思い込みが潜んでいます。
森川さんはこれを、6つの頭文字を取って「MASOKU」と名づけています。
- M:まさか自分が
- A:あんなことで事故になるなんて
- S:そんなつもりはなかった
- O:おれに限って
- K:これぐらいなら大丈夫
- U:うちは今まで問題なかった
どれか一つでも心当たりがあれば、注意が必要です。
たとえば、「いつも使ってる工具だから確認しなくても大丈夫」と思った結果、締めが甘くなり部品が外れた――そんな事故は現場で何度も起きています。
思い込みに気づくには、「人に話す」ことが最も有効です。
ミーティングや朝礼で、自分の作業計画を他人に説明する時間を設けてみてください。自分の考えを言語化することで、「これは思い込みかも」と気づくきっかけになります。
声かけだけでも事故は減らせる――4Mで現場の“抜け”を点検する
ヒューマンエラーを減らすには、「4M」という視点が欠かせません。
これは、森川さんが全国の現場で伝えている、事故防止の基本です。
- Man(人):慣れや不注意、不安定な心理状態
- Machine(設備):老朽化や整備不足、点検ミス、不安全状態
- Media(手順):不明確なマニュアル、非効率なルール
- Management(管理):伝達不足、風通しの悪さ
この4つのどこかに“抜け”があると、事故のリスクは一気に高まります。
たとえば、設備に異常が出た際、「Aさんに任せれば大丈夫」と思い込んで放置した結果、機械がオーバーヒートし、Aさんがやけどを負ったという事例があります。
このような事故は、「Man」と「Management」の両方に問題があります。
日々の声かけやミーティングで、「最近、やりづらくなった作業はない?」「使いにくいマニュアルはある?」と聞いてみるだけで、4Mの“抜け”を早期に見つけることができます。
危険を察知する力は“感受性”で育つ
「まさかこんなところに危険が…」というケースでは、事前に“気づけた人”がいたことも少なくありません。
その人は声を出せなかった、または「気のせいだ」と感じて終わってしまった。
これを防ぐには、“感受性”を育てるしかありません。
森川さんが現場で伝えているのは、次の4つの「配り」です。
- 目配り:周囲の変化に目を向ける
- 耳配り:異音や会話のトーンに気づく
- 心配り:仲間の様子、心理的な変化を察知する
- 手配り:手順を丁寧に行う意識
感受性は、年齢や経験だけでは身につきません。
“想像する訓練”を意識的に行うことが必要です。
「もし自分だったら?」「家族が同じ現場にいたら?」と想像しながら作業計画を立ててみてください。日常の行動に“危機管理の視点”が宿るようになります。
「伝えたつもり」が事故を生む――“伝わる”指示の出し方
最後に、ヒューマンエラー防止でもっとも軽視されがちなポイントが、「伝えたつもり問題」です。
「ちゃんと言ったはずなのに、やってなかった」「注意したのに、伝わっていなかった」
これもよくある事故の原因です。
“伝わる”指示に必要なのは、以下の3つの技術です。
- 省略しない:誰が、何を、いつ、どこで、どのように。これらを端折らず伝える
- イメージで伝える:「こうやって、ここに置いて」ではなく「棚の右から2段目に、赤いケースを左向きに並べて」など、相手が“絵”で浮かぶように
- 相手に話させる:「今の作業手順、もう一度説明してみて」と、確認の言葉を引き出す
「注意しろ」では防げません。大切なのは、“具体的な指示”と“確認の習慣化”です。
組織全体の習慣化が肝要
ヒューマンエラーは、“一人の注意不足”ではなく、“組織全体の習慣”として起きるものです。
だからこそ、日々の声かけ・想像力・感受性・共有の仕方といった、“当たり前の行動”を丁寧に見直すことが、事故ゼロの現場につながります。
スマイル幸師・森川あやこさんによる講演では、「うっかり」「まさか」を防ぐ実践的な手法とコミュニケーション術を、参加者が“自分ごと”として捉えられるよう伝えています。
現場で働く皆さんの「安全」は、ご自身と仲間、そしてご家族の「安心」に直結します。
安全大会の講演テーマとして、現場力を底上げする内容をお探しの方は、ぜひ一度、講演の詳細をご確認ください。
「まさか」をなくすために、「いま、ここ」でできることを、今日から一つずつ始めてみませんか?
森川あやこ もりかわあやこ
人材育成コンサルタント スマイル幸師® RSTトレーナー

78000人のオーディションで、グランプリとフォトジェニック賞をW受賞し、映画に準主役で出演した元アイドル女優。また、リポーター経験を通して、伝える、表現することの大切さを実感。研修講師としての実績も多く、各地で毎回キャンセル待ちが出る大人気講師。
|
講師ジャンル
|
ビジネス教養 | ワークライフバランス | メンタルヘルス |
|---|---|---|---|
| ライフプラン | |||
| ソフトスキル | リーダーシップ | コミュニケーション | |
| モチベーション | |||
| 実務知識 | 安全管理・労働災害 | その他実務スキル | |
| 顧客満足・クレーム対応 |
プランタイトル
STOP労働災害!
ヒューマンエラーをコミュニケーションで防ぐ!
あわせて読みたい
ヒューマンエラー(人為的ミス)は、誰にでもどんな状況でも起こり…
気をつけていても起きるのが”ヒューマンエラー”と呼ばれる人的ミ…
建設現場や工場で起きる災害は大きなものだけではありません。実は…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






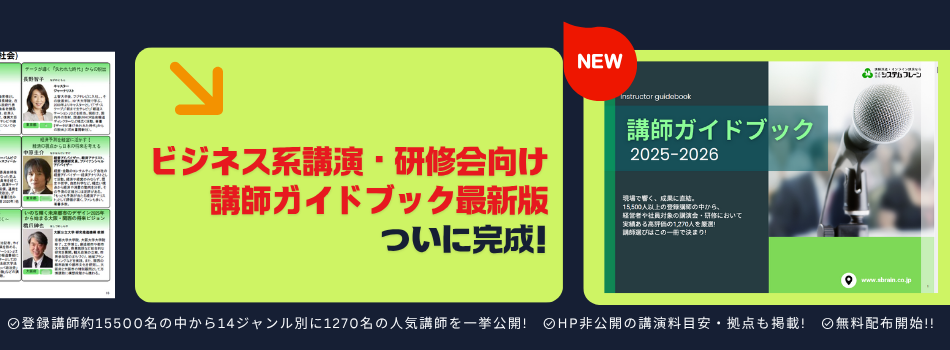











業務外の講師への取次は対応しておりません。