
情報やサービスがあふれ、差別化や顧客の感情への訴求が不可欠な現代。北米発の「カルトブランディング」は、商品やサービスの枠を超え、信念や価値観を共有する熱狂的ファンを育成し、そのファンの発信(口コミ)により自然とコミュニティーが広がっていく新しいブランド戦略です。
今回は、国内カルトブランディング論の第一人者・田中森士さんに、カルトブランディングの必要性や導入プロセスなどを伺いました。顧客から選ばれ続けるブランドを目指す上でのヒントが詰まっています。
※本記事の内容は2025年6月時点のものです。
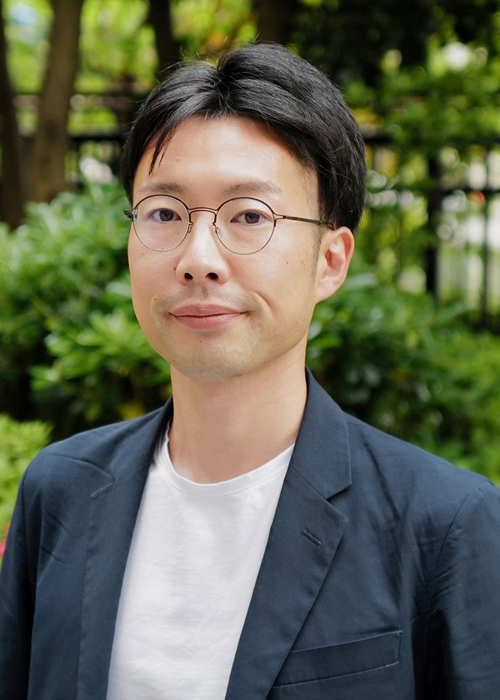 【監修・取材先】
【監修・取材先】
田中森士氏
株式会社クマベイス 代表取締役CEO
アジアスモールビジネス連盟 日本(ASBF Japan)代表
コンテンツマーケティングコンサルタント
ブランド戦略の重要性が増している背景とは?
 ブランドの価値を高めるブランディングの重要性が高まる背景には、主に以下の3点があります。
ブランドの価値を高めるブランディングの重要性が高まる背景には、主に以下の3点があります。
① 情報の流通量の増大
AIの進化により情報流通量は爆発的に増加し、私たちは情報過多の状態です。
膨大な情報から必要なものを選ぶのは難しく、従来の広告ではメッセージが伝わりにくいため、ブランドと消費者とのより強い関係構築が必要です。
② 小さく深く、そして増加するコミュニティー
情報量の増大に伴い、商品やサービスが消費者に届く経路(チャネル)は多岐にわたっています。以前は、会社や学校などで共通の話題がありましたが、今ではそれが難しくなっています。これは、小規模なコミュニティーが多数存在し、かつコミュニティーに属する人たちの興味関心がより深まっているのが要因です。「推し活」や「〇〇沼」などの言葉がこれを象徴しています。
アウトドアやキャンプ業界に見られるガレージブランドは、小規模ながらも素材やデザインにこだわった製品を、少量生産・販売しています。熱狂的なファンを持つブランドが多く、車のリアガラスにブランドのステッカーを貼っている人をよく見かけます。これは、コミュニティーが小規模化し専門性が高まっている現代市場の一端を示しています。
また、現代ではAIの活用や一部の業務を外部委託することによって、個人でもブランドを立ち上げやすくなっています。これは、小規模なコミュニティーが増えている市場の変化に適した手法と言えます。
③ 消費者のマインド変化
消費者は、意味のある商品やサービスを求める「意味消費」へと変化しています。特に、Z世代以降の若い世代は、単なる消耗品としての消費ではなく「社会貢献」や「ストーリー性」など、意味のあるものを重視しています。商品に付加価値として何らかの意味を求める傾向が強まっているのです。
それに伴い、ブランド側も、ブランド立ち上げの経緯やブランドに込めた想いを発信するようになっています。このように、時代に合わせたコミュニケーションに取り組んでいるブランドこそが、今の市場で生き残っています。
長期的なファンを生み出す「カルトブランディング」とは?

熱狂的なファン(≒信者)を持つ「カルトブランド」を目指すブランド戦略を「カルトブランディング」と呼びます。「信者」はブランドに対する高い忠誠心と献身性を持ち、自分とブランドとの関わりを自発的に発信します。これにより消費者の「自分らしくありたい」という自己実現欲求を満たし、結果的にブランドの宣伝にも繋がります。カルトブランディングでは、「信者」による自発的な発信を「非合理的な忠誠心」と呼びます。
日本における例として、スズキのジムニーが挙げられます。納車までに1年以上要すほどの人気ぶりですが、もともとそのデザインや機能は、林業従事者などプロユーザー向けに設計されたものでした。その一方で、マーケティング戦略では、プロユーザーだけではなく、日常ユーザー層、フォロワー層といった複数のペルソナが設定されているのも特徴です。
このように、プロユースを前提とした製品開発が一般層の「憧れ」に繋がり、広がっていくのは、カルトブランディングの王道です。例えば、ロレックスは水深200メートルに耐えられるダイバー向けの製品を開発し、プロユースでの信頼性とともに憧れの対象としての地位を確立しました。
カルトブランディングを成功させるには、まず「革新的なイデオロギー」が必要です。ありきたりなものでなく、尖ったイデオロギーを打ち出す勇気が求められます。(カルトブランディングにおいて「イデオロギー」と「パーパス」はほぼ同義とされる)
例えば、アウトドアブランドであるパタゴニアは「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」という明確なパーパスを掲げています。アパレル業界は、製造過程自体が環境負荷を伴うジレンマを抱えていましたが、同社は再生素材の使用や、環境負荷の少ない製品開発により、熱狂的な支持を得ました。
また、アメリカのプロホッケーチーム「ベガス・ゴールデンナイツ」は、ラスベガスを拠点とします。ラスベガスを「エンターテインメントの世界の首都」と定め、エンターテインメントの提供に振り切ったサービス設計をしています。試合ではシルク・ドゥ・ソレイユが監修するハーフタイムショーなどで、他チームと差別化し、「信者」の獲得に成功しています。
カルトブランディングにおいて重要なのは「イデオロギー」だけではありません。「象徴」や「共創」「異端児」など通常のブランディングとは異なる特徴的なキーワードがあります。その一つが「敵」です。カルトブランドには「敵」が必要とされますが、日本では同業他社ではなく、「我々はこの社会課題と戦っている」や「お客様の課題を解決する」といった形で、社会課題や顧客の悩みを「敵」に設定することが効果的です。
今こそ取り入れたい!カルトブランディングの6ステップ

① 存在理由の明確化(パーパス)
ブランドの存在意義を革新的なイデオロギーとして設定・明確化します。パーパスは、ブランドの行動やメッセージの根幹となる重要な要素です。
② ペルソナ設定
メッセージを届けたい対象や、商品開発におけるペルソナを具体的に設定します。年齢、性別、ライフスタイル、価値観などを詳細に描くことが求められます。
③ ストーリー構築
宗教に神話があるように、ブランドにも共感を生むストーリーが必要です。ブランドの背景や開発秘話、顧客とのエピソードなど、エンゲージメントを高めるストーリーを組み立てます。ストーリーは複数あっても良いです。
④ タッチポイントの探索
顧客との接点(タッチポイント)を洗い出すか、新たに設定し、ターゲットに合った適切な配信経路(チャネル)を選定します。若い世代であればSNS、高齢者であれば新聞・テレビなど、ターゲットに応じた媒体が候補となります。
⑤ コミュニティー形成とサポート
ファンが増えたタイミングで、ブランド主導のコミュニティーを作るか、顧客が立ち上げたコミュニティーをサポートします。カルトブランドにはコミュニティーが不可欠で、オフ会やSNS上での交流、会員制度もその例です。
⑥ 解析とメンテナンス
ブランド認知度や顧客満足度を定期的に測定し、必要に応じて戦略の見直しや微調整を行います。
カルトブランディングを成功させるためのポイント
カルトブランディングの成功には、以下の2要素が不可欠です。
① 創業者の愛
創業者のブランドや商品への深い愛情が最も重要です。金銭目的の姿勢は顧客に伝わってしまいます。ブランドの最初の「信者」は従業員であるべきです。創業者自身がブランドを心から愛していなければ、従業員もその想いを共有できません。
まずは社内にブランドを愛する人を増やすことが、「信者づくり」の第一歩です。
② 透明性(トランスパレンシー)の徹底
現代は「嘘のつけない時代」です。したがって、隠し事は悪手でしかありません。透明性の高い情報公開こそが成功の鍵です。企業として、あらゆる情報を責任を持って公開し、時にはネガティブなことも開示する姿勢が求められます。
海外では、排出した温室効果ガスの量「カーボンフットプリント」や、材料費や労働コスト、配送費など、商品の原材料費の内訳を全て明示するブランドもあります。このような透明性の高い情報開示は、ブランドの正直な姿勢を消費者に印象付けます。結果、信頼と「信者」の獲得に繋がります。
そのためには、自社のビジネスへの自信と、責任ある経営を行っているという確固たる信念が欠かせません。そして、その信念を支えるのは、やはりブランドへの「愛」なのです。ブランドへの「愛」があるからこそ、正直でいられるわけで、これがカルトブランディングの根幹となります。
幸福感を高めるカルトブランディング
ブランドへの「愛」があれば、すべての企業・ブランドはカルトブランドを目指せます。
人間の幸福には、物欲を満たしたときに感じる一過性のものと、崇高な理念を追求する過程で得られる持続的なものとがあります。カルトブランディングはパーパス(存在意義)を起点とするため、このパーパスを意識しながらブランド作りに取り組むことで、創業者や経営者自身が長期的な幸福感を得ることができます。
一方、顧客側にとっても、愛するブランドに「依存」できる状態は大きな喜びをもたらします。カルトブランディングは、創業者と顧客双方に幸福をもたらし、さらには社会全体の幸福量を増やす手法なのです。
「カルト」という言葉は強いインパクトがあるかもしれませんが、不安や不信の感情が蔓延する現代において、この考え方はむしろ重要であり、必要なものです。そしてこの発想は、企業に限らず、個人にとっても有効です。自分自身の存在理由や存在意義を捉え直すことは、より豊かな人生を送るきっかけとなります。
カルトブランディングが提唱する「パーパスの重要性」は、あらゆる人にとって意義深い視点と言えるでしょう。
多様な個性が息づく豊かな社会へ
個々の生命力溢れる存在が共存する「ジャングルのような社会」を目指すことは、多様性、そしてより豊かな社会の実現に繋がっていきます。現在の日本はアメリカに比べて、カルトブランドが少ないですが、今後カルトブランドが増えることで、より面白く、活気ある社会になっていくことでしょう。
田中さんの講演では、具体的な事例を挙げながらカルトブランディングについて解説いただき、実践のための手順などを詳しく教えていただきます。
ブランド戦略に行き詰まりを感じている方や、これから新たなブランドを立ち上げようとしている方にとって、カルトブランディングは進むべき方向を示す「羅針盤」となるはずです。
ぜひ講演の開催をご検討いただければ幸いです。
田中森士 たなかしんじ
株式会社クマベイス 代表取締役CEO
アジアスモールビジネス連盟 日本(ASBF Japan)代表
コンテンツマーケティングコンサルタント
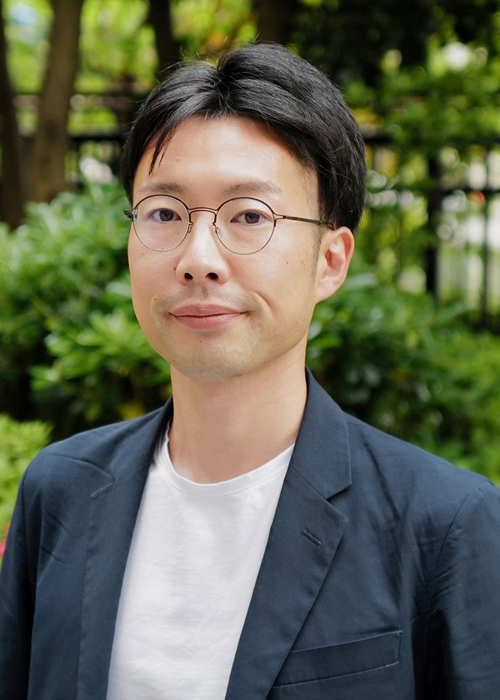
熊本大学大学院修士課程で消費者行動を研究後、県立高校講師(地理・歴史)、産経新聞記者を経て起業。「カルトブランディング」「間口を狭める戦略」「マーケティングZEN」といったマーケティング・経営理論を研究、国内外へ発信。著書『なぜ看板のない店に人が集まるのか』他多数。豊富な講演・執筆実績。
|
講師ジャンル
|
実務知識 | 営業・販売・マーケティング | 経営戦略・事業計画 |
|---|
プランタイトル
カルトブランディング
~熱狂的なファンを生む新しいブランド戦~
あわせて読みたい
コロナ禍以降、マーケティング戦略も大きく変革しています。 今だ…
自社の製品やサービスをお客様に購入・利用していただくために必要…
コロナ禍以降、消費動向も先読みが難しい日々となっています。 新…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






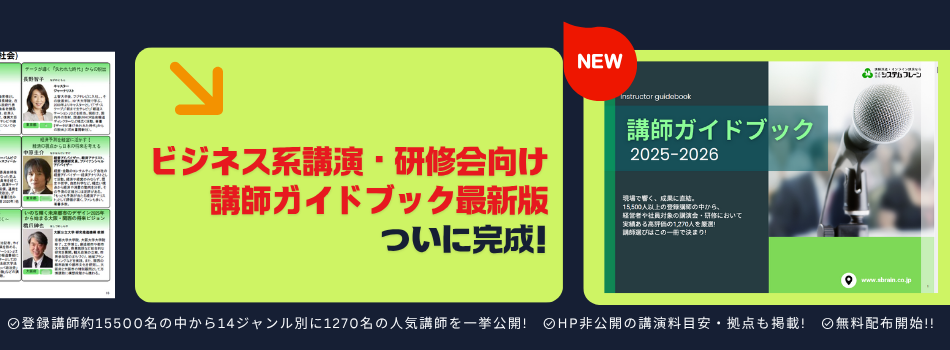


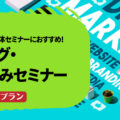








業務外の講師への取次は対応しておりません。