
2023年4月、「こども基本法」が施行されました。
この法律は、子どもの健やかな成長と社会への参画を社会全体で推進することを目的に制定された、日本で初めての包括的基本法です。
しかし現場では、「目的や理念はわかるが、具体的にどう動けばよいかわからない」と立ち止まる行政・教育・福祉の担当者も少なくありません。
忙しい日常業務の中でも、「こどもまんなか社会」を現実にするためには、まず正しい理解と、自庁・自地域に落とし込む運用設計が大切です。
本記事では、長年にわたり地方自治や多文化共生を研究されてきた林 加代子さんに、こども基本法における子どもの参加の考え方や国の提案と実例、そして実装を担う大人の役割を解説していただきます。
※本記事の内容は2025年10月時点のものです。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
林加代子氏
(株)ソーシャル・アクティ 代表取締役
愛知学泉大学、人間環境大学非常勤講師
地方自治研究学会理事
2023年施行の「こども基本法」。低い認知度が生む弊害
 2023年に施行されたこども基本法ですが、そもそも「知らない」という人が多く、浸透していない実情があります。
2023年に施行されたこども基本法ですが、そもそも「知らない」という人が多く、浸透していない実情があります。
たとえば、日本財団の「こども1万人意識調査」(2023年)では、こども基本法やこどもの権利条約について、約6割の人が「聞いたことがない」と回答しています。
また、セーブ・ザ・チルドレンの全国3万人調査では、約半数の大人が「子どもの貧困の実態について聞いたことがない」と回答。
さらに同調査では、こども基本法でも重視されている自分の意見を聴かれる権利「子どもの意見表明権」を大切だと考える子どもが4割以上だったのに対し、大人は3割未満でした。加えて、この権利が守られていないと思う子どもが27.6%であるのに対し、大人は18.1%と、子と大人で大きな差があることが示されました。
こども基本法が広まらない背景にある日本の因習
この認知度の低さには、日本に根付いた古い考え方が背景にあると考えられます。
日本人は「権利」という言葉や価値観に疎く、昔の家父長制度の考え方も影響してか、「子どもの権利」に対して「子どもを好き放題にさせてしまう」「子どもに権利を持たせたら大人の立場が危うくなる」といったイメージを抱きがちです。それが、こども基本法の理解を遅らせているのかもしれません。
また、「知ってはいるけれども、日々の業務が忙しくて実務に落とし込めない」ことも要因の1つです。
自治体の担当者は施策の反映に努めますが、子どもに関連する施設の職員は日々の業務で手一杯で、施策にまで手が回らない状況にあります。これは施設に限らず、たとえば育児の負担が大きいひとり親家庭や介護世帯にもいえることです。
「社会全体で子どもを育てる」という考え方の欧米とは違い、日本はまず家庭が第一にあります。そのため、外部に支援を求めず「家庭で対処しなければならない」という意識が根強く残っています。
この育児観の在り方は、貧困・虐待・ヤングケアラーなど深刻な課題の「見えにくさ」を助長し、適切な支援の早期介入を妨げる要因にもなっています。
法律はできた、でも現場では動かない。このギャップを埋めるには、こども基本法の目的を正しく理解し、子どもの参加を前提にした社会環境を整備することが求められます。
そもそもこども基本法とは?子どもの権利条約との違い
1989年に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、世界共通の基準として「生きる・育つ・守られる・参加する」という4つの柱を定めた国際条約です。
一方、2022年に成立し、2023年に施行されたこども基本法は、日本国憲法と子どもの権利条約に基づき、日本の子ども施策を総合的に推進する目的で制定されました。
以下6つの基本理念で構成されています。
- 子どもの基本的人権を保障すること
- 子どもに対し、適切な養育・生活の保障・愛情の下の保護・平等な教育機会・平等な福祉の保障を行うこと
- 子どもがさまざまな場面で意見を表明したり多様な社会的活動に参画したりすること
- 子どもの意見を尊重し、最善の利益を優先すること
- 子どもの心身の健やかな成長を大人が支援すること
- 大人が子育ての喜びを実感できるような社会環境の整備を行うこと
参考:法務省「こどもの権利条約」
こども家庭庁「こども基本法」
こども基本法が制定された背景
これまで日本には、教育基本法や児童福祉法など、子どもに関わる法律はありましたが、子どもの権利を包括的に位置づける法律はありませんでした。
子どもの権利条約が批准された頃の日本は一億総中流の時代で、今ほど格差は生じておらず、子どもの権利という概念がなかったのです。
しかし、そこから30年以上が経ち、子どもの声が社会に十分届かない現状や、貧困・虐待・いじめなどの課題を受けて、ようやく「子どもの権利を守るための基本法」が整備されました。加えて、少子化対策の一つとしても制定された背景があります。
また、こども基本法とセットで「こども家庭庁」が新設されました。これは、従来バラバラだった子ども関連の行政をまとめ、教育・福祉・医療などを横断的に対応できるようにするための仕組みです。
こども基本法における子どもの参加の考え方
 こども基本法を実現するには、子どもの意思決定を日常生活の細部にまで落とし込むということが重要です。
こども基本法を実現するには、子どもの意思決定を日常生活の細部にまで落とし込むということが重要です。
しかし実際は、大人の都合や事情や思い込みですべて決めてしまう場面が多くあります。
一般的に家庭では、財布の紐を握る親が日々の献立を考えたり、子どもが着る服を選んだりしています。
子どもに必要な栄養は何か考えて作っても、給食のメニューと重なったり、子どもに似合うと思って買っても、子どもは着なかったりすることもあります。
また、大人が子どもに良かれと思ってやったことが裏目に出ることもあります。
たとえば、安全に歩ける通学路を作るために信号の位置を変えたところ、かえって歩きにくくなってしまったと地域の大人が勝手に思い込み、その後要望を出したものの、当事者である子どもに聞いてみると、何とも思っていなかったなどの事例もあります。
このように、大人の思い込みによる子どもとの考えのすれ違いは、さまざまな場面で生じています。
保護を受ける立場の子どもは社会経験が乏しく、職業生活についても理解していません。大人よりも経験値が圧倒的に低いため、日常生活のさまざまな場面で「何を選べばよいかわからない」「どんな選択肢があるのか知らない」という状況に陥ります。だからこそ、大人が代わりに決めてしまうのです。
こども基本法に対する国の提案と実例
こども家庭庁は、こども意見ファシリテーター養成講座や開催ガイド(教材・モデルプログラム)を整備し、実務力の底上げを支援しています。
こども意見ファシリテーターとは、必要な情報をわかりやすく伝え、子どもの意見を引き出す、いわば子どもと大人の間に立つ橋渡し役のような存在です。
受講対象者は関連施設の職員などですが、自治体側は人員が不足しており、活動は低調気味です。そのため、外部の人材や地域NPOとの協働でファシリテーション体制を確保しています。
参考:こども家庭庁「こども意見ファシリテーター養成講座」
まちづくりに子どもの意見を取り入れたケース
自治体の実例としては、条例策定から子どもの意見を反映してきた愛知県幸田町(2011年施行)があります。
幸田町では、「すべての子どもが幸せになり、責任のある大人になってほしい」という願いを込め、「幸田町子どもの権利に関する条例」を制定しました。公式サイトでは、条例全文と逐条解説が公開されています。
特色的なのは、策定の過程で子どもが参画している点です。幸田町をはじめ、最近では条例の制定・改正やワークショップを通じて、子どもの意見を聴取する動きが広がっています。
参考:幸田町「幸田町子どもの権利に関する条例」
こども基本法を実装するために必要な大人の役割
こども基本法を実装するうえで大切なのは、家庭や学校でも「子どもは親の所有物ではなく、一人の人間」として尊重する姿勢を持つことです。
子どもとの合意形成では、必要な情報を伝えて選択肢を提供し、納得できる話し合いを心がけましょう。
そのうえで、今後は以下の取り組みが求められます。
子どもの声を制度に組み込む
会議や計画づくりに、子どもの意見を反映するルールをつくることが大切です。たとえば、先にあげた幸田町のように、策定に子どもの意見を取り入れたり、資料をやさしい言葉や図解で説明したりといった取り組みもあります。
生活の中での参加を広げる
特別な場だけでなく、日常生活で意思決定を経験できる場を増やすことも重要です。たとえば、キャッシュレス決済が普及する中で実際に子どもに本物のお金を渡し、限られた予算内で欲しいものをどのように買うか学ばせたり、地域行事の準備や運営を任せたりする事例もあります。
デジタルツールを安全に活用する
学校のタブレットやオンラインアンケートで子どもの声を集める動きも高まりつつあります。ただし、SNS利用においては、ネットリテラシー教育とセットで運用することが欠かせません。
こども基本法を正しく理解し子どもの笑顔であふれる社会に
 こども基本法の認知度は低く、現場では古い教育文化や業務負担への抵抗から戸惑いの声も聞かれます。
こども基本法の認知度は低く、現場では古い教育文化や業務負担への抵抗から戸惑いの声も聞かれます。
しかし、重要なのは「子どもの声を尊重し、生活や地域、政策に反映すること」です。
そのためには「子どもを大人の所有物にしない」姿勢が不可欠です。大人自身が意識を変え、子どもの声を聞くための仕組みを整えていく必要があります。
本記事でご紹介した内容は、講演でさらに詳しく解説しています。
林氏は講演で、「こどもまんなか社会」の実現に向け、大人の役割の重要性を説いています。
講演では、子どもが安心して意見を言える環境や、地域・行政・家庭が連携して支える仕組みを学ぶ場となり、実践例や具体的ヒントも得られます。理念は理解しているものの、実践に迷う行政・教育・福祉関係者や子育て世代にとって、大人の関わり方を見直すきっかけとなるでしょう。
子どもの権利を尊重し、地域で実践につなげていくためにも、ぜひ講演をご検討ください。
林 加代子はやしかよこ
(株)ソーシャル・アクティ 代表取締役 愛知学泉大学、人間環境大学非常勤講師 地方自治研究学会理事

トヨタや日興證券、朝日生命での勤務の傍ら、地域活動に参加、まちづくりに関心を持つ。大学院に進学し、まちづくりやボランティアのあり方等を研究。URでまちづくりの現場を学んだ後、まちづくり支援企業設立。ファシリテーションを活用した政策・条例づくり、企業向け研修等を展開、地域や組織活性化に貢献。
|
講師ジャンル
|
ソフトスキル | コミュニケーション |
|---|---|---|
| 社会啓発 | 人権・平和 |
プランタイトル
こども基本法のこどもの参加を実現しよう!
あわせて読みたい
2021年の総務省「社会生活基本調査」によると、男性の家事・育…
ゲーム、スマートフォン、インターネットなど、いつでも簡単にアク…
偏食やファーストフード、朝食をとらないなど、子どもたちの食生活…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






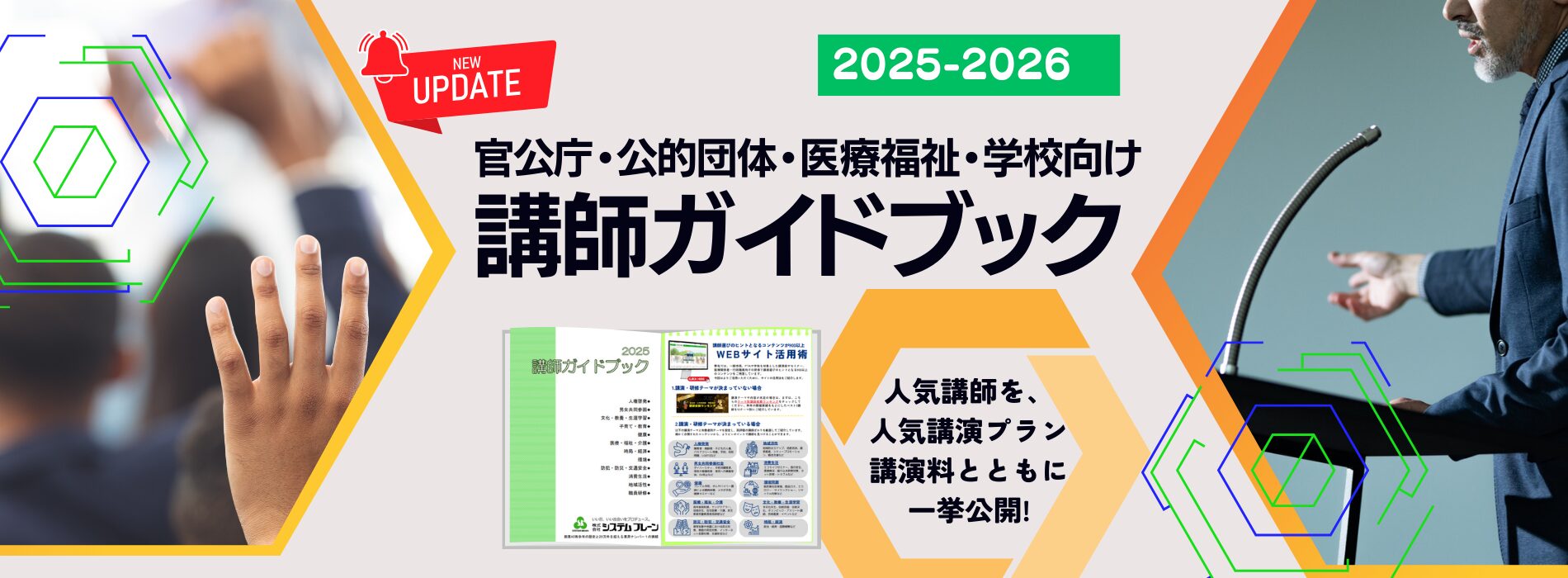


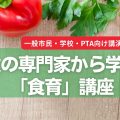








業務外の講師への取次は対応しておりません。