
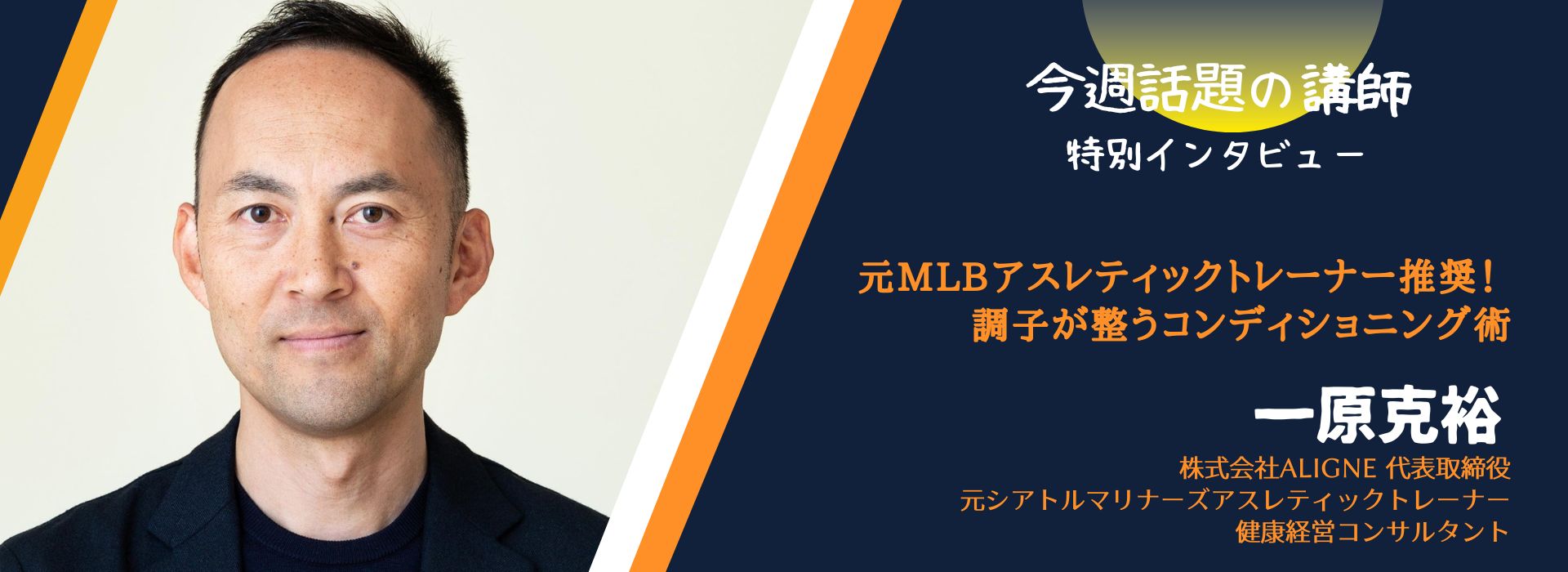 「腰が痛い」「休んでもスッキリしない」など、年齢のせいと諦めてしまう方も多い、ちょっとした身体の不調。しかし、そんな不調を放置すれば、仕事が思うように進まなかったり、事故を起こしてしまったりする可能性もあります。
「腰が痛い」「休んでもスッキリしない」など、年齢のせいと諦めてしまう方も多い、ちょっとした身体の不調。しかし、そんな不調を放置すれば、仕事が思うように進まなかったり、事故を起こしてしまったりする可能性もあります。
今回は、MLBやWBCなどプロスポーツの世界でアスレティックトレーナーとして活躍してきた一原 克裕(いちはら かつひろ)さんに、不調を改善して調子のいい自分をつくる「コンディショニング」の方法とその効果についてお話を伺いました。
※本記事の内容は2025年8月時点のものです。
日本スポーツ界に安全管理体制を。本場の技術を学びにアメリカへ

▲WBC中国代表にトレーナーとして帯同していた頃の一原さん
――一原さんは、早稲田大学在学中からアメフト部で学生トレーナーとして活動されていらっしゃいましたね。トレーナーの道を選んだのはなぜですか?
一原 高校では選手として野球部に所属していたのですが、怪我が多く、専門家のケアを受けていたという経験が大きかったですね。怪我のこともあり、スポーツにずっと関わっていきたい気持ちはあるものの、選手としてプロを目指すのは難しいと思っていました。
そこで、「選手をサポートする側であれば、プロとしてスポーツに関わっていけるのではないか」と考え、アスレティックトレーニングを学べる早稲田大学に進学したのです。一切経験のなかったアメフト部のトレーナーになったのも、アスレティックトレーニングを実践的に学ぶためでした。
――留学もされていらっしゃいましたが、何を学ぶために留学されたのですか?
一原 大学のアメフト部では、トレーナーの重要性が広く認知されていますが、高校のラグビー部やアメフト部などコンタクトスポーツでも、現場にトレーナーがいないチームがまだまだ多くあります。。だからこそ、「少年団のような草の根スポーツやユース世代の安全管理を変えていきたい」「スポーツ現場の安全管理を徹底しているアメリカに学びに行きたい」と思うようになりました。
スポーツ現場の安全管理の啓発活動を行っている「NPO法人スポーツセーフティージャパン(以下、SSJ)」に参加したのも大きな転機でした。「大学卒業後、すぐにNPOで活動するよりも、海外で経験を積んだ方がいい」とNPOの代表に勧められたことが、アメリカ行きを決断する後押しになりました。
――海外ではシアトル・マリナーズやWBC中国代表のトレーナーとして活躍されていましたが、そうしたプロの現場で特に印象に残った学びは何でしたか?
一原 アメリカは約10万人が入るような大きなスタジアムもあるほど、スポーツが産業の一部になっている国です。上司として私を指導してくださった方々も、私が生まれる前から業界にいるようなベテランばかりでした。
スポーツ医学も日々進化するため、過去の知識が通用しなくなることも多々あります。しかし、若い世代には見えていないものを見ることができるのは、プロの現場で長年活躍してきたベテラン達なのです。そういった方々から学べたことは、非常に大きかったと思っています。
事故の危険性も。労働環境におけるコンディショニングの重要性

▲イメージ画像
――一原さんはコンディショニングの重要性を伝えていらっしゃいますが、そもそもコンディショニングとはどのようなことを指すのでしょうか?
一原 予防という観点からシンプルに言えば、コンディションとは、「今日の調子」のことです。「今日の調子は何点ですか?」と聞かれた時に満点でないのであれば、そこには何か要因があるはずです。しかしその不調の要因は、単純に身体的要因や精神的要因だけでなく、人間関係や気圧の影響など多岐に亘ります。
コンディショニングとは、それらの多様な要因に対し、パフォーマンスを上げていくために取るアクションのことを指します。例えば疲労回復のためにストレッチを多めにしたり、バランスのいい食事を摂ったりするのも、コンディショニングの一環です。
アスリートが自分のスキルを最大限発揮するためには、その根底にある回復能力や身体の可動域、メンタルなどの調子が良いことが重要です。その根底部分の調子を整えるのが、コンディショニングなのです。いくら練習しても、スキルの土台となるコンディションが整っていなければ、十分なパフォーマンスを発揮できません。
――コンディショニングを行わないことで、心身に影響や危険が及ぶことはありますか?
一原 コンディショニングが重要なのは、決してスポーツの現場に限った話ではありません。私は現場ワーカーと呼ばれる身体を使って仕事をされている方々のサポートもしていますが、そういった労働環境においてコンディションが整っていないと、様々な影響を受けることがあります。
例えば重い荷物を持ち上げる際、持ち上げられるだけの筋力を持っていなければ怪我に繋がります。バランス能力が落ちている方であれば、脚立に上るだけでも落下の可能性があります。身体機能の衰え1つを取っても、コンディショニングの不足が労災に直結する恐れがあるのです。
また、暑い時期には熱中症のリスクもあります。現場での水分補給不足も前提としてありますが、下痢や嘔吐による脱水や、朝食を抜く・睡眠不足といったコンディションが整っていない状態も、熱中症の重要なリスクファクターとなります。
「仕事に来る前の段階で熱中症にかかるかどうかが決まっている」と言っても過言ではないほど、熱中症とコンディショニングは密接な関係があるのです。
現場での事故防止のために、整理整頓など労働環境の改善を意識している企業様は多いと思いますが、個々によるコンディショニングも事故防止のための重要な要素なのです。
――コンディショニングは幅広い観点からの配慮が必要なのですね。
一原 コンディショニングは、運動・栄養・睡眠・メンタルなど、あらゆる領域への配慮が必要です。労働環境そのものを個人の力だけで変えることは難しいですが、コンディショニングは個人の意識で変えられます。
近年は高齢労働者も多くなっていますので、まずは自身の生活習慣や身体、心に対し、どれくらいコンディションを整えるアクションをしているのかを投げかけるところから私はアプローチしています。
第一歩は自己分析。1日5分から始める調子のいい自分づくり

▲イメージ画像
――コンディショニングにはどのような方法があるのでしょうか?
一原 まずは自分の調子を記録として残し、振り返る習慣をつけることからスタートします。例えば、睡眠時間が削られた場合に一番調子が崩れたと感じるなど、自分のコンディションに対し何が最も影響するのかは、人によって様々です。そのため、まずは自分の調子をスコア化し、何が影響を与えているのかを理解する自己分析が必要なのです。
次に必要なのが、運動・栄養・睡眠・メンタルといったコンディショニングに関係する原理原則を理解することです。原理原則を知らないが故に調子が悪いだけという方は、実は非常に多いのです。原理原則に則っていれば、5分程度のエクササイズでコンディションが改善する方もいらっしゃいます。
そして、最も難しい段階が行動変容です。今までやってこなかったことをいきなり生活に入れ込み、習慣的に継続していくというのは、非常にハードルが高いことです。そのため私は、1日5分程度など、努力感なくできるところから始めて、何かしら自分の体が変わることを感じていただく方法をお伝えしています。
講演会の中でも、15分程のエクササイズなど、身体の変化を実感していただく機会をたくさん設けています。それまで体を動かしていない方ほど、大きな変化を感じて驚いていらっしゃいますよ。
――たった5分でも効果を感じられるのですね。
一原 1〜2週間ほど続けた上での変化にはなりますが、2日に1回、5~10分程度体操するだけでも変化は実感できます。「なんだか体が疲れにくくなってきた」「そういえばあの症状が最近ないな」といったゆるやかな変化ですが、それぐらいの変化率の方が継続しやすいと感じています。
「もう歳だから」「この仕事に腰痛は付きものだから」と改善することを諦めてしまう方も多いですが、ちょっとした取り組みからでも大きな変化を得られることはあります。まずは自分が「変わらない」と思っていることを、「変わるかもしれない」にシフトさせることがとても重要だと思っています。
ただ、コンディショニング自体が目的になってしまっては意味がありません。コンディショニングの大きな目的は、自分が頑張りたいときに頑張れる状態を担保することです。これをレディネス(readiness)とも言います。
たとえば、睡眠を削ることは本来健康管理としては悪手ですが、その徹夜がその人にとって「勝負をするために必要なアクション」であるならば、それは意味のある選択だと思っています。大切なのは、コンディショニングという行動そのものではなく、コンディションが整うことで何に繋がるのかを意識することなのです。そのため、勝負のために心身に負荷がかかった後にしっかりとリカバリーをする時間を意識的に持てることこそが大切であり、自分で自分の調子を整えられる能力こそ重要だと考えます。
日本の労働環境をコンディショニングの視点で守る

▲一原さんの講演会の様子。講演会では短時間のエクササイズなどの実践的な時間も設けられている
――講演会ではどのようなお話をされていらっしゃいますか?
一原 講演では、主に企業の方を対象に、健康経営や安全衛生の観点からお話しすることが多いです。海外の事例なども交えながら、スポーツの現場で培ってきた安全管理や予防、コンディショニング全般のお話を、ご依頼いただいた企業の労働環境に合わせてお話させていただいています。
講演会では簡単なフィジカルチェックなどの実技講習的な要素も取り入れています。フィジカルチェックをしてみると、できると思ってやってみたらできなかったという方が多くいらっしゃいます。そこに気づいていただくことも、講演会の目的の1つです。
現在、多くの企業では、設備面での安全対策──いわゆる「場のリスク」への対応が進められ、労災も減少傾向にあります。しかし一方で、労働者の高齢化が進む中、なにもない場所でつまずくような身体機能の低下による労災事案が増えているのも現状です。
そうした「人のリスク」に企業として取り組もうとしても、日本にはまだ専門家も少なく、分からないまま手付かずになっているケースが多く見受けられます。だからこそ、そのような状況に対し、海外などで私が得てきた知見や実践的なノウハウを日本に広めていきたいという思いで講演会をしています。
――本日は貴重なお話をありがとうございました!
一原克裕 いちはらかつひろ
株式会社ALIGNE 代表取締役 元シアトルマリナーズアスレティックトレーナー 健康経営コンサルタント

米国BOC公認ATC取得後、MLBシアトルマリナーズ、WBC中国代表トレーナー帯同等を経験。帰国後、健康経営支援事業参画を経て、独立。長年のスポーツチームやトップアスリートサポート経験を活かし、企業向け健康経営コンサル、労災・コンディショニング研修、安全管理啓発セミナーなど定評がある。
プランタイトル
元シアトルマリナーズトレーナーが伝授。
身体機能向上で高齢労働者の転倒災害ゼロへ
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されましたあわせて読みたい
少子高齢化で、ますます厳しくなる中小企業の人材確保ー。 専門ス…
ADHDの診断を受け、すべてを失いかけても何度でも立ち上がり、…
FIRE達成や世界一周といった華やかな実績の裏に、自己否定や貧…
他の記事をみる







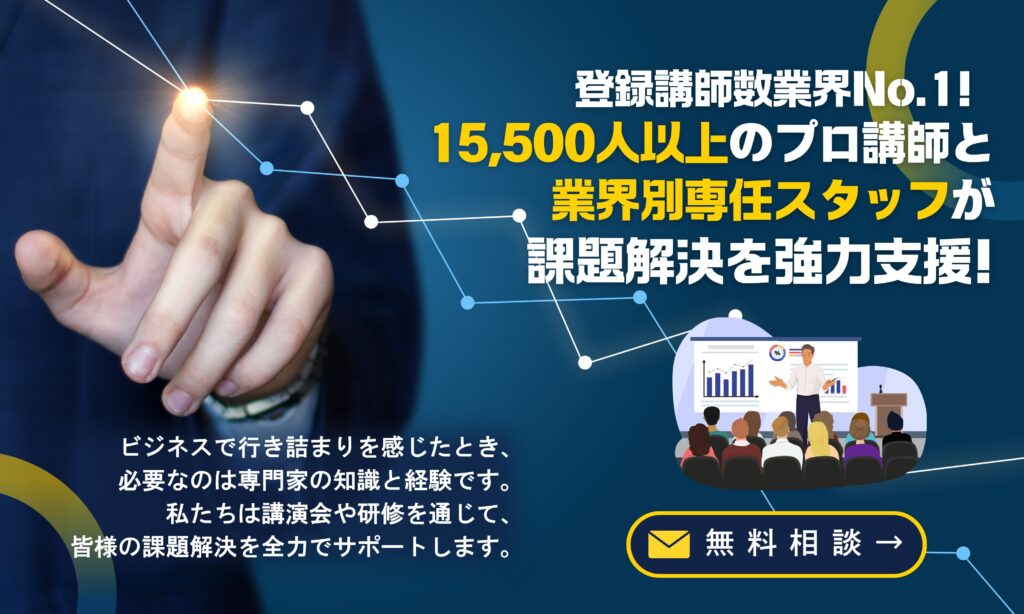











業務外の講師への取次は対応しておりません。