
「個々は優秀なのに、なぜかチームとしての成果が出ない──」
多くの企業や職場が抱えるこの課題。その要因は、個人の能力不足ではなく“チームの構造”にあるかもしれません。
本記事では、東京ディズニーリゾート®やユニバーサルスタジオジャパン®で人材育成を担い、現在は企業研修講師、企業人材開発コンサルタントとして活躍する今井千尋氏の講演内容をもとに、「シナジー(相乗効果)を発揮するチームのつくり方」を解説します。
現場で“使える”チームビルディングとは何か。人が育ち、組織が進化し、成果が出るチームとはどのような構造なのか。理論と実践の両輪で紐解いていきます。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
今井千尋氏
株式会社ワンダーイマジニア 代表取締役
2大テーマパーク 人材育成・人材開発トレーナー
なぜ今、チームビルディングなのか?──「個の力」だけでは勝てない時代に
現代のビジネス環境は、もはや「過去の成功体験」では立ち行かないほどに複雑化・多様化しています。テクノロジーの進展、グローバル競争の激化、世代・国籍・価値観の多様性……こうした環境の変化は、従来型のマネジメントや組織運営の限界を明らかにしました。
たとえば、次のような課題を抱えている企業は少なくありません。
- 個々は優秀な人材なのに、なぜかプロジェクトがうまく進まない
- 会議で意見が出ず、意思決定に時間がかかる
- 現場とマネジメント層の間に“見えない壁”がある
- 若手社員が受け身で、育成に時間がかかる
- 人が育たず、常に人手不足が続いている
こうした課題の多くは、「チームとしての機能不全」によるものが要因として含まれています。
今井氏は、「成果を出せるチーム」と「そうでないチーム」の違いを、“シナジーの有無”にあると語ります。シナジー(相乗効果)とは、チーム内のメンバー同士が互いの強みと弱みを理解し、補完し合いながら、包括的に個人では達成できない大きな成果を出す状態を指します。
つまり、チームビルディングとは単なるレクリエーションではなく、メンバーの力を「掛け算」に変えるための“仕組み”であり、“文化づくり”なのです。
この視点に立つと、従来のように「優秀な人材を採用して終わり」ではなく、「優秀な人材が育ち、定着し、活躍するチームを設計する」ことこそ、これからの企業に求められる本質的な人材戦略であることが見えてきます。
組織を動かす“場の力”──再現力と浸透力のマネジメント
 個々人の意識向上や最大限の行動発揮をするには、まず“場の力”に注目すべきだ──これが今井氏の持論です。今井氏は「人はルールに従うのではなく、“場”に影響されて動く」と言います。
個々人の意識向上や最大限の行動発揮をするには、まず“場の力”に注目すべきだ──これが今井氏の持論です。今井氏は「人はルールに従うのではなく、“場”に影響されて動く」と言います。
たとえば、同じようなスキルセットを持つチームでも、A社では自発的に行動が生まれ、B社では指示待ちが常態化していることがあります。この違いは、個人の能力ではなく、日常の「場の設計」にあります。
今井氏は、“成果が出るチーム”には共通して次の4つの要素があると指摘します。
- 共通言語:メンバー全員が、目的を達成する為に、同じ言葉を意識し使っている
- 共通理解:その言葉の背景・意図という意味づけも共有されている
- 共通認識:背景や・意図という意味づけを意識した目的達成に期待される行動の水準が具体的に可視化されている
- 共通体験:上記の3つ(言語・理解・認識)を身体・思考に染み込ませ、現場での行動の判断軸として、すべてのチーム人材が言葉と行動に落とし込み、すべての言動に一貫性を持ち、実感を持って機能させている
たとえば、「ホスピタリティ」という言葉。現場では「笑顔で挨拶すること」と捉えられ、マネジメント層では「顧客体験価値において期待を上回る言動」と理解されていたとすれば、それは“共通言語からの共通理解”が徹底されているとは言えません。
このようなズレを放置すると、同じ目的・目標に向かっていても、共通理解(意味づけ)が違うことで行動がバラバラになり、組織は足並みを揃えることができません。
また、場の設計には“再現力”と“浸透力”が欠かせません。
再現力とは、「誰がやっても、どのような機会でも同じような成果が出る」状態。
浸透力とは、「一過性で終わらず、日常の行動として定着している」状態です。
この2つを実現するには、「言葉の定義」と「行動の具体化」が必要です。今井氏の研修では、人により解釈がわかれる曖昧な言葉を排し、行動水準という目的達成に必要なそれぞれの段階ごとに推奨される具体行動を1~10段階で評価・可視化するフレームワークを使って、組織全体で共通の価値観と行動様式を醸成していきます。
このプロセスを経ることで、社員一人ひとりの行動が組織の文化(自組織らしさ)となり、社員が自信を持って、自発的に判断、行動できるようになります。結果として、チームが“自ら成果を出す組織”へと進化していくことができるようになります。
「自律型人材」はこうして育つ──3つの軸と表現力の鍛え方
 成果を出すチームには、常に“自ら考え、動ける人材”がいます。これを今井氏は「自律型人材」と呼び、彼のチームビルディングメソッドの中心に据えています。
成果を出すチームには、常に“自ら考え、動ける人材”がいます。これを今井氏は「自律型人材」と呼び、彼のチームビルディングメソッドの中心に据えています。
自律型人材とは、言われたからやるのではなく、自分で課題を見つけ、主体的に解決に動ける人。変化に強く、成果志向でありながら、チームとの協働にも長けている──そんな人材をどう育てるかが、企業の未来を左右するといっても過言ではありません。
今井氏は、自律型人材に必要な土台となる要素を、次の「3つの軸」で説明します。
- 感謝軸:当たり前のことに感謝し、それを“表現”できる
- 貢献軸:自分の役割を超えて、他者のために動ける
- 最適軸:常に相手の立場に立ち、判断・行動を選択できる
これらの軸は、いずれも「人として相手に信頼され、応援される土台」に関わる要素です。業務スキルや専門知識以前に、チームの一員として信頼され、協働できる人間性が問われるのです。
さらに、自律型人材には「表現する力」も求められます。
感謝や貢献の気持ちを“言葉にする力”、あいまいな概念を“具体化して伝える力”、そして“「どんな目標に向かって、なぜ行動するのか」を分析し、自分の言葉で語り、それを動かす力”です。
この表現する力を高めるために、今井氏の研修では、日常的に使える具体的なフレーズのトレーニングや、曖昧な言葉を定義し直すワークショップが組み込まれています。
また、「1日50回“ありがとう”の機会を見つけ出し、それを伝える」といった習慣づけの実践も導入され、意識と行動をつなぐ“言語化→行動化→習慣化”のステップが丁寧に設計されています。
理論と“場”の両輪で、チームは進化する
ここまで紹介してきたように、チームビルディングとは単なる「仲良くなるための施策」ではありません。個人の力を組織の成果に変える“構造設計”であり、成果を出し続ける組織づくりの根幹にかかわる取り組みです。
今井氏の講演では、組織の中にある「個人と組織の接点」に光を当て、自律的に動ける人材と、再現力ある“場”の両輪を設計するメソッドを体系的に学ぶことができます。
講演では、「Magic4」という行動定着の仕組みや、メンバーの多様性を活かすための4つのリーダータイプの活用法など、再現性と習慣化を実現する実践的ツールが具体的に紹介され、チームビルディングの構築に非常に有効です。
「優秀な人材を集めたのに、なぜ成果が出ないのか」と悩む経営者や人事・研修企画、人材開発担当者の皆様にとって、今井氏の講演は、チームの“見えない仕組み”を再構築するきっかけになるはずです。
自社で再現力と浸透力のあるチームビルディングを実現したいという方は、ぜひ講演をご検討ください。
今井千尋 いまいちひろ
株式会社ワンダーイマジニア 代表取締役
2大テーマパーク 人材育成・人材開発トレーナー

小学校の夢だった「ジャングルクルーズの船長になりたい!」を見事実現!「夢は願うものではなく叶えるものである!」を自ら体得。ディズニー、ユニバーサルスタジオジャパンでの人財育成・開発担当の経験を基に、全国各地でエンターテイメント性溢れる講義(楽習)を行っている。
|
講師ジャンル
|
ソフトスキル | モチベーション | 意識改革 |
|---|---|---|---|
| リーダーシップ | コミュニケーション | ||
| 実務知識 | 顧客満足・クレーム対応 | 人材・組織マネジメント | |
| 安全管理・労働災害 |
プランタイトル
2大テーマパーク(ディズニー・ユニバーサルスタジオジャパン)流
シナジー(相乗効果)を発揮させるチームの考え方とその作り方を学ぶ
あわせて読みたい
組織内のチーム力向上のために有効な「チームビルディング研修」。…
2022年に中小企業でもパワーハラスメント防止対策が義務化され…
リーダーシップは誰でも身に付けることができます。学習や実践訓練…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






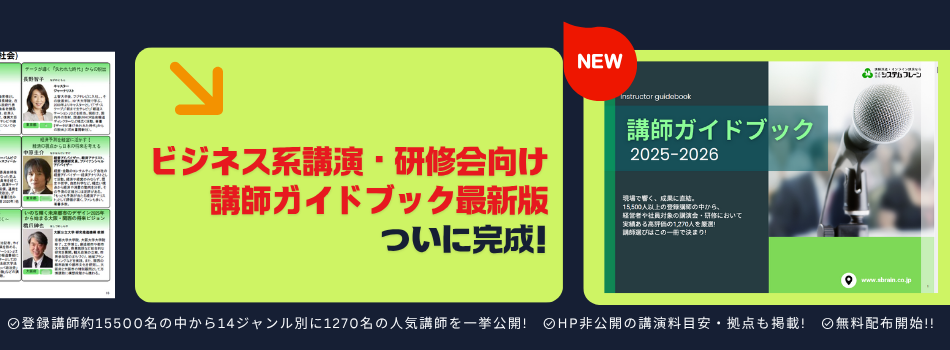











業務外の講師への取次は対応しておりません。