
情報があふれる時代、どれだけ注意し、入念なチェック体制を整えても、「人によるミス」を完全に防ぐのは容易ではありません。こうした課題に頭を悩ませている企業や組織は多いのではないでしょうか。
今回は、認知科学に基づくミス防止の仕事術を開発した宇都出雅巳さんに「ミスを防ぐ実践的なアプローチ」について伺いました。脳のメカニズムを正しく理解し対策を講じれば、多くのミスは防げると言います。
一人ひとりができること、そして組織ができる対策とは何かーー。
すぐに実践できる方法でミスを減らし、生産性の向上や職場環境改善を図りませんか?
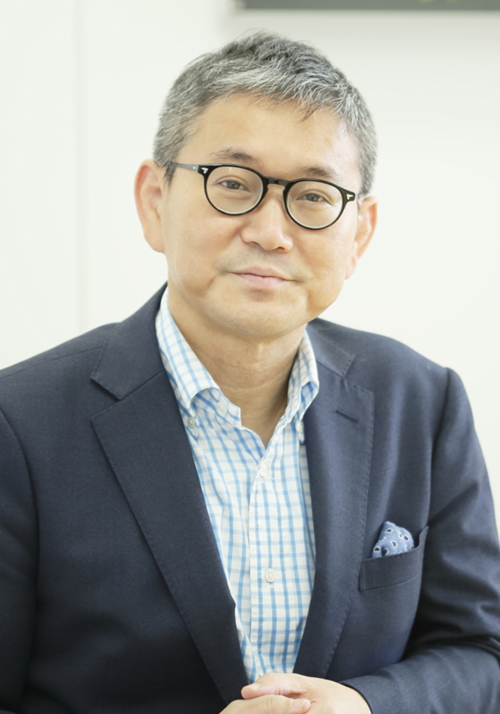 【監修・取材先】
【監修・取材先】
宇都出雅巳氏
ビジネスコーチ
仕事のミスのなくし方コンサルタント
速読勉強術コンサルタント
人はなぜミスをするのか?脳のメカニズムや背景とは?
私たちは日々、大量の情報を受け取り、素早く判断・認識しています。そのために脳は非常に効率的なシステムを作り上げていますが、ある意味、「手抜き」であり「雑」なのです。
脳は入るそばから情報を忘れ、気になるところだけしか見ないなど、うまく手抜きをしながら、情報を処理しています。つまり、人間の脳は思ったほどちゃんと見たり、覚えたりしていないのです。いわば、そもそも脳はミスをする構造になっているのです。
また、ミスが減らない社会的要因としては、情報量が以前に比べて膨大に増えていることも挙げられます。人の「注意」には限りがあるため、情報が増えれば増えるほど、注意が分散し、ミスが起きやすくなるのです。
近年人々の注目そのものが経済的価値を持つという「アテンション・エコノミー」という言葉も注目されています。SNS、アプリ、広告など、あらゆるものが私たちの注意を奪おうとしています。企業は、限られた時間をいかに消費者から奪うか、他の競合から奪うかという競争に注力しています。結果として、注意を引く刺激が増え、集中力が削がれ、ミスが発生しやすくなっているのです。
つまり、情報過多と注意の奪い合いこそが、現代社会でミスが増える大きな要因だと考えられます。
4つのパターンのミスが起こるメカニズムと個人でできる対策とは?
 ミスを防ぐために個人でできることは、まずは脳の仕組みを理解し、ミスのタイプに合わせて対策をしていくことです。ミスのタイプは以下の4つに分類することができます。
ミスを防ぐために個人でできることは、まずは脳の仕組みを理解し、ミスのタイプに合わせて対策をしていくことです。ミスのタイプは以下の4つに分類することができます。
それぞれ原因と対策をご紹介します。
①メモリーミス
<原因>
「覚えたつもりなのに、うっかり忘れてしまう」──そんな経験は誰にでもあります。例えば、隣の部屋に何かを取りに行こうとして、部屋に着いた途端に何をしようとしたか忘れてしまうというようなことです。
これは「ワーキングメモリ(短期記憶)」の特性によるものです。長期記憶とは異なり、ワーキングメモリは容量がとても小さく、新しい情報が入ると、古い情報が押し出されてしまいます。
心理学者・エビングハウス氏による記憶に関する「忘却曲線」の研究によると、20分後には約4割、1日後には7割以上を忘れるという結果が出ています。
つまり、私たちの脳は“忘れるようにできている”のです。逆をいえば、この「忘却」は脳が自動で情報を整理して、不要な情報を処分してくれる「効率的なシステム」とも言えます。
<対策>
情報がワーキングメモリに入っているとき、その情報をしっかりと覚えているという感覚がありますが、これにだまされないことです。ただワーキングメモリに入っているだけで、新しい情報が入ってくると、前の情報は追い出され忘れてしまう「はかない記憶」であることを自覚することが大切です。対策としてはシンプルですが、「メモを取る」ことです。
②アテンションミス
<原因>
「うっかりミス」や「見落とし」など注意の不足によって起こるミスです。誤植やプレゼン資料のチェック漏れなどがこれにあたります。人間の脳は、自動的に情報を補完して読みやすくするため、誤りを見逃しやすい構造になっています。
<対策>
ミスを防ぐには、同時並行であれこれチェックしようとしないことが重要です。例えば、文章をチェックする際には、「内容の整合性」「誤字脱字」など、何に注目してチェックするのかを明確にし、一つずつ集中して行います。ダブルチェックや、文章を後ろから読むなど視点を変えて確認することも良いでしょう。
さらに、チェックリストの活用も有効です。頭の中でチェックできる内容だと思っても、チェックリストを作成することで、ワーキングメモリの負担を減らし、見落としを防げます。実際にアメリカの病院では、チェックリストを導入した結果、ミスが激減したという事例もあります。
ワーキングメモリ自体は鍛えられず、容量を増やすことはできないと考えられています。例えば、膨大な桁数の数字の暗記ができる人をみると、 その人が膨大なワーキングメモリを持っているように思うかもしれませんが、実は、メモリが多いのではなく、語呂合わせや意味づけなどの記憶術を使って、情報量を減らしたり、長期記憶を活用したりしているのです。
このため、人間は忘れる生き物であると理解した上で、なるべくワーキングメモリの負担を減らし有効活用することが大切です。頭の中で覚えておこうとするのは、限られたワーキングメモリを無駄遣いしています。ワーキングメモリを空けた状態にしておくことが、アテンションミスをはじめ、さまざまなミスの防止につながります。さらには思考力の向上や生産性の向上にもつながります。
具体的には以下の対策が挙げられます。
- 気になることは紙に書き出す、人に話すなど情報をアウトプットして、頭の中をスッキリした状態にする。
- スマホなど注意を奪うものを遠ざけ、デスク周りを整理整頓するなど、片付いた環境で作業を行う。
- 専門用語や基本知識を理解し、繰り返すことで長期記憶を定着させたり、仕事の基本動作を体で覚えたりするなどして、ワーキングメモリを使わないで済むようにする。
③コミュニケーションミス
<原因>
意思疎通のずれによって起こるミスです。
私たちは人の話を聞くとき、勝手に(自動的に)過去の記憶が思い出され、その記憶も使い、情景をイメージしながら話を理解しています。
当然、同じ言葉でも人によって思い出される記憶が違うため、相手と理解のズレが必ず生じます。こうした「潜在記憶(勝手に思い出される記憶の働き)」こそが、コミュニケーションミスの最大の原因です。
また、セールスや交渉などの場面では、売り手と買い手が自分の都合の良いように話を解釈してしまうことも、コミュニケーションミスの原因となります。
<対策>
相手が伝えようとしていることと、自分の認識にズレがないか、「それは〇〇ということで合っていますか?」と一言確認するだけで、コミュニケーションミスを大幅に減らせます。
また、抽象的な表現を避け、具体的な言葉でやりとりするということも重要です。例えば、「早めにお願い」と言われたとき、相手と自分が捉える「早め」の基準が同じとは限りません。「明日まで」など具体的に伝えてみましょう。
④ジャッジメントミス
<原因>
「どうしてあんな判断をしてしまったのだろう」というものや、良かれと思って行ったことが裏目に出てしまったというようなミスです。これは、第一印象に引っ張られたり、自分と相手の価値観が異なったりすることで起こります。人は無意識のうちに偏見やバイアスに影響されることがあるのです。
<対策>
判断をする前に、自分が今思い出している潜在記憶の影響を受けていないか、一度立ち止まってフラットな視点に戻し、逆の立場に立って考えることが大切です。
また、相手が何を重視しているのかを確認することも重要です。仕事のスピードを重視する人もいれば、質を求める人もいます。指示された作業の目的などを明確に確認することで、期待のズレを防ぎ、ジャッジメントミスを減らすことができます。
ミス防止と心理的安全性の関連は?職場づくりのヒント

ミスを減らすことと、職場環境のあり方には深い関連性があります。
近年、職場環境のあり方として注目される「心理的安全性」。この考えを提唱したハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が、心理的安全性の重要性に気づいたのは、パフォーマンスが高いチームほどミスの報告件数が多いという調査結果でした。一見すると意外に思えますが、これはパフォーマンスの高いチームではミスを報告しやすい環境が整っていることを意味しています。すなわち、チーム内で隠ぺいが少なく、ミスをオープンに共有できているのです。
小さなミスを隠蔽すると、後で大きな問題に発展する可能性があります。一方、小さなミスをすぐに報告・共有できる職場環境であれば、ミスを防ぐ仕組みを作りカバーできます。心理的安全性が高い職場では、表面的なミスの報告件数は増えるかもしれませんが、重大なミスは減っていきます。
また、ミスを恐れて萎縮すると、「注意」を奪われ、かえってミスが増えることもあります。リラックスできる環境の方が、注意の無駄遣いが起きにくく、結果的にミスが減ると考えられます。
心理的安全性の高い職場にしていくためには、組織として、従業員がミスを言いやすい関係性を築き、失敗を責めない風土を作ることが大切です。ミスを報告しても非難されない環境であれば、隠ぺいを防ぎ、早期に対処することができます。
さらに重要なのは、小さなミスを個人レベルで終わらせることなく、組織全体でミスを防ぐ仕組みを構築することです。はじめはミスが増えたように見えるかもしれませんが、長期的に見ると、ミスは減少し、チームの信頼と生産性は向上していきます。
社会変化に合わせて質が変わるミスとどう向き合うべきか?
 生成AIの普及など社会や時代の変化により、ミスの性質も変わってきています。
生成AIの普及など社会や時代の変化により、ミスの性質も変わってきています。
かつてワープロが普及した頃は、文字の打ち間違いや変換ミスが問題でした。現在では、生成AIの台頭により、AIが出力する情報の信憑性を見抜くチェック能力も求められるようになり、ミスを防ぐ視点も変化しています。
ただ、AIが普及しても、最終的に人間が関わる部分でミスが起こり得ることには変わりありません。だからこそ、「人はミスをするものだ」という前提で、前述のような対策は欠かさず、どのようなミスが発生する可能性があるのかを見極めながら、柔軟に対応していくことが大切です。
また、新しいことに挑戦する上で、ミスはつきものです。ミスを恐れて挑戦しないことは最大のミスとも言えます。「ミスを減らすこと」は大切ですが、「ミスを無くさなければならない」という強迫観念にとらわれることも一種のミスです。
挑戦する過程で起こるミスは、仕組み作りやチームの協力によってカバーしていけば良いのです。そうした試行錯誤の中からこそ、新しい発想やイノベーションが生まれていきます。
ミスを恐れずに挑戦し、ミスと向き合いながら成長していくーー
そんな前向きな職場づくりを目指しませんか?
宇都出さんの講演では、脳の仕組みに基づいたミスのメカニズムや、ミス別の対処法、そして、職場づくりのヒントを詳しく紹介しています。どれもすぐに実践できる対策ばかりで、職場のミス削減とチーム力向上の両立を後押ししてくれる内容です。
ぜひ講演の開催をご検討ください。
宇都出雅巳 うつでまさみ
ビジネスコーチ 仕事のミスのなくし方コンサルタント 速読勉強術コンサルタント
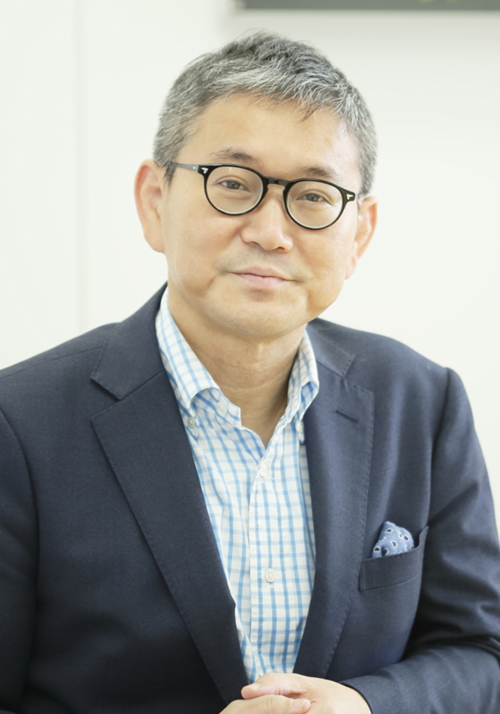
東大卒後、経済誌で編集業務等に従事。コンサル業界・外資系銀行で経験を積み独立。独自の速読法「高速大量回転法」や認知科学に基づくミス防止の仕事術を開発、人材育成や組織開発を支援。公認会計士試験に合格、会計監査にも携わる。講演多数、仕事術等に関する著書25冊以上、累計50万部超。
|
講師ジャンル
|
ソフトスキル | コミュニケーション | |
|---|---|---|---|
| 実務知識 | その他実務スキル | 安全管理・労働災害 |
プランタイトル
仕事のミスをゼロにする!~認知科学に基づく実践的方法~
あわせて読みたい
これまでにない物価高が家計を直撃しています。少子高齢化で年金の…
電気・ガス、ガソリンなどの燃料や物価の高騰が家計を苦しめる一方…
経営、ビジネスをよりよく進めていくためには、情報の収集は欠かせ…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






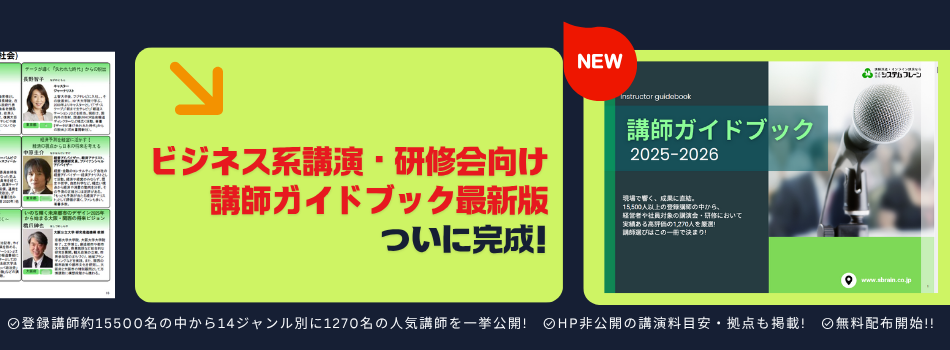

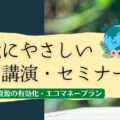









業務外の講師への取次は対応しておりません。