
地震や台風など災害の多い日本では、「防災」は常に関心の高いテーマです。しかし、多くの人はインターネットやテレビで一般的な防災の情報を得たところで安心してしまっているのではないでしょうか?
防災で大切なのは「知識」よりも、いざ災害が起きたときに正しい判断をするための「考える力」です。
今回は消防官として30年の現場経験があり、東日本大震災では現地での救助活動を指揮、さらに火災に関する研究分野でも実績のある永山政広氏に、防災において最も重要なポイントについて伺いました。
※本記事の内容は2025年10月時点のものです。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
永山政広
防災危機管理アドバイザー
検索だけで安心していませんか?防災のポイントは「考えること」
 テレビ番組で「もしも大地震が起きたら、家の中のどこに避難すればいいでしょう?」という問題が出たとき、誰しも一瞬は自分の頭で「どこだろう?」と考えると思います。
テレビ番組で「もしも大地震が起きたら、家の中のどこに避難すればいいでしょう?」という問題が出たとき、誰しも一瞬は自分の頭で「どこだろう?」と考えると思います。
けれど、すぐ後に「正解は、玄関です」と言われると、「そうか、玄関か」と納得してしまい、そこで思考は止まってしまいます。「玄関」という知識だけをインプットして、「これでいざというときも大丈夫」と安心してしまうのです。
しかし実際には、一番安全な場所というのは家によって違います。玄関が正解と言われるのも、一般的には「物が落ちてこない」「閉じ込められない」という条件が揃った場所だからです。つまり間取りや家具の配置など、それぞれの家の状況を確認しなければ、何が本当の正解かは分かりません。自分の目で家の中を見て、自分の頭で考える必要があるのです。
それにも関わらず、現在は手軽に情報が得られるからこそ、ただ知っただけで満足してしまうことが増えています。特にインターネットで検索すれば、避難するべき場所も家に備蓄しておくべき物もすぐに調べられるでしょう。基本的にインターネット上の情報は“分かりやすさ”が重視されるため、どの記事もそれほど頭を使わず簡単に答えを得られ、分かったつもりになってしまいます。
しかし、この“分かったつもり”が落とし穴です。
実際には個々の状況によって正解は変わり、災害時はその場の状況に応じて判断しなくてはなりません。分かったつもりでいるとそこで思考が停止して、考える力は養われません。
しかも災害は頻繁に起きるものではないため、自分自身のその危うい状態に気づかないまま、日々を過ごしてしまうのです。
過去の事例がなぜ防災に生かされないのか?注意すべきポイント
 テレビやインターネットで発信される防災の知識は、基本的に過去の災害の事例に基づいています。では、なぜいつまでたっても災害時の被害はなくならないのでしょうか?
テレビやインターネットで発信される防災の知識は、基本的に過去の災害の事例に基づいています。では、なぜいつまでたっても災害時の被害はなくならないのでしょうか?
過去の事例に基づく知識が完全に生かされるのならば、被害を防げるはずです。
その理由は、災害の進化・大規模化にあります。
現場の消防官として、東日本大震災の発生直後に仙台市に派遣され、現地で救助活動の指揮を執っていた永山政広氏は、当時の自身の体験について、こう語ります。
「瓦礫の下にいる人を助けようとしていたとき、『津波がくる』という緊急速報が入ったんです。私はそのとき突然、現場の指揮官として『救助活動を続けるのか、隊員を避難させるのか』という判断を迫られることになりました。そんな状況でどうすべきかなど、それまで一度も教わったことはありません。東日本大震災のような規模の災害を、誰も想定していなかったからです。
はっきりとした正解はなく、どうすべきか教えてくれる上司も先輩も、誰もその場にいませんでした。どれだけ難しくても、自分で考えて決断するしかなかったのです」
災害は進化し、何かしらの想定外を生むものです。
過去のケーススタディが必ずしも役に立つとは限りません。
このときの経験から、永山氏は「災害の対策で真に必要なのは、知識よりも考える力である」と学んだと言います。
「あのときのような経験は、私の消防官としての30年のキャリアの中でもあの一度きりでした。稀にしか起きないことだから、想定するのは正直難しい。けれど、起きるときには必ず起きるんです」
「もしも自分の身に起こったら?」備えるべきポイントは3つ
 それでは、災害が起こる前に私たちは具体的にどのような対策をすればよいのでしょうか?永山氏は防災を3つの観点から考えるべきだと語ります。
それでは、災害が起こる前に私たちは具体的にどのような対策をすればよいのでしょうか?永山氏は防災を3つの観点から考えるべきだと語ります。
①ハードウェア
ハードウェアは「物」の備えです。
水や非常食を用意したり、枕元に懐中電灯を置いたり、耐震性の高い家に住むことなどがこれにあたります。
テレビやインターネットで得られる防災の知識の多くは、このハードウェア面に偏りがちです。もちろん物を用意しておくことは大切ですが、それはあくまでも防災の一面でしかないと理解しておく必要があります。
②ソフトウェア
ソフトウェアは、組織や仕組みづくりの備えです。
地域の自治会や会社組織の中には、「災害時にどう対応するか」というマニュアルが用意されているでしょう。こうした組織だった対策が一人ひとりの命を救うために重要な役割を果たします。
特に自治体や会社組織では、物の備えだけでなく、災害時に機能するシステムを整えておくことが求められます。
③ヒューマンウェア
永山氏が最も重視するのが、ヒューマンウェア、すなわち”人間一人ひとりが持つ力”です。具体的には「もしものときに、どう行動すべきか」を考える力や、周囲と助け合い共に危機的状況を乗り越える力などを指します。
常に想定外のことが起きる大災害では、平時に備えていた「物」や「仕組み」に頼れない場面が出てきます。そのときに自分の命を守ることができるのは、自分だけです。
では、インターネットの検索で答えが得られないような状況で生き延びる力は、どうすれば身に付くのでしょうか?
永山氏はこう強調します。
「大切なのは、想像力を養うことです。想像力は、危険が迫ったときに「どう行動するべきか」の答えを見つける力です。」
災害時には、誰にも頼れず、正解を自分で探さなくてはならない場合があります。そのときのために、日頃から「もしも自分だったらどうするか」を具体的にイメージし、想像力を鍛えておくことが重要です。
たとえば災害のニュースを見るとき、気になったことをすぐにインターネットで検索するのではなく、自分の頭で「今この場で同じ規模の災害が起きたら、自分ならどう行動するか」を考えてみましょう。
検索では一般的な知識しか得られず、それが必ずしも自分自身の状況に当てはまるとは限りません。しかし想像力が鍛えられていれば、その場に応じた最適な答えを自分で見つけられるようになります。
防災のポイントを抑えて、もしものときに命と生活を維持すること
 消防官として東日本大震災地の救助活動も経験した永山氏は、防災において「物」や「組織」の力には限界があると感じたと言います。
消防官として東日本大震災地の救助活動も経験した永山氏は、防災において「物」や「組織」の力には限界があると感じたと言います。
「もしも一人ひとりにもっとヒューマンウェアの備えができていれば、救助が間に合わない場面でも、個々で正解を見つけて助かる命があったのかもしれない」
そんな思いから、永山氏は「知識のインプットよりも、考える力を養う防災対策」という観点で、自治体や企業を中心に精力的な講演活動を続けています。
これらの組織が運営する防災研修においては、ただ知識を伝えるのでなく、受講者の意識づくりや想像力向上を目的とするべきだ、と語る永山氏。組織や仕組みで補えない部分を、個々の力を伸ばすことによって補うのが、今後の防災研修で求められるあり方だと提唱しています。
永山氏の講演では、受講者自身が主体的に防災について考え、想像力が養われるようにプログラムが設計されています。防災というテーマであっても決して難解な内容ではなく、まずは楽しいワークによって頭をほぐすウォーミングアップから始まるため、誰でも気軽に参加できると好評です。
一般的な防災知識の提供に留まらず、命を守るための実践的スキルが身に付く研修をお探しのご担当者様は、ぜひ次回の研修企画としてご検討ください!
永山政広 ながやままさひろ
防災危機管理アドバイザー

消防官として30年間活動しながら、火災調査技術向上の研究などに従事。火災・自然災害や企業のBCP対策、防災コミュニティなどに精通。消防現場経験と研究知見の両面を踏まえた指導が強み、市町村や企業の防災・減災対策を支援。講演やメディア出演も多数、専門知識を活かしてドラマ・映画監修も担う。
|
講師ジャンル
|
実務知識 | 危機管理・コンプライアンス・CSR | 安全管理・労働災害 |
|---|---|---|---|
| 人材・組織マネジメント | その他実務スキル | ||
| 社会啓発 | 防災・防犯 |
プランタイトル
”覚える防災”から”考える防災”へ
あわせて読みたい
2011年東日本大震災、2016年熊本地震に続き、2024年1…
災害大国である日本は、常に地震や台風などの脅威にさらされていま…
地域の少子化、空き家問題、コミュニティの希薄化、公民館の担い手…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






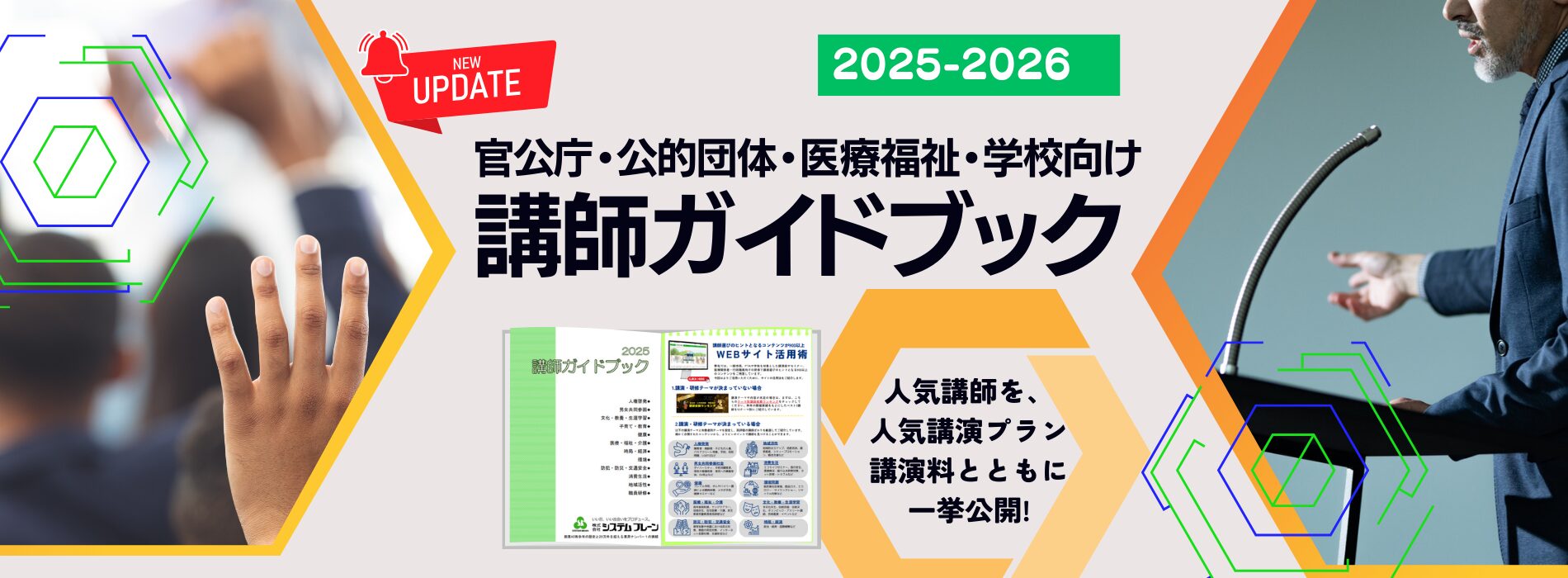











業務外の講師への取次は対応しておりません。