
 テレビや新聞だけでなく、SNSなどを通じて、私たちは日々多くの情報に触れる時代となりました。真実はどこにあり、どう受け止めるべきなのでしょうか。
テレビや新聞だけでなく、SNSなどを通じて、私たちは日々多くの情報に触れる時代となりました。真実はどこにあり、どう受け止めるべきなのでしょうか。
今回は、元新聞記者でジャーナリストの三枝玄太郎さんに、これまでの歩みや事件報道の裏側などについて伺いました。私たちがどのように情報やニュースと向き合うべきなのか、そのヒントが詰まった内容となっています。「報道を見る目」を養うきっかけとして、ぜひご一読ください。
※本記事の内容は2025年7月時点のものです。
信頼関係を築けるかが記者としての腕の見せ所
ーーまずは、三枝さんのこれまでのご経歴を教えてください。
三枝 事件取材をしたいという思いから、1991年4月に産経新聞社に入社しました。最初は静岡支局に3年間勤務し、うち約2年は静岡県警察を担当しました。1993年に東京社会部へ異動、遊軍(特定の担当を持たず、幅広く取材をする記者)を約1年経験、その後、警視庁担当として3年間、生活安全部や、捜査一課、捜査三課(※1)を取材しました。
東京社会部では、国税庁を最も長く担当し、約8年間取材を続けました。その後、通算して約4年間、国土交通省を担当、建設業界と政治家の「口利き」問題などにも向き合いました。
その他にも、東北総局のデスクや防衛省、Webニュース担当も経験しています。Webニュースを扱う部署では、読者がどんなニュースに興味を持つかを意識しながら、人気記事の傾向を学びました。
2018年に退職し、現在はフリーランスとして全国で取材活動を行い、YouTubeなどでニュースの解説を配信しています。特に政治関連のニュースは、視聴者の関心が持続しやすく、反響が大きい話題は繰り返し取り上げるようにしています。
また、新聞社記者時代から始めた再生可能エネルギーの業界の取材は、現在も継続して行っています。
※1:生活安全部:防犯や日常生活に関わる犯罪の取り締まりを行う部、捜査一課:殺人や強盗など凶悪事件の捜査を担当、捜査三課:窃盗事件を担当)
ーー記者という仕事の魅力は、どんなところにあるとお考えですか?
三枝 やはり「人」が相手の仕事だという点だと思います。記者の仕事は非常に手間と時間がかかります。取材先に足を運び、信頼関係を築いていくプロセスは、営業職に近いものがあると感じています。いかに取材相手と信頼関係を築けるかによって、記事に書く内容が変わってくるのです。
警察担当時代、最初は相手にされず、空回りする時期もありましたが、それでも粘り強く足を運び続けることで、徐々に刑事の方と信頼関係を築いていきました。
逮捕のニュースが報じられても、報道されるのは事件全体のほんの一部です。例えば殺人事件では、被害者の交友関係の聞き込み、犯人の動機の特定など、多くの捜査を重ねて容疑者を絞り込んでいきます。
防犯カメラが普及していなかった時代は、半年かけて内偵調査することも多かったです。一例を挙げると、事件現場近くの高速道路の通行チケットを全て回収し、被害者に関係のある人物の指紋が出れば証拠の一つとなります。あるいは、遺体遺棄現場で見つかったガムテープに付着した繊維から、特定の絨毯、そして絨毯があった場所を特定していきます。こうした複数の証拠をつなぎ合わせて、犯人を特定していくのです。しかし、警察の発表では、「様々な証拠を総合して逮捕した」としか伝えられません。
ここで記者の真価が問われます。どれだけ刑事と信頼関係を築けるかによって、裏側の情報を引き出せるかが決まるのです。
また、証拠が不十分な段階で逮捕に踏み切った場合などは、信頼できる警察官から情報を得ることで「今回の捜査の進め方は強引だった」といった見立てもできます。それくらい警察官と関係性を築いていくことを目指しながら取材を行っていました。

ーー三枝さんが取材相手と信頼関係を築く上で、大切にしていることは何でしょうか?
三枝 最も大切にしていたのは「取材相手を裏切らないこと」です。
公務員は地方公務員法や国家公務員法により、原則として情報を外部に漏らしてはならないと定められています。そのため、情報源が特定されないように記事を出すタイミングを見計らったり、2人だけにしか分からない暗号で連絡をとったりと、情報源を守ることは徹底していました。他社が同じ情報を掴んでいるかもしれないという緊張感の中で、記事の出稿タイミングを見極めるのは大きな駆け引きでもありました。
また、私は現場や取材相手の元に足を運び、多くの人と繋がる努力を大切にしていました。特に新人時代は、とにかく多くの場所に顔を出し、接点を増やすことに注力していました。接点が増えれば、波長の合う相手と出会える確率も高くなります。
栃木県警担当のときは、県内にある全ての警察署(当時22署)を夜中に訪問していました。夜間であれば、他社の記者もおらず、警察官と落ち着いて話をすることができたからです。こうした積み重ねの中で、今でも交流が続くような一生のご縁となる出会いもありました。
事件事故を伝える記者としての葛藤と使命感
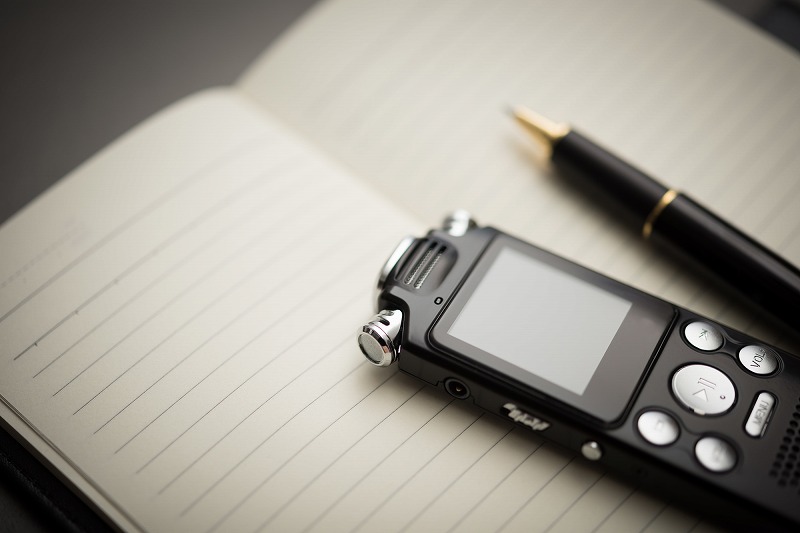 ーーこれまでの記者人生の中で最も印象に残っている取材は何でしたか?
ーーこれまでの記者人生の中で最も印象に残っている取材は何でしたか?
三枝 印象に残っているものはたくさんありますが、特に心が痛むのは、事件や事故で人が亡くなったときに、紙面に掲載するため、亡くなった方の顔写真を手に入れるという仕事でした。
特に印象に残っているのが、2008年に栃木県で自宅から歩いて出て行ってしまった小さなお子さんが、近所にあった学校のプールに落ちて亡くなるという事故です。学校の周辺には植木がありましたが、その隙間から入ってしまったんです。
私が一報を聞いて事故現場に駆け付けると、現場にいた警察官に「そこを見てごらん」と言われました。藻で覆われていたプールの一角が白くなっている部分が目に入りました。「ここに子どもさんが落ちて、もがいていた場所だよ」と言われ、胸が締め付けられる思いでした。
翌日、私はお花を買い、お子さんの自宅を訪ねました。家の中に入れてくださり、亡くなったお子さんを目の前にしたとき、当時2歳だった自分の子どもと同い年ぐらいだと感じました。「もしこの子が息子と出会っていたら、友達になれていたかもしれない」と考えたら涙が溢れ、気づいたらそのお子さんに抱きついていました。
「もし学校にフェンスがあったら、今後このような事故は防げるのではないか」と考え、記事を書きました。この記事が一つのムーブメントになり、事故があった市内の小学校や中学校のプール周りには、現在フェンスが設置されています。
ーー被害者の写真の掲載について、どのようにお考えですか?
三枝 写真があることで、ニュースと正しく向き合えると思っています。
1999年に栃木県で19歳の男性が亡くなるリンチ殺人事件が発生しました。何度も親御さんが、複数の警察署に足を運び、助けを求めていたにも関わらず、警察は全く動かなかったんです。男性は2カ月余り拉致され連れ回された後、熱湯をかけられるなどの暴行を受け、最後は命を奪われてしまいました。
事件の第一報は、「暴走族の少年がリンチされて殺された」という内容のもので、当初、「暴走族の一員だったから」として、どのメディアも動きが鈍かったんです。しかし、被害者の男性の自宅に伺い、男性の写真を見せてもらったところ、本当に真面目そうな方でした。その顔写真と共に事件の問題点を記事にしたことで、社会の事件に向けられる目が変わりました。
また、誰かが亡くなった際に、その方の写真があると世論が喚起され、行政などが対策に乗り出しやすくなるということもあります。このような様々なケースがあることをご遺族にご説明した上で、写真の提供をお願いすることもありました。
報道関係者が被害者や遺族と接点を持つ時は、本来、ご家族にとっても来てほしくないタイミングです。企業の不祥事などもそうですね。だからこそ、「私が同じ状況になった時、どう感じるか」を常に考えながら取材にあたっていました。
情報化社会のいま、どうニュースと向き合うべきか
 ーー報道やニュースを見る上で、私たちが意識すべき点はどんなことでしょうか?
ーー報道やニュースを見る上で、私たちが意識すべき点はどんなことでしょうか?
三枝 新聞社によってスタンスが異なります。同じニュースを取り上げていても、切り口や表現・書き方が違うのです。現在は、インターネット上でも様々な情報が得られ、ある新聞社の記事を読むと、他社の関連記事が表示されることが多いですよね。一つの媒体や一方向からだけでなく、様々な角度からニュースを見る意識を持つことが大切です。
ネット上には、誤情報も含まれます。SNSで流れてきた情報でも、多くのメディアで報じられていない場合は、信憑性を疑う姿勢も重要です。発信源を見極めながら、一つの情報について、クロスチェックやトリプルチェックを行うスタンスを持っていただければと思います。
ーー事件がどのように動き、報道されるかという背景を、なぜ私たちが知るべきだとお考えですか?
三枝 例えば火災に巻き込まれ、症状が重いときは「重症」、交通事故で大けがをしたときは「重傷」と表現します。こうした言葉遣いを知っておくことで、情報の受け取り方や理解度も変わってくると思います。
また、誤認逮捕も稀に発生します。ある事件の捜査本部が置かれた警察署で、捜査を指揮する捜査一課長への囲み取材の際に、とある記者が「犯人が出頭したという話がありますが」と尋ねたところ「それは答えられない。でも逮捕はそんなに遠くはならない」と答えました。
これを受けて某新聞社が「容疑者逮捕へ」という記事を出しました。私も同様の記事を出稿しようと思い、親しくしていた警察官に連絡をしたところ「逮捕はしない」という返答でした。理由を尋ねると、検察庁のナンバー2である次席検事(実質の責任者)が逮捕を認めなかったとのことでした。これを聞いて、私は記事を書くのを止めました。
数日後、再びその警察官に会いに行くと、「出頭してきた人は犯人ではなかった」と言われました。詳しく聞いてみると、殴られて亡くなった被害者の歯は折れていましたが、出頭してきた少年の手はキレイだったそうです。次席検事はそこに注目し「辻褄が合わない」と判断して逮捕を見送ったのです。
実は出頭した少年は身代わりで、本当の犯人は逃亡していました。犯人の手には大きな傷があったそうです。親しかった警察官から、情報を得られなかったら、自分も誤った記事を出していたかもしれません。
殺人事件なのに自殺だと断定して捜査を打ち切ったり、誤認逮捕が起きたりということが、稀ではありますが実際にあります。だからこそ、記者はそうした可能性を踏まえながら取材をし、いかに信頼できる人脈を築くかが非常に重要だと、私は確信を持って言えます。
こうして記者が取材した内容が記事として掲載されます。事件がどのように取材・報道されているかを知ることで、私たち一人一人のニュースとの向き合い方も変わるのではないでしょうか。
公平な社会に向けて関心を高める機会の提供へ
ーー講演を通してどんなことを伝えていきたいですか?
三枝 記者としての経験がある立場だからこそ伝えられるみなさんの生活や社内対応に役立つ情報をお伝えしたいと考えています。
例えば新聞社によってスタンスが異なるので、情報の見分け方や、企業が記者会見を開く際の注意点や意義などです。
また、講演活動を通して、公平な社会や努力している人が報われる社会づくりの一助になりたいと考えています。
例えば政治家のスキャンダルもその一例です。過去には、新聞社のスクープによって総理大臣が退陣に追い込まれた事案がありました。政治家が未公開株を入手し、公開時に大儲けするということが多くあったんです。そうした不公平は許されないと、報道が社会に問いかけたのだと思います。
多くの人に、もっと社会の様々なことに関心を持っていただきたいと思っています。その意識の大切さを今後も伝えていきたいです。
ーー最後に、三枝さんの「夢」と題して、今後の展望をお聞かせください。
三枝 日本はこれからますます少子高齢化が進み、周辺諸国の動向にも不安が高まる状況となっています。私は子どもや孫の世代にも、日本が平和国家であり続けてほしいと思っています。平和とは何か、どうすれば平和を維持できるのかを提案しながら、世論に働きかけていきたいです。
そして、皆さんで一緒に考えるコミュニティやサロンを作りたいと考えています。右翼・左翼といった立場にとらわれず、一緒に考え、お互いに知恵を出し合えるような場を作り出すことが、今の大人の責任の一つなのではないかと感じています。
ーー本日は貴重なお話ありがとうございました。
三枝玄太郎 さいぐさげんたろう
ジャーナリスト フリーライター 元産経新聞記者

早稲田大学政治経済学部卒業後、産経新聞社入社。東京社会部(警視庁、国税庁、国土交通省等)、大阪社会部(大阪国税局)、東北総局次長等、事件・事故の現場取材多数。2019年退社。YouTube「玄ちゃんねる」動画配信、インターネット番組「文化人放送局」レギュラー出演中。著書『事件報道の裏側』他。
プランタイトル
メディアの偏向報道の具体例 それを見分ける方法
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されましたあわせて読みたい
少子高齢化で、ますます厳しくなる中小企業の人材確保ー。 専門ス…
ADHDの診断を受け、すべてを失いかけても何度でも立ち上がり、…
FIRE達成や世界一周といった華やかな実績の裏に、自己否定や貧…
他の記事をみる







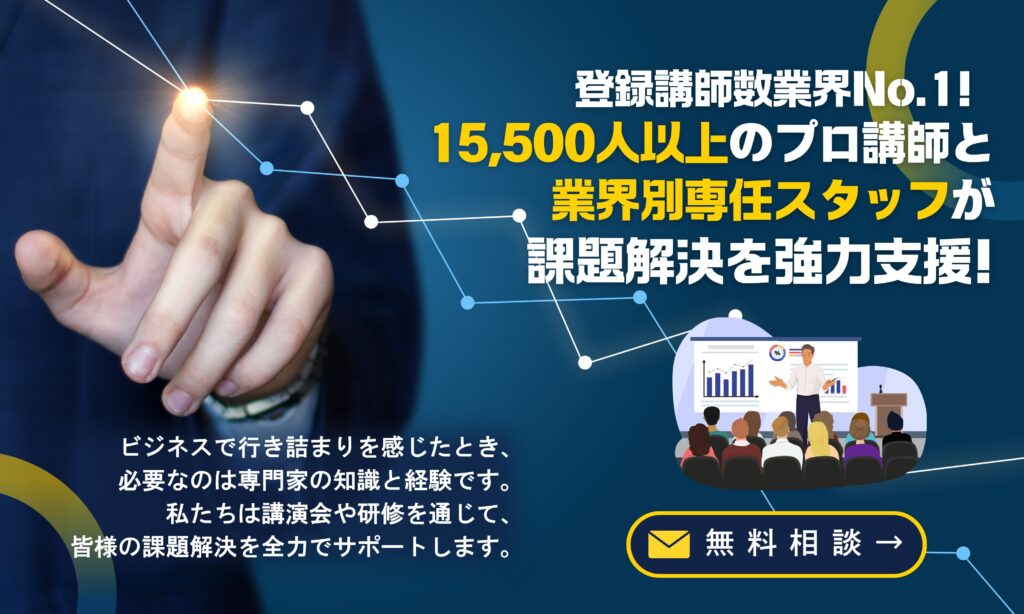











業務外の講師への取次は対応しておりません。