想定する対象者
多くの方は「怒りの感情」に対してネガティブなイメージをお持ちです。
・怒ってはいけない
・怒りは悪いもの
・怒ると疲れる
怒って後悔したり罪悪感を覚えたり、自己嫌悪で自分が嫌になったり..
怒りについての正しい知識を得ることで、イライラに振り回されない生き方ができるようになります。
苦手だった相手とも上手くコミュニケーションがとれるようになることで、報告・連絡・相談がスムーズになり、ちょっとした危険の兆しが共有できることは大きな問題や事故への防止となります。
現代社会では、現場での的確な判断と対応が求められる中、自分の感情をコントロールし、安全な環境を守り、顧客の満足度の向上やクレームの発生を未然に防ぐことは重要な課題です。
企業にとって重要なリスクマネジメントともなります。
どのような場面に遭遇するか、予測のつかないことが多々発生しうる状況への対策も必要であり、判断を誤らない為にいつも平常心でいられるよう、自分自身の感情をマネジメントすることはとても重要です。
・企業で人事、総務、管理職をされている方
・職場での人間関係に課題を抱えている方
・職場での人間関係を良好に保ちたいと考えている方
・アンガーマネジメント的チームビルディングを学びたい方
提供する価値・伝えたい事
パワハラ加害について、頭では理解していても感情がついていかずに、加害者の85%以上がイライラしていたということがわかっています(2019年9月“怒りとパワハラの関係性”に関する調査より)。
つまり、パワハラ防止のためには、法律の理解と怒りの感情と上手に付き合うためのスキル(アンガーマネジメント)が車の両輪の輪として機能することが非常に重要です。
厚生労働省が運営する「明るい職場応援団」では、「ハラスメントを防ごうとするあまり、部下への指導が難しくなっている」と悩む管理職に向けて、アンガーマネジメントを習得する研修が効果的と紹介されています。
人がお互いに人権を尊重しあい、誰もがいきいきと働ける職場づくりができるようになるために、パワハラの基礎的な法的知識に加えて、アンガーマネジメントを生かしてどのようにパワハラ防止につなげられるのか、考え方や具体的なテクニック等を学び、組織づくりのあり方に重点を置いたアンガーマネジメント的なチームビルディングを習得します
内 容
■パワーハラスメントとは
■パワーハラスメントの6類型
■パワーハラスメント法制度の動き
■パワーハラスメントを防止するために
■アンガーマネジメントとは
■私たちを怒らせるものの正体
■怒りが生まれるメカニズム
■アンガーマネジメント的組織づくり
■アンガーマネジメントによるパワーハラスメント防止の効果 etc..
その他、実施時間やご要望に応じて下記を組み込んでのカスタマイズが可能です。
<サンプル>
・自分と相手の価値観のすり合わせ
・合意形成への許容度の上げ方
・目標達成への活用
・部下育成のための望ましい叱り方 etc.
根拠・関連する活動歴
アンガーマネジメントは、職場内でのコミュニケーションの質の向上やお客様やお取引先様への対応、ご家庭で、すべての”人”の関わりに効果を発揮します。
受講者満足度・理解度・活用度90%以上の実績で、効果的にお伝えさせていただきます








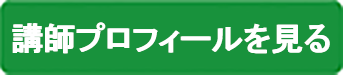


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました













業務外の講師への取次は対応しておりません。