
2025年に戦後80年を迎え、戦争の記憶を語り継ぐ人々が少なくなりつつある今、「どうやって次世代に平和の大切さを伝えていくか」が問われています。
今回は、落語を通して戦争の記憶を後世に伝える取り組みを行っている桂花團治さんに、落語を通じて戦争の記憶を語り継ぐ意義や、戦争を知らない世代が持つべき意識などについてお話を伺いました。
落語が持つ可能性、そして「当事者意識」や「想像力」といったキーワードとともに、私たちに求められていることが詰まった内容となっています。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
桂 花團治氏
落語家 公益社団法人上方落語協会 理事
戦争の記憶を後世に伝える「伝戦落語」とは?
花團治さんの先代である二代目桂花團治は、襲名した翌年の昭和20年6月15日、大阪大空襲によって防空壕の近くで亡くなられました。47歳という若さでした。
先代の無念の思いを後世に伝えていこうと花團治さんが始めたのが戦争を伝える「伝戦落語」の創作です。これまでに3つの作品が生み出されています。最初の作品は亡くなった先代を題材にした「防空壕」。2作目は花團治さんが創作した落語「伝鐘」をもとに、大阪音楽大学の学生たちが作曲するというコラボレーションも実現しました。
そして3作目は、空襲で多くの命が奪われた場所で植樹された桜の木を題材にした「じぃじの桜」です。観光客を迎えるため、寄付を募って大阪城公園一帯に桜を植樹する事業に、花團治さんの義父が多額の寄付をしました。幼い時に戦争を経験し、打ち上げ花火の音を爆弾の音と重ねて苦手だと語っていた義父は、桜に平和への願いを託したのでしょうか。
現在、大阪城公園は外国人観光客でにぎわい、平和の象徴ともいえる光景です。
伝戦落語は、戦争にまつわるエピソードを交えながら、平和への願いを込めた作品となっています。
現在創作中の4作目は、戦時中に多くの動物園で動物たちが殺処分される中で、戦後までゾウが生き残った動物園を題材にした絵本「ぞうれっしゃがやってきた」に着想を得ています。
この作品の中では、動物園の話だけでなく、防寒具のために殺された犬や猫、そして、金目のものも奪われ廃業に追い込まれた商店の話など、戦場だけでなく、私たちの日常の中にも暗い影を落とした戦争の様々な側面を描いています。
伝戦落語で描く人々の日常の暮らしと人生
戦時中には、戦争を美化する落語が存在していました。落語、浪曲、漫才といった大衆芸能も、戦争のプロパガンダに利用されていた時代があったのです。だからこそ平和を願う落語の存在は、現代において重要な意味を持つものなのです。
花團治さんの伝戦落語では、戦場ではなく日本で暮らしていた人々の暮らし、いわゆる「銃後の暮らし」に焦点を当てています。これまで平穏な日常を送っていた人々が、突如として戦争に巻き込まれていく様子を描き出しています。
そして、この伝戦落語には、鎮魂の思いが込められた「能」の要素が取り入れられています。物語の最後には、登場人物の魂が解放され、明るい未来への希望が見える構成となっていて、平和への強い願いが込められています。
また、戦争に関する書籍や資料だけでなく、実際に戦争を体験した人たちのもとに足を運び、その真実や生の声を落語に織り込んでいます。遠い過去の出来事として捉えがちな戦争の記憶を、身近に感じてもらうための工夫が、この伝戦落語には凝らされているのです。
花團治さんの講演会では、創作された伝戦落語に加えて、戦争体験者の話や、家族に関するエピソードも語られています。
花團治さんの母方の祖父は満州に出征し、その体験を武勇伝のように語っていました。過酷な体験をしながら生き抜き、自らの心を保つための術だったのかもしれません。戦争の記憶は、正当化しなければ持ち続けることが難しいほど、重く苦しいものだったに違いありません。
一方で、反戦を訴え獄中で亡くなった父方の祖父。花團治さんは、様々な角度から戦争を見つめ、癒えることのない苦しみや恐ろしさを伝えています。
戦争を伝える一つの形|「落語」だからこそ伝えられることとは?

▲伝戦落語を披露する花團治さん(花團治さん提供)
悲惨な戦争の映像を見て恐怖を感じ、目を背けてしまう人もいるかもしれません。しかし落語は想像の世界です。想像力を刺激されるからこそ、物語の世界に没入しやすく、登場人物の置かれた環境や感情をリアルに感じ取ることができるという一面を持っています。
さらに、落語には「笑い」の要素が含まれています。
例えば、伝戦落語には空襲後の焼け野原を歩く2人の男性が冗談を言い合う場面があり、「こんなことでも言わないと気が持たない」という言葉が出てきます。悲惨な状況下だからこそ、人々は生きるために笑いを求めていたのです。
時折、笑いを挟み、ふっと息を抜きながら戦争の話を聞くことができるのは、落語ならではです。こうした演出が、聞く人たちの心や記憶に残り、戦争について考えるきっかけとなって、戦争の記憶を未来に伝えることに繋がっているのです。
そして、落語は登場人物を自由に増やすことができるのも大きな特長です。1つの出来事に対して、様々な意見を持つ人物を登場させることができます。古典落語を例にとっても、登場人物への捉え方は人それぞれです。
落語という世界に落とし込むことで、私たちは多様な視点を持ち、多面的な考えや意見に触れ、深く考える機会を得られるのです。
戦後80年、戦争を知らない世代ができることとは?
 日本は戦後80年という節目を迎え、戦争を知らない世代に、どのように戦争の記憶を継承していくかが喫緊の課題となっています。戦争を知らない世代にとって最も大切なことは「自分事として捉え、当事者意識を持つ」ということです。
日本は戦後80年という節目を迎え、戦争を知らない世代に、どのように戦争の記憶を継承していくかが喫緊の課題となっています。戦争を知らない世代にとって最も大切なことは「自分事として捉え、当事者意識を持つ」ということです。
花團治さんの落語には、日本は被害者であると同時に加害者でもあるという視点が盛り込まれています。「戦争を始めるということは、加害者にも被害者にもなり得るということ、勝敗に関わらず、多くの犠牲者が出てしまう」という戦争の本質を伝えています。
私たちは日常の中で、交通事故で子どもが亡くなったというニュースに触れると、子どもを持つ親は誰しもが心を痛め、自分事のように感じると思います。戦争も同じことなのです。
世界に目を向けると、ウクライナとロシアの戦争、ガザ地区の紛争など争いが絶えません。
日本もいつ巻き込まれても不思議ではなく、決して他人事ではありません。「被害者にも加害者にもならない」これこそが平和な社会なのです。
私たちに求められるのは「想像力」です。理屈では「戦争はやってはいけないこと、戦争の記憶を風化させてはいけない」と分かってはいるものの、さらに一歩踏み込み、「もし戦争が起こったらどうなるのか」という具体的な想像力を働かせて考えることが重要です。
「自分の大切な人が明日突然いなくなってしまうかもしれない。二度と会えなくなってしまうかもしれない」。想像力を働かせることによって、私たちには戦争をより現実的な問題として捉える必要があるのです。その想像力を掻き立てる上で、落語は大きな役割を果たしています。
後世に繋ぐ戦争の記憶と平和の願い
 吃音に悩んだ時期や特別支援学級への転入を勧められた経験、いじめを受けた体験も持つ花團治さん。こうした経験が落語の持つ優しさに気づくきっかけとなりました。相手を排除するのではなく受け入れる、落語は人に対する眼差しや声かけが優しく、温かい芸能なのです。自身の劣等感を乗り越え今がある花團治さんは「誰かの救いになれれば」という思いを持ち舞台に立っています。
吃音に悩んだ時期や特別支援学級への転入を勧められた経験、いじめを受けた体験も持つ花團治さん。こうした経験が落語の持つ優しさに気づくきっかけとなりました。相手を排除するのではなく受け入れる、落語は人に対する眼差しや声かけが優しく、温かい芸能なのです。自身の劣等感を乗り越え今がある花團治さんは「誰かの救いになれれば」という思いを持ち舞台に立っています。
そんな花團治さんが創り出す温かい落語は、私たちの心に優しく語りかけ、平和や戦争について改めて考える機会を提供しています。
「戦争は人殺しなので、絶対にいけない」という結論だけでなく、「なぜいけないのか」を自分の身に置き換えて考えることの重要性を訴えかけています。
また、戦争だけでなく、あらゆることへの差別や偏見も含めて、今一度、私たちの日常生活や言動を見つめ直し、考える時間となることでしょう。ぜひ「講演と伝戦落語」の実施をご検討ください。
桂 花團治 かつらはなだんじ
落語家 公益社団法人上方落語協会 理事

大阪芸大中退後、二代目故桂春蝶に入門。毎日放送「落語家新人コンクール」優勝。2015年70年ぶりの名跡復活となる「三代目 桂花團治」襲名。20年以上の狂言稽古で培った「声」を活かした演目に定評がある。独自のコミュニケーション論が評判となり、「大阪で一番多く教壇に立つ落語家」としても知られる。
|
講師ジャンル
|
社会啓発 | 教育・青少年育成 | 人権・平和 |
|---|
プランタイトル
落語を通して戦争の記憶を後世に~伝戦落語:未来へつなぐ噺~
あわせて読みたい
今年(2023年)10月から施行されたインボイス制度。特に年間…
コロナ禍以降、営業は訪問型からオンライン型に移行し、売り方の方…
日本では少子高齢化により労働力不足がさらに加速すると予測され(…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






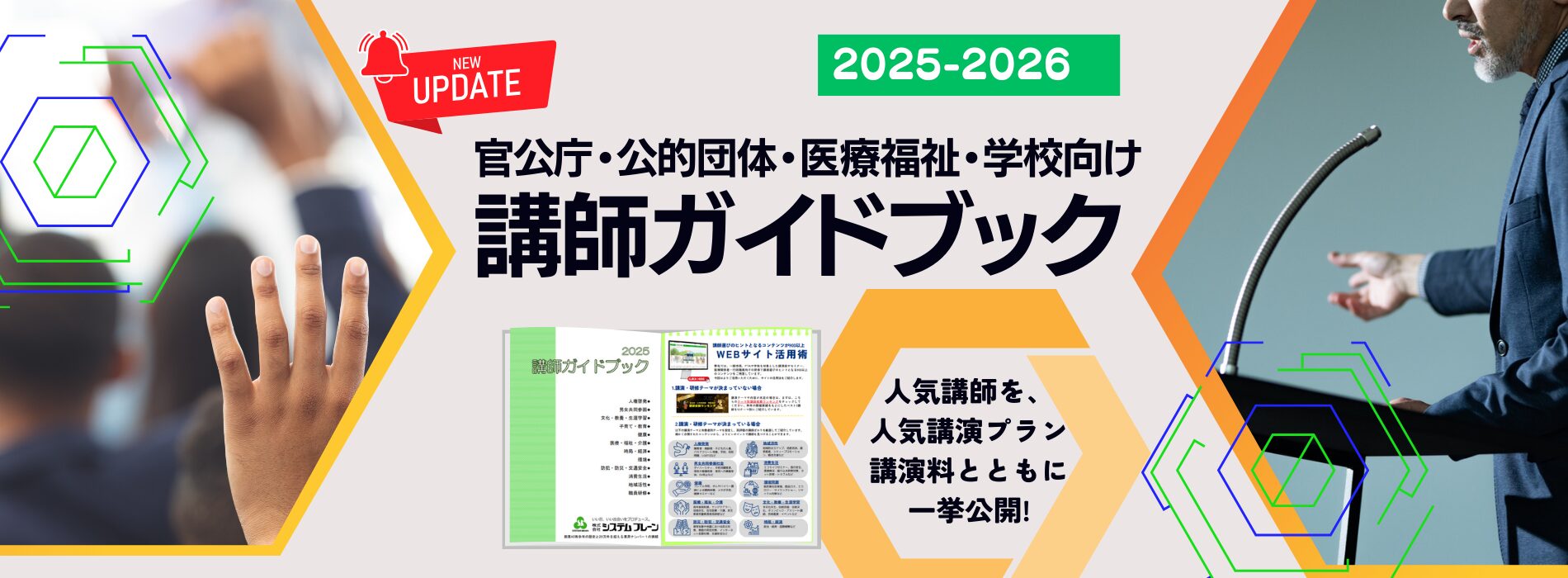











業務外の講師への取次は対応しておりません。