
 人口減少が進む日本では多文化化がさらに進むとされ、多様性の尊重が求められるようになりました。私たちはどう他者と関わり、共に生きていくべきなのでしょうか。
人口減少が進む日本では多文化化がさらに進むとされ、多様性の尊重が求められるようになりました。私たちはどう他者と関わり、共に生きていくべきなのでしょうか。
今回は文化人類学者の斗鬼正一さんに、人間の面白さや「しなやかに、したたかに」生きるヒントについて伺いました。
「常識は一つではない」。
差別や対立が絶えない、変化の激しい時代を生きる私たちが、価値観の違いを受け入れながら「心豊かに生きていく」ためのヒントが詰まった内容となっています。
文化人類学との出会い、学問の可能性は
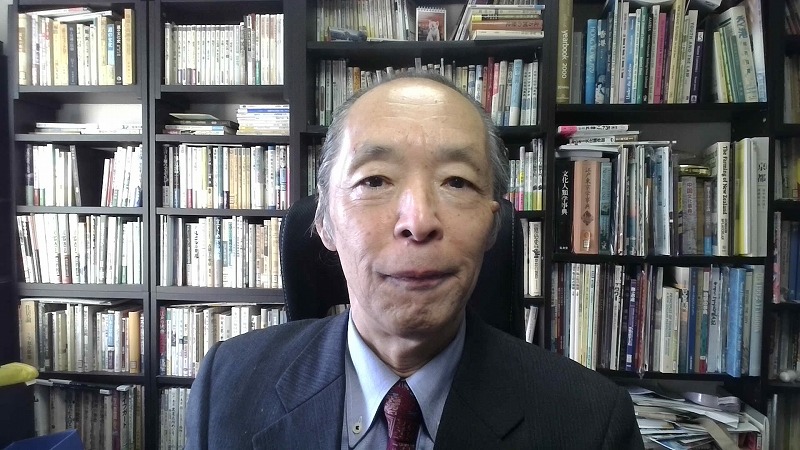 ーー斗鬼さんと文化人類学との出会いを教えてください。
ーー斗鬼さんと文化人類学との出会いを教えてください。
斗鬼 私はもともと、メディア業界を志望していたので、大学は政治経済学部に進学しました。そこで最初に受けた授業が文化人類学だったのです。当時は名前すら知りませんでしたが、その授業で、世界には日本人の想像を超える多様な文化があることを知り、大きな衝撃を受けました。それが文化人類学との出会いでした。
また、私の地元・鎌倉には昔から多くの外国人が訪れ、近隣には横須賀基地もあるため、アメリカ人も多く住んでいます。こうした多文化な環境も、文化人類学に関心を持つきっかけになったと感じています。
文化人類学と出会って以来、50年以上にわたり研究を続け、日本各地や海外でフィールドワーク(現地調査)を行っています。フィールドワークでは、ラポール(親密な信頼関係)を築くことを大切にしています。短期間の訪問では表面的な情報しか得られません。文化人類学のフィールドワークは、できるだけ長期間、できるだけ深く現地の人たちの暮らしに寄り添います。そうすることで、本音や生活のリアリティが見えてくるのです。

▲スリランカでのフィールドワークの様子(斗鬼さん提供)
ーー斗鬼さんは、文化人類学の可能性をどのように感じていますか?
斗鬼 社会は急に変えられるものではありませんが、文化人類学は、様々な問題が少しずつ解決に向かい、より良い社会を目指すことに、多少なりとも貢献できると思っています。
私が伝えたいのは「世界は驚くほど多様である」ということ、そして「日本文化や自分自身を知ることの大切さ」です。異文化を知ることで自分たちの文化を客観的に見つめ直すこともできます。
文化人類学は、不要不急の学問だと思われがちですが、実際は長期的な視点で、より良い社会を作るための手がかりを与えてくれる学問です。異文化理解を通して、多様な生き方や価値観、ものの見方・考え方を学ぶことができ、私たちの暮らしに活かせるヒントとなるのです。
身近なところで言うと、エスカレーターの使い方の文化も一つの例です。エスカレーターを歩くのは高度経済成長期に生まれた「速さ=善」という価値観の名残です。「エスカレーターを歩かない」という行動は、安全性だけでなく、働き方や生き方、ひいては社会のあり方そのものを見直す契機にもなり得ると考えています。
今は、心のゆとりや豊かさを大切にする時代です。過去の効率優先の価値観から脱却し、一人ひとりが、自身の働き方や生き方を見つめ直すことで、社会のあり方も少しずつ変わっていくと信じています。
また、地域社会、企業、学校、あるいは個人でも、異文化との出会いに戸惑う人が多くいます。些細な習慣の違いからトラブルも起きています。こうした場面にこそ、「多様性を知り違いを受け止める」という文化人類学の視点が活きてくるのです。
視野を広げ、心豊かにする文化人類学とは?
ーー文化人類学はどのような学問でしょうか。
斗鬼 一言で言えば「人間を探検する学問」です。なぜなら人間こそが人類最大の謎だからです。これには自分自身も含まれます。
そして、文化人類学のもう一つの大きな特徴は、フィールドワークによる探究であることです。まずは現地に足を運び、現地に根差した生活を体験することで、相対的なものの見方や考え方が培われます。自分の常識だけで物事を判断せず、視野を広げ、世界の多様な文化を相対的に見る姿勢こそが、今の時代に必要な視点なのではないでしょうか。
例えば、ミクロネシアのヤップ島には、厳格な身分制度や男女の隔離がある社会が存在していました。家族であっても男女の住まいや食事は別で、葬儀も男女別に行われていたのです。
私たちはつい、自分たちの常識を基準に考えてしまいがちですが、こうした文化を「野蛮」「遅れている」と決めつけてはいけません。相手から見たら、日本人の文化も特異なものに映っていることでしょう。常識は世界に無数にあり、それぞれに背景や理由があるのです。
自分たちの文化や常識を「唯一の正解」と思い込むと、人生が息苦しいものになります。ですが、自分たちの常識が「世界の中の一つのあり方にすぎない」と理解していれば、もっと気楽に生きられます。私はこれを「楽生」と呼んでいます。
また、文化人類学を学ぶことは、社会に革新をもたらすことに繋がります。異文化、異民族、異質なものに対して反感、差別、攻撃をするのではなく、相手の視点から見ることで、ものの見え方が大きく変わります。「違っていて当然」という捉え方によって、違いを受け止めることができるのです。それこそが、私たちの生活にもたらす大きな意義だと考えています。
つまり文化人類学の視点は、自分の常識だけで物事を捉えず、それぞれの文化を尊重しながら共生していく社会、そして、さらなる社会成長や生きやすい社会の実現に繋がる可能性を秘めているのです。

▲香港でのフィールドワークの様子(斗鬼さん提供)
ーー文化人類学の研究を進められる中で、ご自身の中で変化を感じることはありましたか?
斗鬼 ヤップ島の人たちとの出会いは私にとって非常に大きな経験でした。人間はここまで多様なのかと驚かされる一方で、文化の違いの奥にある共通点にも気づかされました。やり方が違うだけで本質は同じなのです。
例えば、「裸は恥ずかしい」というのは私たちにとっては当たり前のことです。しかし民族によって、体のどの部分を見せることが恥ずかしいと感じるかは異なります。
アマゾンのゾエ人は、私たちから見れば男女ともに全裸ですが、彼らは口元に穴を開け、木の棒を挿しています。この装飾がないことこそが「恥ずかしい」のです。彼らが装飾していない日本人を見たら「あの人たちは恥ずかしい」と思うことでしょう。
このように、「どこをどの程度、隠すか」は文化によって異なります。しかしその根底には、「生まれたままの姿が恥ずかしい」という共通認識が存在しているのです。
また、食文化や食べ方も国によって違いがありますが、「動物のような食べ方を避ける」という点は共通しています。これも、人類共通の認識といえるでしょう。
ではなぜ文化の違いが生まれるのでしょうか。それは自分たちのアイデンティティを明確にするためです。「あの人たちは、私たちと体の隠す部分や食べ方が違う。だから違う民族だ」というように、文化には自分たちのアイデンティティを形づくる重要な意味があるのです。
長年研究している香港や韓国は、日本と文化的に似ている部分も多いですが、自己主張の強さや個人の尊重という点では、明確に異なります。似たようで異なる文化と出会うことで、逆に日本人や日本文化の特徴が鮮明に見えてきます。
また、ニュージーランドでは、13年間、毎年同じ家庭に数週間滞在しています。彼らの生き方や人生観は日本人と大きく異なり、「残業などせず、家族そろって食事する」といった心の豊かさを大切にする暮らしが印象的でした。彼らとの交流を通して、私自身も自分の生き方についても深く考えるようになりました。私はもともと結婚するつもりはなかったのですが、ニュージーランドの夫婦の在り方を見て、「結婚もいいものだな」と感じ、結婚を決意するきっかけにもなりました。
多文化社会とどう向き合い、どう生きるべきか?
ーー斗鬼さんが提案されている「しなやかにしたたかに」生きるとは、どのようなことでしょうか?
斗鬼 「しなやかに」とは、自分と異なる価値観や常識を柔軟に受け入れる姿勢です。常識は決して絶対的なものではなく、違いとして受け止めることで、異なる人々との共存・共生が可能になります。
「したたかに」とは、異文化の人との出会いを創造性へと繋げていくということです。異質なものとの接点によって人は刺激を受け、新しいアイデアや価値を生み出せるのです。
日本はかつて大量生産、大量消費によって経済大国へと大きく成長しましたが、今は「いかに違いを生み出すか」が問われる時代です。これまでのやり方を踏襲するのではなく、異質との出会いこそが、これからの日本の成長に欠かせない要素になるのではないでしょうか。
ーー多文化社会が進む中で、私たちが大切にすべき点は何でしょうか?
斗鬼 まずは、現地に足を運び、様々な文化に直接触れることです。日本国内でもかまいません。身近な異文化や異なる民族との出会いを大切にし、それを柔軟に受け入れましょう。
地下鉄やバスに乗ったり、スーパーに行ったりして、現地の人々の生活に触れてみてください。多くの人と出会うことで、新たな発見や気づきがきっと生まれます。異文化に出会ったときに、「変だね」で終わらせず、深く理解しようとする姿勢が大切です。
同時に、日本の文化史を知ることも重要です。日本の文化は「独特だ」と言われることもありますが、実際にはどの文化も他の文化からの影響を受けています。日本の伝統文化だと思われているものの中にも、実は海外の影響を受けているものは少なくありません。逆に、ヨーロッパの印象派が日本美術の影響を受けたように、新たな文化は異文化との出会いで生まれてきたのです。
そして日本は、清潔さやマナーは高く評価されていますが、これは昔からあったものではなく、近年になって築かれたものです。世界や歴史、背景を知ることはとても大切です。
文化は比較することではじめて見えてきます。自分たちの文化は当たり前すぎて認識しにくいですが、歌舞伎や茶道のような特別な文化だけでなく、私たちの生活そのもの、身近なこと全てが文化なのです。
常識にとらわれない 多様性を尊重し共存する社会へ

▲斗鬼さん講演会の様子(斗鬼さん提供)
ーー講演会では、どのようなメッセージを伝えていきたいですか。
斗鬼 まずは文化人類学の面白さを知っていただきたいです。そして、文化人類学は物事を根本から徹底的に考えていく学問であることも知っていただき、文化人類学的なものの見方や考え方を少しずつ身につけていただけたら嬉しいです。
もう一つは、「人間って面白い存在だ」と感じていただくこと、これが文化人類学への入口になればと願っています。
私が目指しているのは、「多様性を理解し、共に生きる社会の実現」です。分断や対立、差別のない、創造性に溢れ、心豊かで誰もが生きやすい社会を目指す上で、文化人類学がその一助となることを伝えていきたいです。
ーーでは最後に斗鬼さんの「夢」と題して、今後の展望をお聞かせください。
斗鬼 人間は本当に多様で面白い存在です。人類最大の謎は人間であり、社会であり、そして自分自身でもあります。文化人類学は、そんな人間を探検する学問なのです。
人口減少が進み、多文化社会にならざるを得ない状況の中で、いかに「しなやかに、したたかに」生きていくかという点で、文化人類学はとても役に立ちます。
異文化や異なる人々との出会いは、時に困難を伴います。しかし、その背景には社会構造や文化の仕組みがあり、それを理解することで、対立や誤解といったマイナス面を小さくすることができます。
そして、人間は皆同じだと刺激がありません。異質と出会うことによって刺激され、創造力が生まれ、革新を続けることができるのです。世界にある様々な文化、生き方、価値観と出会い、刺激を受け、そこからヒントを得て、クリエイティブな新しい社会を作っていくことが非常に重要だと考えています。
「多様であっていい」「身近な常識にとらわれず、世界は広い」と知ることで、もっと心豊かに楽に生きられる「楽生」な社会になればと思っています。そのためにお役に立てれば嬉しいです。
ーー文化人類学の視点を持つことで、コミュニケーション齟齬や価値観のズレからくるすれ違いなど日常の中にある様々な問題の解決、そして私たちが生きやすい社会に繋がるという可能性を感じさせていただきました。貴重なお話をありがとうございました。
斗鬼正一 ときまさかず
文化人類学者 江戸川大学名誉教授 元明治大学大学院・文学部兼任講師
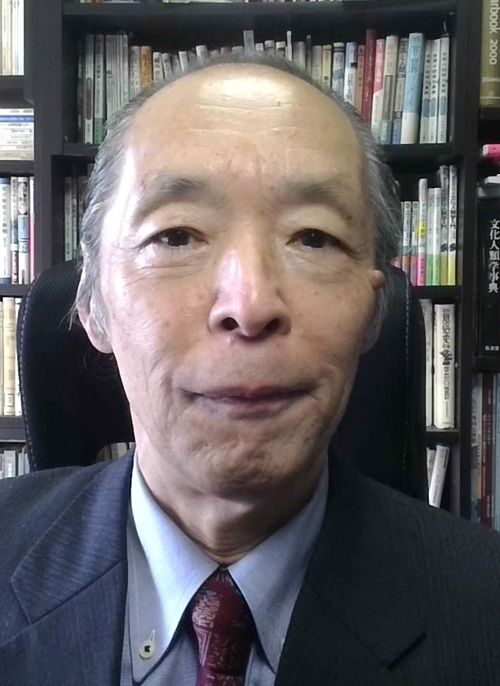
国内外現地生活密着型フィールドワークで「人間」を探求する文化人類学の第一人者。講演では“多文化社会を「しなやかにしたたかに」生き抜く知恵やコツ”を説く。メディアでは衣食住、身体、マナー、エスカレーターなどに関する文化を解説。著書『目からウロコの文化人類学入門』他、多数。
プランタイトル
迫り来る多文化社会をしなやかに・したたかに生きよう
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されましたあわせて読みたい
ADHDの診断を受け、すべてを失いかけても何度でも立ち上がり、…
FIRE達成や世界一周といった華やかな実績の裏に、自己否定や貧…
現代社会にとって、多様性は重要なテーマの1つです。多様性社会を…
他の記事をみる







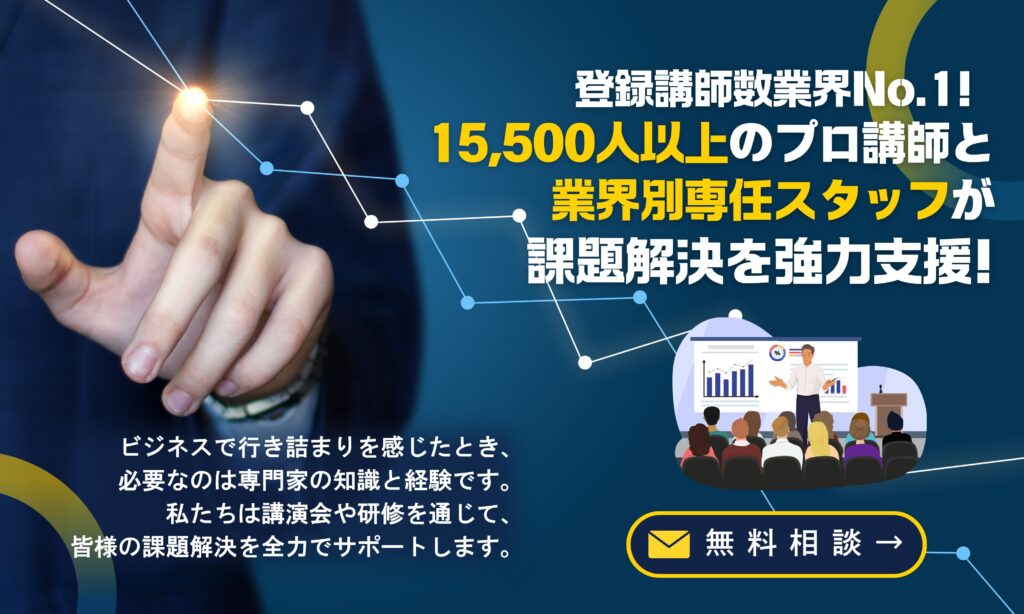











業務外の講師への取次は対応しておりません。