
 現代社会にとって、多様性は重要なテーマの1つです。多様性社会をいかに実現していくか―。今回ご紹介するアートプロデューサーの栗栖良依(くりす よしえ)さんは、この問題に1つの答えを示しています。
現代社会にとって、多様性は重要なテーマの1つです。多様性社会をいかに実現していくか―。今回ご紹介するアートプロデューサーの栗栖良依(くりす よしえ)さんは、この問題に1つの答えを示しています。
がんによる命の危機を乗り越えて、東京2020パラリンピック開閉会式のステージアドバイザーという夢を叶えた栗栖さん。多様な人々をつなぐ活動を続けてきたその軌跡と、多様性の持つ力についてお聞きしました。
「作りたい舞台はこれだ」16歳で抱いたオリンピックの夢

▲1998年長野オリンピックにボランティアとして参加された際の栗栖さん。選手村の式典交流班として携わった
――栗栖さんはオリンピック開会式を演出するという夢を抱いてアートの道に進まれたそうですが、なぜオリンピック開会式を演出したいと考えたのですか?
栗栖 オリンピックの夢を抱いたのは高校生の頃です。卒業後は舞台や表現の世界を学びたいと考えたものの、様々なエンターテイメントの世界がある中でどんな方向に進むべきか迷っていました。そんな時、偶然リレハンメルオリンピックの開会式(1994年)を見て、「私が作りたい舞台はこれだ」と思ったんです。
私は幼少期から身体表現をしてきて、中学・高校では舞台作品も作ってきましたが、プロの役者やダンサーが作る舞台にはあまり興味がありませんでした。私が惹かれたのは、名もなき市民にハレの場を作るような、市民参加型の舞台だったんです。
オリンピックの舞台は、地域の子どもからお年寄りまで、様々な人々が出演します。平和活動に興味があったこともあり、自分の創りたい世界観にとてもマッチしていると感じました。
オリンピックは数百人規模の大スケールで作る舞台であり、その演出手法は仕組みをデザインすることに近いものです。オリンピックのように社会と芸術を横断的につなぐスケールの大きな手法を学ぶため、東京造形大学でアートマネジメントを学び、卒業後はイタリアのドムス・アカデミーのビジネスデザイン専攻に留学しました。
180度変わった人生観。命の危機で絶たれた夢と新たな夢
▲栗栖さんが代表を務める認定NPO法人スローレーベルで実施された市民参加型プロジェクトの様子。2011年の設立以降、障がいの有無に関わらず誰もが参加できる様々なプロジェクトに取り組んでいる(引用:SLOW LABEL公式youtubeチャンネルより)
――夢に向けて進んでいる最中に骨軟部腫瘍(がん)により右下肢機能を全廃されていますが、闘病中のお気持ちはいかがでしたか?
栗栖 骨軟部腫瘍を患ったのは、イタリアから帰国して数年後の32歳の時です。病気の進行が早く、命に関わるほどの病状でした。当時は東京オリンピックの開催も決まっていない状況です。そんな挑戦できるかも分からない夢のために命を落とすわけにはいかないと、そこで一度夢を捨てました。
幾度もの抗がん剤治療と手術を経て社会復帰できるまでになりましたが、5年生存率はまだ低い状況です。来年生きているかも分からない状況で、夢を追いかけようとは思えませんでした。
そこで人生観や価値観が180度変わったんです。それまではオリンピックの夢のために逆算して、1分1秒も無駄にしない生き方をしていました。しかし来年生きているかも分からない状況になったことで、今、この瞬間をいかに楽しむかを考えるようになったんです。
――その状況から、なぜパラリンピックを目指すことになったのですか?
栗栖 社会復帰後すぐに、障がいのある人とアーティストが共にものづくりをするプロジェクトのディレクターを依頼されたんです。このプロジェクトは現在代表を務める認定NPO法人スローレーベルの発足にも繋がり、私が障がいのある人とのプロジェクトを多く手掛けていくきっかけになりました。
そのプロジェクトから1年後に、ロンドンオリンピック・パラリンピックが開催されました。私が障がい者となってはじめての大会でしたし、障がいのある人たちとのプロジェクトの経験からパラリンピックに注目して見たのですが、開会式が非常に良くて。
ちょうど1年生き延びたことで生存率も上がり、「もう少し生きられるかもしれない」と思っていたこともあり、パラリンピックの開会式へと夢を上書きすることにしました。
積み上げた計画と努力で掴んだ夢のパラリンピックの舞台

▲Cap/東京2020パラリンピックでの栗栖さん。パラリンピック開閉会式ではステージアドバイザーを、オリンピック開閉会式ではD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)チーフプロデューサーを務めた
――パラリンピックの夢に向けて、どのような取り組みをされましたか?
栗栖 開会式を想定して、障がいのある人たちとパフォーマンスを作る活動をするためにワークショップやフェスティバルを立ち上げました。しかし実際に活動を始めてみると、日本にはパラリンピック開会式ができるインフラも整っておらず、出演できるプレイヤーもほとんどいないことが分かったんです。
その頃には東京オリンピック開催が決まっていましたが、このままでは日本でパラリンピックは開催できないと思いました。そこで人材発掘や育成、インフラ整備など、パラリンピックに必要な準備を始めたんです。
活動を通して分かったのは、ワークショップを計画しても障がいのある方がアクセスできないということです。会場に向かうまでのサポートができるヘルパーを手配できないといった物理的バリアや、「迷惑をかけるかもしれない」といった心理的バリアがアクセスを妨げていたのです。
そこで取り組んだのが、アクセスコーディネーター※1とアカンパニスト※2というケア人材の育成でした。その結果、障がいのある方々が少しずつワークショップに参加してくれるようになったのです。
そうした仕組み作りをしながら、パラリンピックの開会式を想定したパフォーマンスを何度も行い、組織委員会や東京都などへのロビー活動も続けていきました。
そうした活動が注目され、リオオリンピックの際には旗引き継ぎ式のアドバイザーを依頼されました。それらの実績が、東京オリンピック・パラリンピックの参加に繋がっていったのです。
※1:障がいのある人が参加するための環境を整える者のこと。バリアフリーなどの情報を個別に提供したり、現場での参加者の体調や精神面のケアを行う。
※2:障がいのある人と共に創作活動を行う伴奏者のこと。創作の際に発生する困難を、同じ創作者の立場で寄り添い、乗り越える手助けをする。
――パラリンピックの演出を担当できるという確約もない中で、そこまで大掛かりな取り組みをすることに対し不安はありませんでしたか?
栗栖 私は仕組み作りをずっとやってきているので、大きなビジョンを描いたり行政などに働きかけて制度を作ったりすることが得意なんです。
ただ、担当できるかも分からない机上の空論に、仲間たちは本当によくついてきてくれたと思います。昔であれば、オリンピックの演出なんて大きな夢を叶えられるとは、誰も信じなかったでしょう。しかし、少しずつ実績を作り上げてきたことで、「本当にやるんだ」と思ってくれるようになったのだと思います。
――実際にオリンピック・パラリンピック開閉会式演出という夢を叶えた瞬間は、どのような感情が湧きましたか?
栗栖 「終わった」や「できた」といった感情はありませんでした。夢が叶ったというよりも、まだ道半ばという感覚だったんです。それは、「やり切れた」と思う一方で「まだできた」と思う部分もあったからだと思います。
パラリンピックに関しては、2021年時点で出せる100%のものを出し切れたと思っています。しかしオリンピックに関しては立場的に妥協せざるを得なかった点が多く、とても心残りがあったのです。もし札幌オリンピックが実現したなら、もう一度参加したいと思うほどでした。
人は一人ひとり違う。個性の掛け合いが可能性を切り拓く

▲Cap/栗栖さんの講演会の様子。自治体や企業、学校など、様々な場で講演会を行っている
――講演会ではどのようなお話をされていますか?
栗栖 講演会では、私が実践してきた活動事例をもとに、多様性を力に変える面白さをお伝えしています。ご依頼いただいた企業・組織の形態や状況、ご希望を事前にしっかりとヒアリングした上で講演内容や講演形式を毎回カスタマイズしているため、同じ講演会は二度とありません。
講演会の中でも私が特にお伝えしているのは、マジョリティの中にある生きづらさの解消です。私は講演会でいつも「生きづらさを抱えているのは誰ですか?」と聞いています。生きづらい人=マイノリティと思われがちですが、最近は特にマジョリティの方が生きづらさを抱えていると私は感じています。
まずマジョリティの生きづらさを解消しなければ、そのコミュニティの中にマイノリティが入ってもお互いに不幸になるだけです。だからこそ私は、みんな違う個性を持った人間同士だということを理解し、個性を出し合って力に変えていくチーム作りを推奨しています。誰しも得意不得意があるのは当たり前のことです。その個性をチーム内でどう組み合わせて成果を出していくのかが重要なのです。
多様性やダイバーシティの話というと身構えてしまう方も多いですが、気楽な気持ちで聞いていただきたいです。
――栗栖さんは、どのような形で多様性社会が実現されることが理想だとお考えですか?
栗栖 日本では多様性と言うとマイノリティを受け入れるスタンスがイメージされることが多いですが、それでは対立が生まれたり、忌避されたりしてしまいます。私が考える多様性社会とは、障がいの有無や国籍、思想に関係なく、一人ひとりの個性や違いを認め合い、生きづらさを解消することです。
「一人ひとり違う」ということを受け入れ、その違いを組み合わせることで力に変えていき、みんなが居心地のいい調和の取れた環境へと変えていく。そのためにどうすべきかを考えることが、多様性を受け入れるということだと私は考えています。
――栗栖さんの考える「個性」とは、どのようなものなのでしょうか?
栗栖 個性と言われると特別な感性を持っているように思われがちですが、「みんな違う」ということが個性だと思っています。
個性において日本で見過ごされがちなポイントは、目に見えない部分だと考えています。特に日本は肌の色や髪色などの見た目が同質の人が多いため、「みんなも自分と同じ意見を持っている」と思い込んでしまう傾向があると思います。
しかし実際には、人は一人ひとり感じ方も考えていることも異なります。多くの方に「あなたの普通は隣の人の普通ではない」ということに、まずは気付いていただきたいです。
――最後に、栗栖さんの夢をお聞かせください。
栗栖 私の夢は多様性の面白さをもっと多くの人に実感してもらうことです。多様な人達と活動していると、自分では思いつかないようなアイデアに出会うことがあります。それは本当にワクワクする瞬間です。
多様性やダイバーシティ、インクルージョンと言うと、「配慮が必要なもの」「義務」のようなイメージを持って構えてしまう方も少なくありません。しかし私は、多様性は自分の世界を広げて組織の閉塞感を無くし、新しい可能性を拓くものだと考えています。そのワクワク感を色々な企業や教育現場、地域コミュニティの方々に広げていきたいです。
――貴重なお話をありがとうございました!
栗栖良依 かくりすよしえ
アーティスト アートプロデューサー
東京2020パラリンピック開会式ステージアドバイザー( DEI 監修)

イタリア・ドムスアカデミービジネスデザイン修士取得。その後、骨軟部腫瘍で右下肢機能を全廃。闘病・再起を経て【誰もが文化芸術参画可能な仕組みと環境づくり】に取り組む。東京パラリンピック開会式の演出にも携わる。また日本初のソーシャルサーカス普及団体設立など、多様性と共創社会実現に奔走中。
|
講師ジャンル
|
文化・教養 | 文化・教養 |
|---|
プランタイトル
多様性を力に変えるチームへ
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されましたあわせて読みたい
ADHDの診断を受け、すべてを失いかけても何度でも立ち上がり、…
FIRE達成や世界一周といった華やかな実績の裏に、自己否定や貧…
現代社会にとって、多様性は重要なテーマの1つです。多様性社会を…
他の記事をみる







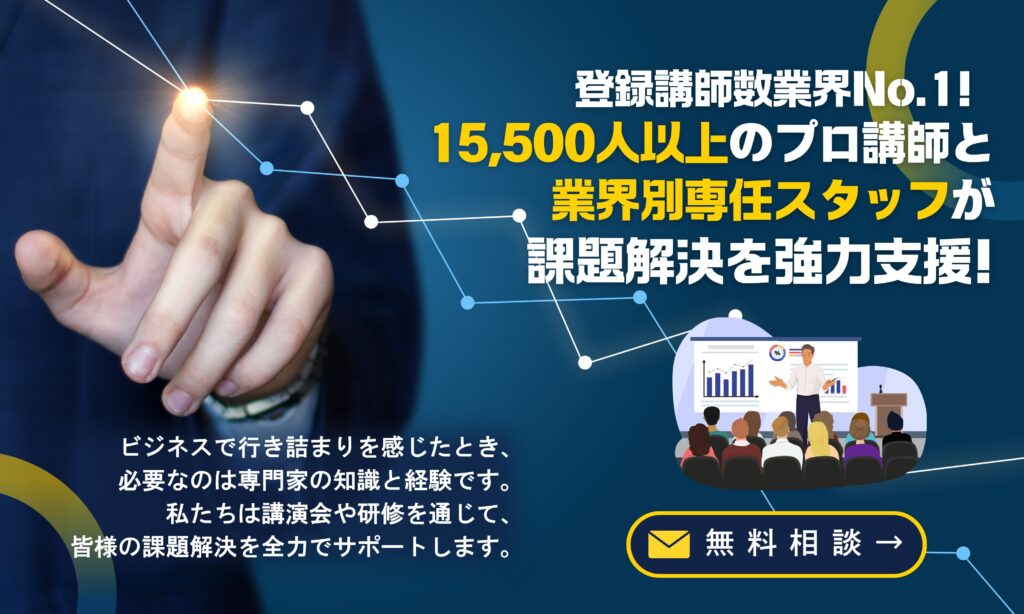











業務外の講師への取次は対応しておりません。