想定する対象者
パワハラ・セクハラ・マタハラなどハラスメント対策を実施している(実施検討している)企業。管理職など役職者、経営者、人事総務コンプライアンス部門担当者、一般社員などが想定受講者です。
法的なリスクや労務面は講師の専門ではなく、そもそもハラスメントを未然に防ぐために何が必要かを解説するのが講師の強みです。
提供する価値・伝えたい事
ハラスメント対策を実施するほど、どこまでがハラスメントかグレーゾーンの線引きに悩んでしまったり、適切な指導が行えなくなる弊害があります。またハラスメントに気を取られ、役職者がメンタル不調を引き起こしてしまうことがあります。これは本末転倒です。
そこで本講演では、ハラスメントを未然に防ぐ2つのポイントを、メンタルヘルスとコミュニケーションの領域から解説します。難しい専門用語は一切使わず、実際の現場においてすぐに活かせる内容を、主に心理学のアプローチでお伝えします。
ハラスメント・メンタルヘルス・コミュニケーションと、異なる3領域の内容を一度に扱うことができます。
内 容
以下の順で講演を進めますが、クライアント様の置かれた状況やニーズや所要時間等も踏まえ、内容を修正します。
1、ハラスメントの基礎知識
・代表的なハラスメントと詳細な分類(パワハラ・セクハラ・マタハラ)
・これはハラスメント?ハラスメントで誤解されがちなこと
・ハラスメント対策の弊害
2、ハラスメントを未然に防ぐ2つのポイント
・ポイント1:役職者自身が自分のメンタルを整えることができているか(セルフケア力)
・ポイント2:従業員と信頼関係を築けているか(コミュニケーション)
・ハラスメントとメンタルヘルスの相互関連性
3、ポイント1:役職者が自分のメンタルを整える方法
・メンタル不調を理解する鍵となる「心の便秘」とは?
・セルフケア力を高めるうえで重要な「解消と解決」の違い
・自力でメンタルを整える3ステップ
4、ポイント2:従業員と信頼関係を築きハラスメントを未然に防ぐ方法
・ハラスメントの本質は人間関係
・ハラスメントを未然に防ぐための「課題の分離」の考え方
・ハラスメントに配慮しながら従業員と関わるうえで効果的な3つの方法
・ハラスメント発生時の対応
5、まとめ
根拠・関連する活動歴
これまで職種や階層を問わず7,000名以上のメンタル支援を行なってきた実績があります。また、既刊の著書2冊『ストレスフリー人間関係』『声に出すだけでモヤモヤがスッキリする本〜たった5秒のメンタルケア』を通して、理論を広く周知しており、増刷を果たすなど多くの方に手に取っていただいております。
ハラスメントやメンタルヘルス対策の講演会・研修を企業で実施した実績があります。
最近ではテレビ・ラジオ等のメディア出演を通して、理論を知っていただく機会を精力的に作っています。2025年5月27日には静岡放送SBSラジオの朝の情報番組「IPPO」にて、企業のカスハラ対策やカスハラを受けた人のメンタルケアをサポートしている専門家として招かれ、約10分のゲスト出演をしました。








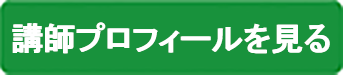


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました













業務外の講師への取次は対応しておりません。