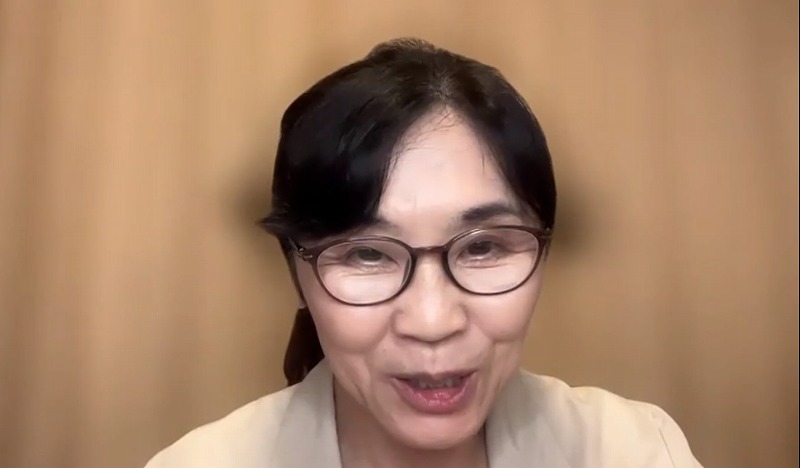
一般社団法人 日本医療安全調査機構が発表した2024年の年次報告書によれば、2023年の医療事故に関する相談件数は累計15,287件、医療事故報告件数は2,909件に上り、いずれも年々増加傾向にあります。社会全体のコンプライアンス意識が高まる中、患者や家族の苦情・クレーム対応は、これまで以上に迅速かつ誠実な姿勢が求められています。
とくに医療現場においては、単なるミスの説明だけでは納得が得られず、「感情」への対応力が信頼関係を左右する重要な要素となっています。
今回の講演では、大学病院の安全管理部長として医療事故対応に携わり、現場で患者や遺族との対話を重ねてきた永井弥生さんが、「医療メディエーション(対話)」の視点から、クレームや紛争の予防と対応、信頼回復の方法について実践的に語りました。本記事ではその講演の模様をレポートします。
官公庁・学校・PTAチーム
講師 : 永井弥生 氏
開催時期 : 2025年6月下旬
主催者 : Y看護学会
講演時間 : 90分
聴講者人数: 約200人
講演タイプ: オンライン開催
約200名の看護師が参加したオンライン講演会
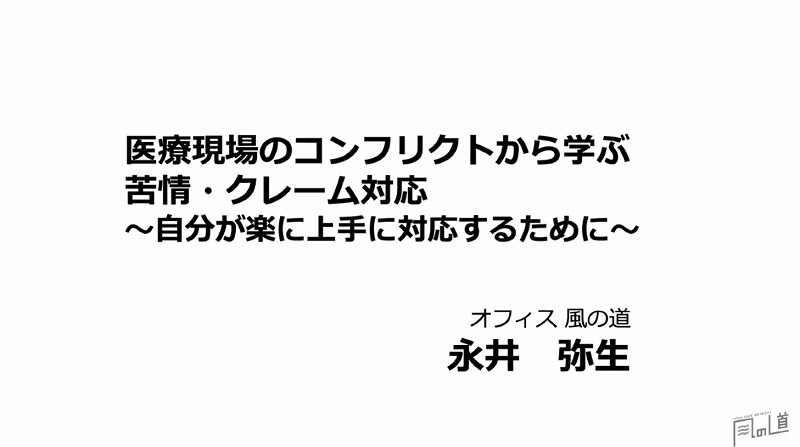 今回の講演は、Y看護協会が主催したオンライン研修会として実施され、病院の主任看護師から「クレーム対応に悩む」若手看護師まで約200名が参加しました。
今回の講演は、Y看護協会が主催したオンライン研修会として実施され、病院の主任看護師から「クレーム対応に悩む」若手看護師まで約200名が参加しました。
日頃から患者や家族とのコミュニケーションに悩みを抱える参加者にとって、「現場で使える対話のスキルを学びたい」「医療事故時の適切な対応方法を知りたい」といったニーズは非常に高く、講師には医療現場で多くの実績を持つ永井弥生さんが指名されました。
永井さんは、現場で経験した大規模医療事故の対応から、医療メディエーションを導入した経緯、患者と医療者をつなぐ第三者の役割、そして、実際の対話を通じて信頼関係を再構築していく過程を、具体的なエピソードと動画資料を交えて解説されました。
医療現場コンフリクトとは?――事故の現実と対話の必要性

▲イメージ画像
永井さんが「医療メディエーションの必要性」を実感したのは、腹腔鏡手術に関する医療事故がきっかけでした。4年間で8名が亡くなり、最後の一人が亡くなった時、永井さんは安全管理部長として遺族対応の責任を担っていました。
報道が先行し、遺族が病院から真相を知らされる前に新聞記事で知るという事態が発生。病院は連日、新聞で批判を浴び、内部でも緊張が走りました。永井さんは「このとき初めて、医療者と患者・遺族の間で、感情と事実の溝がどれほど深いのかを痛感した」と振り返ります。
その後、第三者委員会を設置して1年半かけて真相を究明しながらも、永井さんは日々多くの苦情・問い合わせに対応しました。「感情を放置すれば、たとえ説明が正しくても、納得は生まれない。だからこそ“対話”が必要なんです」と語る永井さんの言葉は、深い説得力をもって受講者に届いていました。
“いる”と“いない”でどう違う?実例から見る対話の変化~医療メディエーションの役割
講演では、看護師による点滴薬の誤投与という実際に起こり得る医療事故をもとにした再現動画が紹介されました。
手術を一週間前に控えセンシティブになっている患者に看護師が点滴を投与しますが、点滴が半分になったところで点滴名に自分の名前が書いてないことに患者自身が気づき、看護師に指摘。その後、看護師と医者が患者に状況を説明するというシーンから始まります。
「医療メディエーターがいない場合」と「いる場合」の2つのパターンで、患者・看護師・医師のやりとりの違いが比較され、その効果が鮮明に浮き彫りになりました。
パターン1:医療メディエーター不在の対話

▲イメージ画像
患者は、誤って他人の抗生剤を投与されたことに激しく怒りを表します。
看護師 「ごめんなさい、二度とこのようなことが起こらないようにします」
患者 「謝ってすむ問題じゃない。注射する前にしっかりとチェックしてなかった。他の看護婦とぺちゃくちゃしゃべりながらやっていて、名前を確認してなかったじゃないか。」
看護婦「ぺちゃくちゃおしゃべりしたのではありません。他の看護師に用事を頼まれて…」
患者「言い訳ばかりして、謝る気がないのか。」
医師が副作用の少なさを説明しても、患者は納得せず、ますます感情的になっていきます。
医師:「今回の薬は副作用がほとんどない抗生物質で、心配はありません」
患者:「そんなことが聞きたいんじゃない!他人の薬が自分の体に入ったことが問題なんだ」
このやりとりでは、患者の「怒り」の裏にある「不安」や「恐れ」が放置されたままで、信頼関係が完全に崩れていきます。
パターン2:医療メディエーターが介入した場合

▲イメージ画像
同じ事例で、医療メディエーターが間に入りました。まずは患者の想いに耳を傾け、話す許可を得たうえで、医療者の説明へと進行。謝罪の言葉を丁寧に繰り返し、患者の不安を受け止めることで、感情が次第に和らぎ、最終的に「この病院で手術を受けてもよい」と患者が納得するまでに至ります。
この対比を通して、医療メディエーターの役割として以下が紹介されました。
① 共感がわかる会話
メディエーター「○○さん(患者)、本当に驚かれたと思います。“体に他人の薬が入った”と聞いて、不安にならない人はいませんよね」
患者(少し表情を和らげながら)「そうなんです。すごく怖くて……」
このように、患者の発言に寄り添う言葉が添えられることで、「怒り」ではなく「不安」を言葉にする流れが生まれていきます。
② 共感した上で、医師の説明の許可を得る場面
医療メディエーターが、「他の人の薬が入って、どんな症状があったか」を患者にきくと、患者は、具体的な症状は言わないが、体のだるさを訴えます。
メディエーター「点滴の接種後に体のだるさがあったということですね。それでは、副作用について、医師から詳しくお話してもらってもよろしいでしょうか?」
患者「……はい。どんな副作用があるのか、ちゃんと知りたいです」
共感した上で「話していいか」と一言患者に確認を取ることで、患者が説明を受ける準備が整い、感情の受け皿ができていることがわかります。
③ 感情の言葉を繰り返して表現するやりとり
患者「本当に不安で、眠れなかったんです」
メディエーター「“眠れないほど不安”だったのですね。それは大変でしたね」
(医師や看護師も神妙な面持ちで頷く)
この「繰り返し(パラフレーズ)」の言葉は、患者に「わかってもらえている」という実感をもたらし、信頼の回復へつながっていきます。
最終的に、医師が副作用について説明した後、メディエーターの提案で医師が血液検査を行うことになりました。
医師「これまでも〇〇さん(患者)を見てきました。これからも責任をもって経過を見ていきます」
患者「そうですね。▲▲先生にはこれまでずっと見てきてもらいました。そこまで言ってくれるのなら、ここで手術を受けてもいいと思います」
看護師「本当に申し訳ありませんでした」
患者「あんたもまだ若いですから、この経験を糧に二度と同じようなことを起こさないように、頑張ってください」
●比較して見えた、医療メディエーションの5つの役割
| ポイント | メディエーター不在 | メディエーターがいる場合 |
| 感情対応 | 怒りが噴出し、不信感が強まる | 怒りの裏にある不安に共感し、感情の整理を促す |
| 謝罪の伝え方 | 一方的な謝罪が「言い訳」と受け止められる | 患者の承認のもと、謝罪の意図が丁寧に伝わる |
| 説明のタイミング | 医師が一方的に説明し、患者の感情を無視 | メディエーターが許可を得てから丁寧に橋渡し |
| 会話の進行 | 感情と事実が交錯し、混乱 | 感情→背景→事実→提案と段階的に整理される |
| 信頼関係 | 対立し、病院を去ると発言 | 納得が生まれ、治療継続を自ら選択する |
コンフリクト時の対話のポイント

▲イメージ画像
その1:傾聴・共感・承認
相手の話を「聴く」ことは、最も重要な初期対応です。永井さんは、特に以下の要素を強調しました。
- 非言語の共感:姿勢・視線・うなずきなどで「聴いている」ことを伝える
- パラフレージング:患者の言葉を繰り返して受け止める
- 承認の姿勢:否定せず、いったんそのまま認める
- 責任承認と共感表明:たとえ故意でなくても、結果に対して責任をもって謝罪する姿勢
その2:本当の思いとは何か?
医療の現場で表出される怒りやクレームの多くは、実は「二次的な感情」としての怒りです。つまり、怒りの根底には、「不安」「悲しみ」「孤独感」「理解されていないという思い」など、より根源的な感情が潜んでいます。
永井さんは講演の中で、「怒っている人にどう向き合うかではなく、その人が本当は何に傷ついているのかに目を向けることが、対話の出発点だ」と語りました。
誤投与の事例でも、患者が繰り返し「他人の薬が自分の体に入った」ことを訴えていたのは、怒りではなく、「命に関わるかもしれない」という切実な不安の裏返しでした。
メディエーター「“他人の薬が体に入った”という事実が、○○さんにとってどれほどの不安だったか…それを一番に受け止めたいと思います」
こうした言葉を織り交ぜながら対話を進めていくことで、患者自身も少しずつ自らの感情を言葉にしていきます。
患者「……病院に不満があるんじゃなくて、怖かったんです。何が起きるか、わからなかったから」
このように、「病院を変えたい」「賠償してもらう」という言葉の裏にある“本当の思い”を引き出すには、怒りに圧倒されるのではなく、その背景に耳を傾けることが不可欠です。
ただし、怒りに対して必要以上に深く関わりすぎると、医療者自身の心が疲弊してしまう恐れもあります。永井さんは、「共感して受け止めたら、スッと引く」「抱え込まずに共有する」ことの大切さも併せて伝えられました。
怒りをそのまま受け止めるのではなく、「何がその怒りを生んだのか?」という問いを持つこと。 それが、感情を整理し、建設的な対話へと導く第一歩なのです。
感情の受け止め方に悩む看護師の声に応える
講演の後半では、組織としての体制の整え方や不合理な要求への対応の仕方、コンフリクト・マネジメント、セルフメディエーション、アンガーマネージメントのやり方など、組織、個人としての対応についても具体的事例を出して解説されました。
講演後の質疑応答には、多くの実務的な質問が寄せられ、時間が足りないほどでした。
受講者の現場感覚に即した回答はどれも丁寧で、実践の手がかりになるものばかりでした。
信頼を取り戻す「対話」という選択肢
講演はオンラインにも関わらず非常に多くの反響があり、終了後のアンケートでも満足度の高さが際立っていました。受講者からは、「すぐに現場で使える内容だった」「動画での比較がとても分かりやすかった」「自分の感情整理にも役立った」といった感想が寄せられています。
永井さんの講演は、「対話の力」がいかに人と組織の信頼を再構築できるかを体感させてくれる内容です。医療現場だけでなく、福祉・介護・教育・行政など、あらゆる対人支援の現場にとって有用な講演といえるでしょう。
苦情対応やクレーム処理が「ストレス」ではなく、「信頼構築のチャンス」となるために――。永井さんの講演を通じて、その第一歩を学んでみてはいかがでしょうか。
永井弥生 ながいやよい
医療コンフリクトマネージャー 医学博士、皮膚科専門医、産業医

医療紛争時の対話をつなぐ第一人者として活動。群馬大学病院の医療安全管理部長として同院の医療事故に気づき指摘、その後の対応に一貫して取り組んだ。類を見ない医療事故に対応した講演は、医療のリスクを実感するために役立つ。医療対話、コンフリクトマネジメントを学ぶ実践セミナーも好評。
|
講師ジャンル
|
実務知識 | 危機管理・コンプライアンス・CSR | 医療・福祉実務 |
|---|---|---|---|
| 人材・組織マネジメント |
プランタイトル
医療のコンフリクトから学ぶ苦情・クレーム・紛争対応
~自分が楽に上手に対応するコツ~
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されましたあわせて読みたい
厳しい残暑が続く中、全国各地で開催された夏の人権啓発・人権教育…
「きょうの健康」で人気の 久田直子さん 寒い季節。自然に体が縮…
先日、森透匡さんのオンライン講演の運営を担当させていただきまし…
他の記事をみる



















業務外の講師への取次は対応しておりません。