想定する対象者
地域で孤立・無関心・不参加が増加している高齢者。
退職後や家族の喪失などで、社会との接点が薄れがちな中高年層。
地域包括支援センター・福祉課・民生委員。社会福祉協議会など支援側にも有益。
提供する価値・伝えたい事
定年後や身近な人との別れをきっかけに、外に出るのが億劫になり、人と関わることが「怖い」「面倒」と感じてしまう人は少なくありません。孤立の背景には「心の疲れ」や「つながりの喪失」が潜んでいます。この講演では、「誰かと笑い合う時間」こそが、孤立を防ぐ大切な入り口であることをお伝えします。
無理に人と関わるのではなく、まずは“心の準備運動”から。誰かの役に立とうとする前に、「誰かと笑う」ことから始める——そんな、やさしくて自然な第一歩を後押しします。「ああ、私もまだ笑える」「まだ大丈夫だ」と感じてもらえる時間を通して、孤立や引きこもりの予防に前向きな光を届けます。
内 容
(1)「孤立している人、あなたの周りにいませんか?」
– 主語を“自分”ではなく“身近な誰か”に設定する導入 –
・身近な人に起こる、気づきにくい孤立の兆し
・「孤立の正体」は“関係の喪失”であり、誰にでも起こること
・本人の意志ではなく、環境やタイミングで起こる現実
(2)自分を諦めた瞬間、老いは加速する
– 閉じこもる心理とその背景 –
・「迷惑をかけたくない」が孤立を進める
・高齢者が避ける典型的なパターンと心の壁
・なぜ“助けて”が言いづらいのか
(3)「会話」は心の筋トレ
– 心と脳をゆるめる科学と感情のスイッチ –
・誰かに会う、笑い合うだけで脳とホルモンが変わる
・心を閉ざす前に交わしたい“一言”の力
・ペアワーク:最近笑ったこと・話した誰かを思い出す
(4)「もう一度会いたい人」を思い出すワーク
– 過去のつながりが、これからの行動のヒントに –
・会いたい人、話したい人を紙に書き出してみる
・「何を話そう?」が“行動の設計図”になる
・行きたい場所、やりたいことも具体化してみる
(5)人と関わることで、自分の中が満たされる
– 誰かの役に立つ前に、「誰かと笑う」が最初の一歩 –
・役割意識よりも、“関係”が人を元気にする
・「私はまだ笑える」「大丈夫」と思えたら、もう次の一歩
・最後に:孤立を防ぐのは「小さな会話」と「たまの笑い」
参加者層にあわせて、
自分の中に“人と関わってもいいかもしれない”という意欲が生まれる
外出や交流機会への第一歩を後押しされる
孤立予防だけでなく、QOL(生活の質)の向上にもつながる
が得られる内容にカスタマイズいたします。
根拠・関連する活動歴
福祉専門職としての生活支援・ケアマネ・家族支援の豊富な経験
生活支援・地域包括支援、男女共同参画の第一線での支援実績多数
心理学(NLP・行動科学、コーチング)を活かした非対立的・共感的語り口が好評
社会福祉士のほか、福祉相談支援の専門知識と実績
シニア世代が共感しやすいエピソード、押しつけがましくない語り








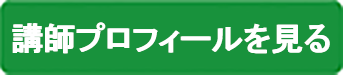


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました













業務外の講師への取次は対応しておりません。