想定する対象者
企業の人事・総務担当者(障がい者雇用・ダイバーシティ推進の実務担当)
障がい者雇用の責任者/障がい者雇用の管理職
経営層(特に「社会貢献」と「持続可能な組織づくり」を重視する層)
特例子会社/就労移行支援事業所との連携を考える企業のご担当者
提供する価値・伝えたい事
1.「法定雇用率を満たす」だけではない、障がい者雇用の経営的価値を伝えます。
・障がい者雇用は「義務」ではなく「戦力化と信頼構築の好機」。
・実例として、障がい者スタッフ20名を部下に持ち、段階的に社内理解と受け入れ体制を構築しながら、2.8%を目指して組織を動かしてきたプロセスを公開。
・採用→定着→活躍までの流れと工夫を知ることで、自社の改善ポイントが見える。
2.「成功事例」にリアルな実務視点をプラスし、明日からできるヒントを得られます
・成功体験だけでなく、壁・誤解・社内の温度差など現場のリアルを正直に共有。
・「1人目の雇用をどう乗り越えたか」「協力者をどうつくったか」「業務の切り出しをどう工夫したか」など、再現性あるノウハウを提示。
・自社でも実践できる“小さな一歩”を持ち帰れる。
3.雇用担当者の“孤独感”に寄り添い、道しるべを示します
・支援者がいない/社内の理解が得られない…そんな中でどんな手順で周囲を巻き込んできたかを具体的に解説。
・「自分ひとりで頑張らなくていい」「協力を得るにはどうすればいいか」という視点と勇気を届けます。
内 容
1. 導入:数字の裏にあるストーリー
・「2013年、私が着任した時、法定雇用率0.95%。これは厳しいと誰もが思っていました。」
・定年退職時には2.8%の見込みを達成。
・後任にバトンを渡せた“持続可能な仕組み”を残せた理由とは?
2. どこから始めたのか?【初期フェーズ】
・課題把握:社内の温度差、現場の不安、採用ルートなし
・最初に着手したこと:「社内ネゴシエーション」+「見学→理解→協力」のステップ化
3. どう広げたのか?【拡大フェーズ】
・1人目の成功が次の扉を開く。小さな成功体験を社内で共有
・仕事の切り出し×職場の理解=定着
・特別支援学校・支援機関との連携、実習と面接の工夫
4. どう継続させたのか?【定着フェーズ】
・成果を「数字」ではなく「人の成長」として捉える文化
・センター長として支援員と連携、障がい者スタッフ20名を戦力として支えるマネジメント
・「できないこと」ではなく「できる形にして任せる」発想への転換
5. 事例紹介:実際に活躍した社員のストーリー
・例:発達障がいのある社員が「広報的な業務」で花開いた話
・「広報活動」→「社内の障がい者理解を高める橋渡し」になった成功例
6. 参加ワーク:自社で最初の一歩を考える
・今、自社で“切り出せる仕事は?
・味方になってくれそうな部署はどこか?
・明日から誰と会話を始めるか?
7. まとめ:雇用から「組織の成長戦略」へ
・障がい者雇用は“支援ではなく、戦力化と信頼関係の構築である。
・社内の見る目が変わったとき、職場が変わり、会社が変わる。
・成功のカギは、「一人でやらない」仕組みと「小さな成功の積み重ね」。
根拠・関連する活動歴
障がい者雇用責任者歴約10年
障がい者雇用に関する賞を受賞
管理職経験25年・部下指導の実績多数
コーチングスクールの講師歴10年








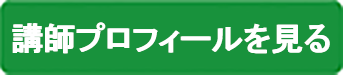


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました













業務外の講師への取次は対応しておりません。