想定する対象者
虐待件数の増加に心を痛めている人 子どもを育てているすべての人
提供する価値・伝えたい事
「秩序の敏感期」は、子どもが秩序や安定性を求める重要な発達段階であり、これを親が理解しサポートすることは、子どもの健全な育ちに寄与します。
秩序の敏感期とは? モンテッソーリ教育では、秩序の敏感期は生後6ヶ月から6歳頃に見られるとされます。この時期の子どもは、周囲の環境の秩序に敏感であり、物の配置や日常のリズムが安定していることを好みます。例えば、毎日同じ流れで食事や遊びが進むこと、物がきちんと片付けられていることなどが、子どもの安心感と自己制御能力を育てます。
内 容
導入:アイスブレーキング 「子どもにイラっとしたこと」についてのあるある
展開:虐待件数の増加グラフを見ながら、原因についての考察
解決策:
親がこの敏感期を理解し、適切に子どもをサポートすれば、余計なフラストレーションや誤解を減らし、親子の関係性が良くなります。また、親自身も子どもの成長を楽しめるようになり、育児ストレスが軽減される可能性が高まります。
日本における虐待事例の増加には、いくつかの社会的背景が影響しています。
1. 心理的虐待の増加: 身体的虐待だけでなく、心理的虐待が増加しており、家庭内の不和や親のストレスが子どもに深刻な影響を与えています
2. 通報しやすい環境の整備: 児童相談所の窓口が広がり、虐待が明るみに出る機会が増えたことも、件数増加の一因とされています。
3. 経済的ストレスと核家族化: 核家族化や共働きの一般化により、育児の負担が親に集中し、経済的な余裕のなさがストレスを増大させています。
4. 社会的孤立: 家族が地域や親戚とのつながりを失い、孤立することで、問題が家庭内で解決できず、虐待に繋がるケースが増えています。
5. 市民意識の変化: 家庭内の問題として見過ごされていた暴力が、社会的に認識されるようになり、通報件数が増加しています。
これらの要因が複雑に絡み合い、虐待事例の増加に繋がっています。社会全体での支援体制の強化が求められています。しかし、子育ての中心的存在のお父さん、お母さんが、我が子が五感の成長の敏感期に居ることを正しく理解すれば、子どもの不可解な行動にイライラせずに成長を促す対応を自然にできるようになり、結果、虐待される子どもを救うことができます。
親が子どもの成長を正しく理解し、適切に支援することは重要です。特にモンテッソーリ教育で提唱されている「秩序の敏感期」は、子どもが秩序や安定性を求める重要な発達段階であり、これを親が理解しサポートすることは、子どもの健全な育ちに寄与します。
秩序の敏感期とは? モンテッソーリ教育では、秩序の敏感期は生後6ヶ月から6歳頃に見られるとされます。この時期の子どもは、周囲の環境の秩序に敏感であり、物の配置や日常のリズムが安定していることを好みます。例えば、毎日同じ流れで食事や遊びが進むこと、物がきちんと片付けられていることなどが、子どもの安心感と自己制御能力を育てます。
親が理解しない場合の影響 親がこの敏感期を理解せず、家庭内で秩序が乱れていたり、育児の一貫性が欠けていたりすると、子どもが不安や混乱を感じやすくなります。このようなストレスが積み重なることで、親子間の関係性が悪化したり、虐待のような深刻な問題につながる可能性も考えられます。
提案 親が子どもの発達段階を正しく学び、理解するためには以下のような取り組みが有効です:
1. 育児講座やカウンセリングの活用: 子どもの敏感期について学べる場を提供する。
2. 地域コミュニティでの交流: 他の親や専門家とつながり、情報交換する機会を作る。
3. 秩序を意識した家庭環境の整備: 子どもが安心できる家庭環境を築く。
社会全体の仕組みも重要ですが、親自身が子どもの成長に合わせて行動することが、虐待予防の鍵になるといえるでしょう。
五感の敏感期とは
五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)の敏感期は、幼少期にそれぞれの感覚が急速に発達し、外部からの刺激に対して特に敏感になる時期です。この期間中に豊かな体験を提供することで、子どもの発達が促進されます。
各感覚とその特徴
1. 視覚: 色、形、大きさ、光と影などを認識し始める時期。絵本や自然観察が効果的です。
2. 聴覚: 言葉、音楽、自然音に敏感になり、音の違いやリズムを楽しむようになります。
3. 嗅覚・味覚: 香りや味に対して好奇心が高まり、食事や自然の中の香りに興味を示します。
4. 触覚: 質感や温度、圧力を通じて物事を学ぶ時期で、触れる体験が重要です。
最後に:
親が知っておくべきこと
•感覚を育む環境作り: 子どもが安心して五感を使える環境を提供することで、ストレスや混乱を避けられます。例:安全な場所で触れる体験を増やす、騒音を減らすなど。
•子どもの反応を観察する: 敏感期は子どもごとに異なるため、興味や反応をしっかり観察することが大切です。
根拠・関連する活動歴
44年間の教育現場経験。虐待問題への対応。要保護児童のカウンセリング経験。SSW(スクールソーシャルワーカー)の日本導入に関わった経験。








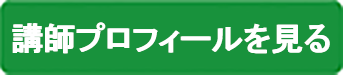


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました

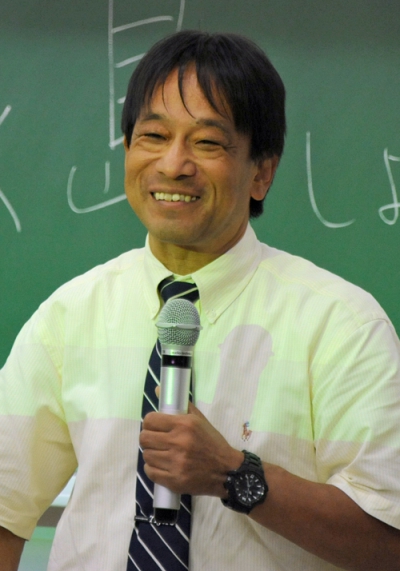











業務外の講師への取次は対応しておりません。