
テレワークが定着した今、オンライン研修は「例外的手段」から「育成の標準」になりつつあります。
とはいえ、初めて担当する方にとっては「通信トラブルが心配」「受講者が飽きないか」「効果をどう示すか」など、不安が尽きません。
本記事では、オンライン運営歴5年以上の講師マスターが、
企業研修を初めてオンライン化する研修担当者に向けて、
- オンライン研修の種類と選び方
- 準備・当日運営・フォローまでの流れ
- よくある失敗と防止策
- 外部サポートを活用して効率化する方法
を具体的に解説します。
オンライン研修とは?
オンライン研修とは、インターネットを通じて講師と受講者をつなぎ、遠隔で行う研修・講演のことです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなどがあれば、どこからでも参加できるのが特徴です。
コロナ禍以降、オンライン研修は「一時的な代替手段」から「企業の標準的な育成手法」へと変化しました。
最近では、時間・場所を問わず実施できる利便性に加え、地方拠点・海外拠点を含めた一斉教育やコスト削減・BCP対策の観点からも注目されています。
主なメリットは以下の通りです。
オンライン研修の主なメリット
- どこからでも受講でき、移動コスト・時間を削減できる
- 録画・資料共有により復習や欠席者対応が容易
- 同一教材を使用できるため、教育の質を均一化できる
- 感染症・災害時にも継続的に実施可能
一方で、「通信トラブル」「集中力維持」「双方向性の確保」といった課題もあり、研修の目的に合った配信形式を選ぶことが成功の鍵となります。
オンライン研修の種類~4つの配信方法を徹底比較
オンライン研修には、目的や受講環境に応じていくつかの方式があります。
主な形式は以下の4つです。
- ライブ配信型(リアルタイム配信)
- 収録型(オンデマンド配信)
- ハイブリッド型(組み合わせ型)
- eラーニング型(LMS活用)
1.ライブ配信型(リアルタイム配信)
あらかじめ決められた日時に、講師と受講者をリアルタイムでつなぐ形式です。
チャット機能や質疑応答機能を通して双方向のコミュニケーションができるのが最大の特徴です。
| 活用例 |
|
| 主な特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
2.収録型(オンデマンド配信)
事前に講義・講演を録画・編集し、後日視聴できるようにする方式です。
受講者は時間や場所を問わず、繰り返し視聴できます。
| 活用例 |
|
| 主な特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
3. ハイブリッド型(複合型)
ハイブリッド型は、複数の配信形式を組み合わせて実施する方法です。
ライブ配信+録画配信や集合開催+オンライン配信など、目的に合わせて柔軟に構成できます。
| パターン | 概要 | 特徴 |
| ライブ配信+収録(ライブ録画型) | リアルタイム配信を録画し、後日視聴可能にする | 欠席者対応・復習に便利。臨場感と効率の両立が可能 |
| 集合研修+ライブ配信(中継型) | 会場の様子を他拠点・自宅受講者にリアルタイム配信 | 会場の臨場感を保ちながら、全国拠点と同時受講できる |
| 集合研修+収録 | 会場での講演を録画し、後日オンデマンド配信 | 現場とオンラインを統合し、記録として活用できる |
| メリット |
|
| デメリット |
|

システムブレーンでは、講師手配からリハーサル・当日運営・録画配信までを一括でサポートしています。
④ eラーニング型(学習管理システム活用)
LMS(Learning Management System)を利用して、オンライン上で受講・テスト・進捗管理を一元化する方法です。
| 活用例 |
|
| 主な特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
4形式の比較まとめ
| 形式 | 双方向性 | 導入コスト | 管理のしやすさ | 主な用途 |
| ライブ配信型 | 高い | 低~中 | 中 | 双方向型研修・体験セミナー |
| 収録型(オンデマンド) | 低い | 中 | 高 | 知識教育・安全講習 |
| ハイブリッド型 | 中~高 | 中~高 | 中 | 全国拠点・全社イベント |
| eラーニング型 | 低い | 中~高 | 非常に高い | 継続学習・資格対策 |
オンライン研修で必要なツール
オンライン研修を成功させるためには、「配信」「管理」「運営」「学習支援」の4つの要素を支えるツールが欠かせません。
集合研修のように一箇所に集まれない分、通信環境や運営システムをしっかり整備しておくことが、受講者満足度を左右します。
以下では、基本ツールと運営支援ツールをあわせて紹介します。
基本的な配信・受講環境に必須のツール
☑web会議ツール
Zoom、Microsoft Teamsなど、オンラインで講師と受講者をつなぐための配信ツール。
無料プランでも使用できますが、時間制限・人数制限のない有料プランの利用をおすすめします。
社内で既に導入しているツールがある場合は、統一して使用すると運営がスムーズです。
☑安定したインターネット環境
映像・音声データ量が大きいため、光回線などの高速通信環境が必須です。特に配信・収録側は、無線よりも有線LAN接続を推奨します。
通信の安定性は、受講者の集中度や満足度に直結します。
☑PC・スマートフォン・タブレットなどのデバイス
 講師や運営担当者は、機能制限の少ないPCの使用が推奨です。
講師や運営担当者は、機能制限の少ないPCの使用が推奨です。
受講者も資料共有・画面操作がしやすいため、可能であればPCで参加しましょう。
スマートフォンやタブレット利用時は、専用アプリの事前インストールを忘れずに。必要に応じて、会社からデバイスを貸与するなど受講環境を整えることも大切です。
☑Webカメラ・イヤホン(またはヘッドセット
 双方向コミュニケーションの品質を高めるため、映像と音声の明瞭さが重要です。
双方向コミュニケーションの品質を高めるため、映像と音声の明瞭さが重要です。
内蔵マイクでも使用可能ですが、外付けWebカメラやマイク付きイヤホンを用いると、音割れやハウリングを防げます。
運営・管理を支える追加ツール
✅学習管理システム(LMS)/研修管理プラットフォーム
受講者の出欠・視聴履歴・成績・理解度を一括で管理できるシステム。
自動でリマインド通知を送る、未受講者を抽出するなど、運営負担の軽減と進捗把握が可能です。
代表例:LearningBOX、Moodle、TalentLMSなど。
✅コンテンツ作成/教材制作ツール
講義動画・スライド・クイズ・テキスト教材を制作・編集するためのツール。
PowerPointやCanva、Articulate、Camtasiaなどを使えば、視覚的で理解しやすい教材を短時間で作成できます。
講師自らコンテンツを更新できる仕組みを整えると、研修内容の鮮度も保てます。
✅ 受講者募集・申込管理・運営ツール
参加申し込みや出欠管理、受講票の発行などを自動化するツール。
Googleフォーム、Peatix、EventHubなどを活用すれば、研修受付〜当日運営までの事務工数を削減できます。
社内ポータルと連携させることで、スムーズな参加導線も構築可能です。
オンライン研修のやり方
オンライン研修を成功させるには、「計画・準備・運営・フォローアップ」という4つの段階を丁寧に設計することが大切です。
ここでは、初めて担当する方でもスムーズに進められるよう、具体的な流れとポイントを紹介します。
STEP1:研修内容とスケジュールを設計する
まずは、研修の目的・内容・対象者・成果目標を明確にすることから始めます。
新人教育や管理職研修、ハラスメント防止など、どのテーマをオンライン化するかを決め、研修目的に合わせて形式を選択しましょう。
- 講師を社内で担当するか、外部講師を招くか
- どの範囲をオンラインで実施し、どこを対面に残すか
- 1回あたりの時間、全体スケジュール
これらを整理し、プログラムと日程を具体的に決めていきます。
目的と手段を一致させることが、効果的なオンライン研修設計の第一歩です。
STEP2:配信ツールの選定と機能の確認
次に、研修に最適な配信ツールを選びましょう。
ZoomやMicrosoft Teamsなどを使用する場合、研修内容に合わせて利用機能を決めます。
主な機能例:
- 画面共有機能:スライド資料や動画を全員に表示
- ホワイトボード機能:資料上にメモや図を書き込み可能
- ブレイクアウトルーム機能:グループワークやディスカッションが可能
- アンケート(投票)機能:理解度チェックや意見収集に活用
- Q&A機能:質問の受付・整理に便利
- チャット機能:補足説明や意見共有が容易
- 録画機能:当日参加できなかった人への配信や復習に利用
どの機能を使うかを事前に決め、必要に応じて操作練習や事前説明を行いましょう。
STEP3:受講者の環境を整える
研修当日に混乱が起きないよう、受講者の通信環境と機器状況を確認します。
- 安定したインターネット環境(可能であれば有線LAN)
- 使用デバイス(PC推奨。スマートフォンは一部機能が制限される)
- Webカメラ・マイク付きイヤホン・ヘッドセットの有無
通信環境や機材が不足している社員には、モバイルWi-FiやPCの貸与など、会社としての支援体制を整えることも重要です。
特に初めてオンライン研修を実施する場合、接続テストを事前に行うことで安心して当日を迎えられます。
STEP4:開催設定と資料共有
配信ツールのスケジュール機能を使って、開催日時とURLを設定します。
設定後、以下を受講者へ事前に送付しましょう。
- 開催URL(当日アクセス用)
- 研修資料・配布物(PDFやスライド)
- 参加手順や注意事項
共有方法は、メール・チャット・クラウドストレージ(Googleドライブなど)を使うのが一般的です。
社内サーバーを使えば誤送信を防ぎ、アクセス権の管理もしやすくなります。
また、資料データが大きい場合は、クラウド経由での共有が安心です。
STEP5:機材・会場準備とリハーサル
本番前には、講師・運営・スタッフ全員でリハーサルを行います。
特に、初回のオンライン研修では以下の点を事前に確認しておくと安心です。
- 音声・映像・画面共有のチェック
- ブレイクアウトルームや投票機能の動作確認
- 質問受付やチャット対応の分担確認
- 録画テスト・トラブル発生時の対応手順
会場を使うハイブリッド型の場合は、カメラ・マイク・照明・回線速度の確認も欠かせません。
小規模でも構わないので、参加者を交えた「接続テスト会」を実施すると安心です。
STEP6:フォローアップと効果測定
研修当日が終わったあとも、フォローアップが学習定着の鍵です。
- 録画した動画を社内共有し、復習機会を提供
- 研修直後のアンケートで満足度・理解度を測定
- LMS(学習管理システム)などを使って受講履歴を管理
- 次回研修や関連テーマへの継続学習を促す
これらの仕組みを整えることで、オンライン研修が単発で終わらず、
「継続的な学び」として社内教育に定着していきます。
オンライン研修を成功させるためのコツ
 オンライン研修を成功させるには、「事前準備」「双方向性」「フォローアップ」の3つが重要です。
オンライン研修を成功させるには、「事前準備」「双方向性」「フォローアップ」の3つが重要です。
ここでは、企業の研修担当者が押さえておきたいポイントを具体的に紹介します。
コツ1:目的と形式を一致させる
オンライン研修の目的に応じて、最適な配信形式を選びましょう。
- ライブ配信型:リアルタイムで講師とやり取りしたい研修(例:新人研修・チームビルディング)
- オンデマンド型:繰り返し学びたい研修(例:コンプライアンス・安全教育)
- ハイブリッド型:リアル会場とオンラインを組み合わせたい研修(例:全国拠点合同の社員研修)
「目的と形式のズレ」があると、受講者の集中力が下がりやすいため、最初の設計段階で明確にしておくことが大切です。
コツ2:双方向のコミュニケーションを意識する
オンライン研修では、受講者が受け身になりやすい傾向があります。
チャット機能や投票機能、ブレイクアウトルームなどを活用し、参加型の仕掛けを取り入れましょう。
- 研修中に「質問タイム」を設ける
- クイズやアンケートで理解度を測る
- グループワークで意見交換を促す
リアルの臨場感に代わる「対話と参加の設計」が、オンラインならではの成果を生みます。
コツ3:運営体制を明確にしておく
オンライン研修では、講師だけでなく運営チームの分担が重要です。
- 司会進行役:開始・終了・質疑応答の進行を担当
- 運営補佐:チャット・投票・資料共有をサポート
- 技術担当:通信や音声トラブルに即時対応
1人がすべてを担うよりも、複数人で役割を明確に分けることで、安定した配信が実現します。
コツ4:事前リハーサルを欠かさない
リハーサルは、オンライン研修の品質を左右する最重要ステップです。
- 通信速度・音声・映像の確認
- 資料共有・録画・チャット動作のチェック
- 想定外トラブルの対応手順を決めておく
特に、初めての配信では「受講者を含めた接続テスト」を実施することで、当日の混乱を防げます。
コツ5:フォローアップで学びを定着させる
研修が終わった後こそ、学びを深めるチャンスです。
- 録画を社内共有して復習機会を提供
- アンケートで理解度・満足度を可視化
- LMS(学習管理システム)で受講履歴を蓄積
- 次回研修やeラーニングへの導線を作る
受講後のフォローアップを仕組み化することで、研修の効果を継続的に高められます。
コツ6:受講者が集中しやすい環境をつくる
オンラインでは、受講者の集中力が途切れやすい点にも配慮が必要です。
- 1セッションを 60~90分以内 に区切る
- 開始5分前にログインを促し、スムーズに開始
- カメラオン推奨で「つながり」を意識させる
講師も、テンポよく話す・スライドをビジュアル化するなど、画面越しでも飽きさせない工夫を取り入れましょう。
オンライン研修は効率と質を両立できる新しい学びの形
オンライン研修は、時間・場所・コストの制約を解消し、全社員に平等な学びの機会を提供できる仕組みです。
ツールや手順をしっかり整え、双方向性と継続学習を意識することで、
対面研修に劣らない満足度と成果を得ることができます。
📌 よくある質問
Q1. オンライン研修を始めるには何から準備すればいいですか?
A.まずは研修の目的と対象を明確にし、配信ツール・講師・スケジュールを決めましょう。その後、受講者の通信環境や機材確認を行うとスムーズです。
Q2. オンライン研修でトラブルを防ぐには?
A.本番前に必ずリハーサルを実施し、音声・映像・資料共有を確認しましょう。通信が不安定な場合は有線LANを使用するのがおすすめです。
Q3. どんな研修にオンライン形式が向いていますか?
Q4. 受講者の集中力を維持するには?
A.セッションを60分以内に区切り、チャット・投票・グループワークなどの参加型要素を入れると効果的です。
Q5. 対面と比べて学習効果は落ちませんか?
A.適切な設計とフォローアップを行えば、オンラインでも十分な効果を得られます。録画やアンケート分析により学びを定着させましょう。
あわせて読みたい
コロナ禍で急増したオンラインでの研修。まだまだ収束が予測できな…
デジタル技術の革新により、世界中の企業がDXの推進を迫られてい…
アンガーマネジメントは今や職場の環境づくりを考えるうえで避けて…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました






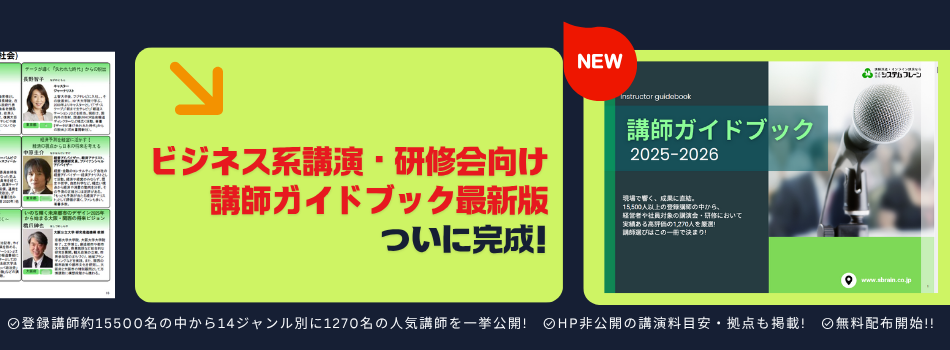











業務外の講師への取次は対応しておりません。