
多様性がイノベーションを生むという考えの下、これまで多くの企業がLGBTQ+のアライ(支援者)としての取り組みを進めてきました。しかし米国で名だたる企業が多様性重視の方針を撤回するなど、現在は揺り戻しとも言える現象も一部で起きています。
今回、LGBTQ+当事者であり、メディアや企業研修においてLGBTQ+を取り巻く課題を長年伝えてきた杉山文野氏に、企業がアライであることの重要性や取り組みのポイントについてお聞きしました。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
杉山文野氏
NPO法人東京レインボープライド理事
日本オリンピック委員会(JOC)理事
株式会社ニューキャンバス代表取締役
企業が今こそ知っておきたい、LGBTQ+について
LGBTQ+についてまず理解しておくべきなのが、彼らが「目に見えづらいマイノリティ」であるという点です。多くの当事者は、自分たちがLGBTQ+であることを周囲に公表していません。それはカミングアウトによって周囲からネガティブな反応を受けることへの不安や恐れがあるからです。そのため、自らのアイデンティティを隠さざるを得ない状況に置かれているのです。
では実際、国内にどれほどのLGBTQ+の人がいるのでしょうか?
統計によると国内のLGBTQ+の割合は、人口の5~8%とされています(※1)。この割合は、たとえば日本で最も多い苗字である「鈴木・佐藤・高橋・田中」の4姓を合計した人口割合(約5%)に相当し、「伊藤・渡辺」を加えるとおよそ8%になります(※2)。
つまり、職場にもこれらの名字の人と同じくらいの割合でLGBTQ+の従業員が存在していると考えられます。
彼らがカミングアウトしない限り、職場にLGBTQ+の当事者がいるかどうかを把握するのは難しいのかもしれません。しかし、「うちの会社にはLGBTQ+はいないよね」と安易な発言をする前に、この5~8%という数字を思い出す必要があります。LGBTQ+の存在は見えづらいかもしれませんが、実際には同じ職場で日々顔を合わせている可能性が高いのです。そしてそのような発言によって存在を否定されることが、さらにカミングアウトしづらい心理状態を生むことも理解しておかなければなりません。
出典: ※1 LGBTQ調査研究・アドボカシー
※2 明治安田生命 全国同姓調査
LGBTQ+当事者が安心して働ける職場づくり、企業側のメリット
 LGBTQ+の多くは、「LGBTQ+であることが知られたら、職場に居場所がなくなるかもしれない」という不安を抱えながら働いています。そのため共に働くチームの仲間であっても本当の信頼関係を築くのが難しい状況にあります。当然、こうした不安はチームワークや仕事の生産性にも影響を与えます。企業がLGBTQ+フレンドリーな職場づくりに取り組むことで、当事者の不安を取り除き、パフォーマンスの向上につなげることができるでしょう。
LGBTQ+の多くは、「LGBTQ+であることが知られたら、職場に居場所がなくなるかもしれない」という不安を抱えながら働いています。そのため共に働くチームの仲間であっても本当の信頼関係を築くのが難しい状況にあります。当然、こうした不安はチームワークや仕事の生産性にも影響を与えます。企業がLGBTQ+フレンドリーな職場づくりに取り組むことで、当事者の不安を取り除き、パフォーマンスの向上につなげることができるでしょう。
一方、2025年1月に発足したトランプ政権がトランスジェンダーの権利を制限する政策を推し進め、米国の一部の大企業でもそれに続いて多様性推進の方針を撤回する動きが見られました。こうした企業と取引のある一部の国内企業においては、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)への言及を避け、取引先との関係維持を優先するケースもあります。
しかし、このような米国での動きが日本国内へと波及し、国内企業の方針に大きな影響を及ぼす恐れは低いと考えられます。
その理由として、第一に日本では揺り戻し現象が起きるほどLGBTQ+のアライとしての取り組みは進んでいない点が挙げられます。
第二に、諸外国のように豊富な資源を持たない日本では、個々の人材をいかに活かすかが発展の鍵を握っているためです。国際社会での競争に勝つためにも、すべての従業員が安心して働ける環境を整え、その能力を最大限に発揮できるようにすることが求められます。
そして何より、LGBTQ+の人々が安心して働ける職場をつくることは、人権を尊重する社会の実現に直結します。マイノリティが不当に排除されることを容認するような社会では、誰も安心して暮らすことができません。LGBTQ+に関する課題を考える際は、それが基本的人権の問題であることを常に念頭に置く必要があります。
どの企業でも始められる、LGBTQ+が働きやすい職場4つの取り組み
 真のアライ企業になるためには、社内の制度やルールとしてLGBTQ+を支援するだけでなく、職場の一人ひとりに支援の意識を根付かせ、それを企業文化として定着させる必要があります。そして、どのような文化も、その第一歩はトップからの発信によって生まれるものです。
真のアライ企業になるためには、社内の制度やルールとしてLGBTQ+を支援するだけでなく、職場の一人ひとりに支援の意識を根付かせ、それを企業文化として定着させる必要があります。そして、どのような文化も、その第一歩はトップからの発信によって生まれるものです。
ここではLGBTQ+の人たちが安心して働ける職場を実現するための、企業の具体的な取り組みの例を紹介します。
①PRIDE指標で自社の取り組みを評価
まずは自社の現状を知り、アライ企業としての客観的な評価を知ることで、さらなる課題も見えてきます。
年に1度開催される「work with Pride」というカンファレンスでは、国内の企業や団体の人事、ダイバーシティ推進担当者を対象に、その取り組みを評価・認定しています。このとき用いられるのが「PRIDE指標」で、LGBTQ+が働きやすい職場づくりのために策定されたものです
この「PRIDE指標」のチェックリストを自社の現状と照らし合わせてみることで、見過ごしていた課題に気づけるかもしれません。
②LGBTQ+支援のための社内制度をつくる
社内制度をつくることは、言わばアライ企業としての意思表示です。同性のパートナーにも福利厚生を適用する、相談窓口を設置するといった制度を積極的に取り入れましょう。
中には「支援制度を整えたものの1年で申請が1件もなかった」という企業もあるかもしれません。しかし、前述した通り、LGBTQ+当事者は多くはカミングアウトに対して強い不安を抱えており、制度があっても気軽に利用できるとは限りません。
それでもなお、「制度を使うか・使わないか」の選択肢が当事者側にあること自体が重要です。当事者にとって「言わない」のと「言えない」のでは、心理的安全性が全く異なります。制度があることで、会社が自分を受け入れてくれるという安心感が生まれ、利用するかどうかは本人の意思に委ねられます。
申請が無いからといって制度が無意味だと決めつけず、取り組みを継続することが大切です。
③社内のアライを可視化
社内制度の1つとして、アライを可視化する方法があります。例えば、レインボーシールやキーホルダーなどを身に付けることで、「この人には相談できる」と当事者が一目で認識でき、安心感につながります。
また、シールのような形式的なものだけでなく、社内での日々の会話の中でLGBTQ+に対して肯定的な発言をすることで、その人がアライであると当事者にも伝わります。LGBTQ+からのカミングアウトをいつでも受け止めるという「ウェルカミングアウト」の姿勢を積極的に示すことがポイントです。
④LGBTQ+についての社内研修を実施
社員に正しい知識と配慮の姿勢を身につけてもらうために、LGBTQ+に関する研修を実施することも重要です。
SNSや一部のメディアには偏った情報が溢れており、正しい認識が広まっていない現状があります。しかし、LGBTQ+当事者の体験談を聞くことで考え方が180度変わり、頼もしいアライとなる社員も少なくありません。
また、たとえ個人の考えがどうであれ、LGBTQ+に対してどう振舞うかというのは社会人の教養の1つとなりつつあります。他者の人権を侵害しない振る舞い方を、研修によってスキルとして社員に身に付けさせる必要があるのです。
LGBTQ+に対して否定的な考えを持つ人も、社会人として職場やSNS上での発言に配慮するようになることで、組織の雰囲気も次第に変化していくでしょう。
合わせて読みたい
LGBTQ+への支援で職場が変わる!企業のさらなる発展へ

企業がLGBTQ+にとって働きやすい職場を実現するためには、何よりも継続的な取り組みが重要です。トップが発信した方針が現場に浸透し、企業文化として根付くまでには、長い時間がかかります。実際に職場で働くLGBTQ+当事者が、本当の意味での「安心」を得られるのはずっと先になるかもしれません。
それでも、LGBTQ+支援のための制度を作ったり、研修を実施したりすることで、当事者が置かれている状況には大きな変化が生まれます。これまで「言いたくても言えない」と感じていた状況が、「今はまだ言わないけれど、いつか自分の意思で伝えたい」という前向きな選択へと変わるのです。そこに選択の自由があることは、当事者にとって非常に大きな意味を持ちます。
現在、国際社会の一部では多様性推進に対する”揺り戻し”の動きも見られますが、国内企業は引き続きLGBTQ+支援の取り組みを行うことで、流行りや表面的な事象に左右されない真のアライ企業であることを体現できるでしょう。また、LGBTQ+に限らず、誰もが何かしらのマイノリティであることを考えれば、マイノリティにとって優しい職場や社会はマジョリティにとっても暮らしやすい社会につながっていくはずです。
今回お話しを聞かせていただいた元フェンシング女子の日本代表・杉山氏の研修では、LGBTQ+当事者の目線から企業として必要な取り組みについて学ぶことができます。同氏の研修に参加した人の中には「何となくLGBTQ+のことを知っているつもりでいたが、話を聞いて自分の中での認識が大きく変わった」と言う人もあり、LGBTQ+の社内研修を初めて導入する企業にも最適な内容です。
多様性推進に興味をお持ちの企業のご担当者様は、ぜひ次回研修としてご検討ください!
杉山文野 すぎやまふみの
NPO法人東京レインボープライド 共同代表理事
日本オリンピック委員会(JOC)理事 株式会社ニューキャンバス代表取締役

フェンシング元女子日本代表。トランスジェンダー 。早稲田大学大学院修了。2年間のバックパッカー生活で世界約50カ国+南極を巡り、 現地で様々な社会問題と向き合う。NPO法人東京レインボープライド共同代表理事、日本初となる渋谷区・同性パートナーシップ制度制定に関わる。
|
講師ジャンル
|
ビジネス教養 | その他ビジネストピック | |
|---|---|---|---|
| 社会啓発 | 人権・平和 | 教育・青少年育成 |
プランタイトル
LGBTQと企業
~職場でのダイバーシティを考える~
あわせて読みたい
営業研修はなかなかうまくいかない、失敗するという声がよく聞かれ…
営業スキルとは「コミュニケーションスキル」と言っても過言ではあ…
数ある商品の中から選び買って頂くために必要な営業ノウハウとは?…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました








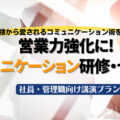









業務外の講師への取次は対応しておりません。