
企業には、対象者やタイミングによって、安全衛生研修を実施する義務があります。しかし法的義務を別にしても、安全衛生研修は労働災害を防止し従業員の健康を維持するのに非常に重要な施策です。
この記事では、安全衛生研修の目的や進め方について解説します。人気の研修プランの情報もぜひチェックしてください。
安全衛生研修の目的
まずは、なぜ企業が従業員に安全衛生研修を受けさせる必要があるのかについて、主な理由を3点に絞って説明しましょう。
1.労働災害を防ぐ知識・スキルの獲得
安全衛生研修の最大の目的は、労働災害の発生を未然に防ぐことです。
厚生労働省「令和5年の労働災害発生状況」によると、年間700人以上が労災によって命を落としています。現場での災害は、正しい知識と行動で多くが防げるものです。
例えば「感電防止のためには絶縁装置を点検する」「足場作業では安全帯の装着が必要」といった基本事項も、理解と習慣が伴って初めて効果を発揮します。
研修では、実際の事例や体験談を交えて事故を「自分事」として考え、現場で実践できる力を養います。
2.従業員の健康維持・増進
安全衛生研修は、身体的リスクだけでなく、日常的な健康維持にも役立ちます。
熱中症や腰痛、メンタルヘルスといった身近なテーマの研修もあり、早期対応の重要性や日常的なセルフケア方法を学べます。これらの知識は、体調不良による生産性の低下や休職を防ぐうえでも欠かせません。
3.安心して働ける職場づくり
「この職場は安心して働ける職場」と感じられるかどうかは、従業員のモチベーションや定着率にも大きな影響を与えます。
研修で身につけた知識やスキルで職場の改善が進めば、心身とも健康的に働きつづけられる従業員が増え、顧客や取引先からの信頼性も高まるでしょう。
安全衛生研修を義務付ける法令
次に、安全衛生研修が求められる法的根拠や業種別の注意点、さらに法改正への対応について解説します。
労働安全衛生法における研修受講の義務
労働安全衛生法および労働安全衛生規則では、企業に対して従業員に研修を受けさせる義務を課しています。
例えば、危険性の高い機械や重機・化学物質を扱う人、高所作業に携わる人、安全・衛生管理者や職長などに選任する人に対しては、法律上の教育義務があります。
建設業・製造業は特に注意が必要
安全衛生研修はすべての業種に有効ですが、特に建設業・製造業では法的義務に対する確実な対応が重要です。
これは労災発生率が他産業に比べて高く、死亡災害や重篤な事故が多いためです。実践・応用力を身につけるため、座学だけでなく、演習・訓練なども重視されます。
法令改正対応にも研修が有効
安全衛生に関する法令は時代背景に応じてたびたび改正されるため、うっかりしていると、知らない間に法令に違反していることになりかねません。近年の改正では、定期的なストレスチェックの義務化や作業場所の照度基準改正などで、多くの企業が影響を受けました。
最新の法令を正しく理解したうえで社内で取り組みを推進するのに、研修は有効です。
一般的な安全衛生研修の対象者
基本的な内容を扱う一般向けの安全衛生研修は、法的義務ではないものの、企業には安全衛生教育が推奨されています。研修による教育は、職種・階層・年次・雇用形態などにかかわらず、すべての従業員にとって有益です。
現場作業員はもちろん、オフィス内での作業がメインの事務職や営業職も同じです。転倒事故・腰痛・過重労働による精神疾患など、健康リスクと隣り合わせにあるためです。
また、管理職やリーダー層は、部下への安全配慮義務や職場環境整備の観点から、より高度な知識が必要です。役割や立場に応じた教育は、リスクを防ぐうえで欠かせません。
研修・講習受講が法的義務とされている対象者
次は法令で義務化されている研修の対象者に関して、代表的な4つのカテゴリに分け、実務にどのように関わってくるのかを整理します。
安全管理者/衛生管理者、安全衛生推進者/衛生推進者
安全管理者や衛生管理者は、一定要件を満たす職場には選任が義務付けられた役割です。
特に衛生管理者は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」では、必ず1人以上を置き、職場の衛生管理体制を整えなければなりません。衛生管理者は国家資格で、資格の取得後も定期的な研修などによる最新知識の習得を要します。
また規模を問わず一定の業種では「安全衛生推進者」や「衛生推進者」の選任も義務になります。現場により近い立場で、職場内の定期巡視や安全教育に取り組む存在です。
職長および安全衛生管理責任者
建設業や製造業における「職長」や「安全衛生責任者」は、現場の第一線で従業員を指導する安全衛生活動のリーダーです。労働安全衛生規則において、これらの職務に就く人は「職長教育」や「安全衛生責任者教育」の受講が義務づけられています。
職長は、作業者への業務指示や安全指導を通じ、労災防止に貢献する立場です。安全衛生責任者は、労災発生時における報告や現場の安全対策強化など、企業と現場とをつなぐ重要な役割を果たします。
特別教育を必要とする作業従事者
クレーンやフォークリフトの操作、高所での作業、化学物質の取り扱いなど、危険性・有害性の高い職務に従事する人には、「特別教育」が義務づけられています。
受講しないままこれらの業務に従事させた場合、労働安全衛生法違反となり、行政指導を受けたり、罰則を科されたりする可能性があります。
新規に雇い入れた従業員・作業を変更する従業員
新たに雇用された従業員や、配置転換などにより業務内容が変わる従業員に対しても、労働安全衛生法は「雇入れ時教育」「作業内容変更時教育」の実施を義務づけています。
業務経験の浅い従業員が被災する事案が多いため、必ず事前に教育の時間を設け、正しい手順や安全ルールを伝えましょう。
安全衛生研修プログラムに取り入れたい主なテーマ8選
ここでは、安全衛生研修の基本となる8つのテーマについて、その目的や内容に加え、システムブレーンのおすすめ研修プランを交えながら紹介します。
①安全衛生関連の業務従事に不可欠な講習
安全衛生関連の業務や役割に就くうえで欠かせない講習の例は以下の通りです。特に建設業や製造業などでは、安全に関する教育の重要性が高いです。
- 職長・安全衛生責任者教育
- 安全管理者選任時講習
- 衛生管理者資格取得講習
- 安全衛生推進者養成講習
- 衛生推進者養成講習
- 特別教育
人気研修プラン
作業を指揮命令する人には、災害防止の責任がある!労働災害と経営者等の刑事責任および民事責任
労働災害発生時に問われる刑事・民事責任について、具体事例を交えて解説する実践講座です。元三菱電機安全衛生協力会事務局長で安全衛生教育の第一人者が、作業指示者が負うべき安全配慮義務の本質を、法的観点と現場目線の両面からお教えします。
建設業の安全管理体制(労働安全衛生法より)
建設業に特化した安全管理体制の基本を、法令の背景から実務での活用まで整理する研修です。「個別管理」と「統括管理」の役割や、労働安全衛生法第100条の報告義務についても、労働安全コンサルタントが実例を交えながら明快に伝えます。
リーダーに求められる3つの管理
「先取りの安全衛生管理」「情報管理」「部下育成」──リーダーに求められる3つの管理機能を軸に、現場で活かせるリーダーシップを磨く実践型研修です。安全衛生教育トレーナーであり社会保険労務士である講師が、職長教育やコミュニケーション研修で培ったノウハウをもとに指導します。
機械包括安全指針に沿った機械設備安全化の進め方
「絶対安全」ではなく「リスクの適正低減」を目指す国際規格に基づき、機械設備の設計段階から行う安全化手法を学ぶ研修です。ISO/IECガイド51やJIS規格を踏まえたリスクアセスメントの進め方を、労働安全コンサルタント講師が実例とともに解説。技術者・管理者層に必須の内容です。
合わせて読みたい
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
②リスクアセスメントの手順
「リスクアセスメント」は、職場に潜む危険を事前に特定・評価し、対策を講じるための手法で、多くの企業で導入されています。
全体的な手順や各プロセスの進め方、継続的に改善する方法などについて体系化された教育プログラムもあり、研修・講習によって効率的に学習が可能です。
人気研修プラン
「ホンネ」 と 「タテマエ」の中で本当の安全をつくる
「危険は必ずある」という前提に立ち、痛みを経験する前にできることを考える――それが本研修の核です。現場での安全パトロールや事故後の再発防止会議を通じ、多くの“ホンネ”と向き合ってきた講師が、実体験に基づいたリスクアセスメントの本質と、現場で使える判断軸を具体的に伝えます。
現場責任者の「危険感受性」の向上~気づかなければ注意できない!作業員を守れない!~
事故を防ぐ鍵は、現場責任者の「危険感受性」です。中小企業診断士・特定社労士であり、豊富な実務経験をもつ講師が、現場主導の安全文化づくりを目指し、危険発見力を高める具体的手法や改善事例を交えて詳しく解説します。現場の“気づき”を鍛える機会です。
後追い型安全管理から安全先取り型管理への挑戦
これからの現場には、「起きてから対応」ではなく「起きる前に備える」力が求められます。本研修では、リスクアセスメントを活用した“安全先取り型管理”の思考と手法を習得。CSP・CIHの両資格を持ち、現場教育に定評のある講師が、未来志向の安全体制づくりを後押しします。
建設業・製造業の労働安全~安全は家族の願い、会社の望み~
本研修では、実際の労災事例を通じて、安全配慮義務や建設業・製造業のリスクを深く考えます。入札制度との関連や一人親方制度など、業界特有の課題にも対応。CSP労働安全コンサルタント講師が、選択制で柔軟に講義を構成し、現場と経営の意識改革を促します。
合わせて読みたい
いくら注意を払い労働災害・事故を起こさないようにしても、まった…
いくら注意を払い労働災害・事故を起こさないようにしても、まった…
③5S活動
「5S活動」とは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取った職場改善の基本活動のこと。安全で効率的な職場づくりに直結します。日本の製造業で生まれた手法として、今や世界に知られています。
安全衛生研修でも定番となっているテーマの1つです。
人気研修プラン
仕事が楽しくなる!安全に繋がる!職場が見違える!アッと驚く5S色彩活用術
5S活動に“色”の力をプラスして、現場が劇的に変わる!本研修では、色彩戦略家が、心理効果を活かした整理整頓術や、視認性・効率・モチベーション向上につながる色の使い方を伝授。安全性だけでなく、働く楽しさも手に入る“驚きの5S”を体感いただけます。
安全意識の向上は職場環境風土の改革から
災害を防ぐには、ルールや設備だけでなく“職場の意識風土”を変えることが不可欠です。本研修では、欧米との比較や現場の事例を通して、自主的な安全文化づくりの重要性を共有。RSTトレーナーが、行動を変えるヒントを伝えます。
建設現場の労働災害を防ぐ~ヒューマンエラー発生のメカニズムと現場での防止~
「人は誰でも間違える」――だからこそ、現場では仕組みとチームの力で災害を防ぐ必要があります。本講演では、ヒューマンエラーのメカニズムと5Sの視点を交え、エラーを防ぐ環境づくりを提案。航空業界の安全専門家講師が、楽しく学べる参加型スタイルで伝えます。
経費ゼロ!? 安全な職場環境のつくり方!~5Sをスムーズに実現するために!思考とモノの整理のコツ~
探し物ばかり、片づかないデスク、イライラ…そんな職場の悩み、5Sで解決しませんか?本講演では、人材育成のプロが、整理整頓を“目的”ではなく“成果を生む仕組み”と捉え、意識と行動を変えるヒントをお届けします。ワークを交えた参加型で、明日から実践できる整理力を手に入れましょう。
合わせて読みたい
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
単に職場をきれいにするためだけに環境整備(整理・整頓・清掃)を…
④危険予知訓練(KYT)
「KYT(危険予知訓練)」は、作業前に潜在的な危険を予測し、安全な行動を考える訓練です。「何が危ないか」について現場メンバー同士で話し合い、対策を考えるプロセスを重視します。
特に建設・製造現場などで、実際の作業現場の写真・イラストを用いた実習が取り入れられています。
人気研修プラン
安全先取りに役立てる危険予知活動の進め方~リスクアセスメントを取り入れて~
見えている危険だけでは防げない――本研修では、従来の危険予知活動にリスクアセスメントを加え、事前対策を強化する実践法を学びます。700回以上の安全研修経験をもつ講師が、現場で本当に使える「簡単にできる危険予知」の進め方を具体的に伝授。三現主義の視点も重視します。
KYT(危険予知訓練)研修
形だけのKYTになっていませんか? 本研修では、実技やグループ討議を通じて、現場で活きる「正しいKYT」の本質を習得します。講師は公認KYTインストラクターとして多数の現場を指導してきた経験を活かし、短時間で口頭実施できる独自手法や業種別の応用法も紹介。実践重視の内容です。
5ラウンドで決める!効果バツグンの危険予知
KYTを導入しても「効果が出ない」「続かない」と感じていませんか? 本研修では、従来の4ラウンド法を進化させた“5ラウンド法”を導入し、危険感受性と継続的な安全意識を養います。KYTの本質と進め方を実践ワークで体得し、現場で成果を出すための第一歩を踏み出しましょう。
不安全行動/ヒューマンエラーはこう防ぐ(危険感受性を高め危険敢行性を下げるには)
ヒューマンエラーや不安全行動を防ぐ鍵は、KYT(危険予知訓練)で危険感受性を高め、危険敢行性を抑えることにあります。本研修では、人間の行動特性に基づき、KY活動を通じて「気づく力」と「行動を変える力」を養成。現場全体で安全意識を共有し、事故を未然に防ぐ実践的な知識を身につけます。
⑤ヒヤリハット報告の活用や事例
 「ヒヤリハット」とは、「ヒヤリとした」「ハッとした」ものの、事故には至らなかった事象のことです。
「ヒヤリハット」とは、「ヒヤリとした」「ハッとした」ものの、事故には至らなかった事象のことです。
重大災害の背後には数多くのヒヤリハットが存在し、それらの情報を集めて対策につなげることが、安全管理の基本です。研修では、報告を集める方法や分析手法、改善につなげる流れなどを学べます。
人気研修プラン
ヒヤリハットすらおこさない!安心・安全現場・職場の作り方~一致団結!危険の芽をつみとろう!~
ヒヤリハットを未然に防ぐには、気づく力と共有する力がカギ。本研修では、KYT的視点を取り入れ、危険感受性を高め、風通しの良い職場づくりを実践的に学びます。建設業界での研修経験豊富な講師が、現場に笑顔と安全意識を届けます。
労働災害防止に生かすアンガーマネジメント~職場の安全衛生/ヒヤリハットの防止と対策~
怒りに振り回される職場では、情報共有が滞り、ヒヤリハットの芽を見逃しがちです。本研修では、アンガーマネジメントの手法を通じて感情を整え、現場の安全と信頼関係を築く力を育みます。職場内のストレス対策からKY活動の質の向上まで、実践的に学べる内容です(オンライン対応可)。
同じヒヤリハットを起こさない! 安全な職場をつくる『なんでやねん力』
同じヒヤリハットを繰り返さない職場づくりには、報告しやすい空気と“正しい問い”が必要です。本研修では、笑いを通じて「なんでやねん力=問題発見力」を磨き、心理的安全性のある職場を実現。芸人ならではの視点で、楽しく学べるプログラムです。
目ウロコ!「最悪の事態でも全員が助かるために」~羽田空港地上衝突事故を例に・・・
羽田空港地上衝突事故をもとに、最悪の事態でも全員が助かるために必要な判断力と連携力を考える研修です。航空業界での経験をもつ講師が、ヒヤリハットの早期共有や脳の特性を踏まえたコミュニケーション術を紹介。小さな異変を見逃さず、重大事故を防ぐ感性を養います。
合わせて読みたい
どの職場にもヒューマンエラーは付きものです。「今度こそ気をつけ…
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
⑥熱中症対策
熱中症は職場においても重大な健康リスクとして注目され、2025年からは、一部の事業者に対して熱中症対策の実施が法令で義務付けられました。
研修では、熱中症の基礎知識や発症時の応急対処のほか、暑熱順化(身体が暑さに慣れること)、水分・塩分補給の重要性や作業環境の改善などについて習得します。
人気研修プラン
まずはこれだけ!熱中症予防と対応の3つのポイント
本研修では、作業現場での熱中症対策を「安全衛生管理」の視点から学びます。「休む・冷やす・飲む」の3原則を中心に、重症度の見極めや救急要請の判断基準をわかりやすく解説。看護師としての現場経験を活かし、管理者・作業者ともに実践できる予防と対応を丁寧に伝えます。
熱中症を予防しよう!一番わかりやすい熱中症予防のおはなし
熱中症対策は、水分・塩分補給だけでは不十分です。本研修では、消防現場の豊富な経験をもつ講師が、誤解されやすい予防法や体質に応じた対策を、誰にでもわかる言葉で丁寧に解説します。現場作業に役立つ“本当に効く”熱中症対策を、安全衛生の視点から学びましょう。
この夏の傾向と熱中症
異常気象が常態化する中、熱中症による労働災害リスクも年々深刻化しています。本研修では、気象予報士講師が「この夏の傾向」とあわせて、建設現場や高齢者に多い熱中症の特徴と予防策をわかりやすく解説。気候変動時代の安全対策を、最新データとともに学びます。
【実践的】25問のクイズで考える健康と安全習慣アプローチ ~熱中症と睡眠の関係~
熱中症対策と快眠習慣――実はどちらも職場の安全と生産性に直結しています。本研修では、25問のクイズ形式で楽しみながら、正しい水分補給や睡眠の質がもたらすパフォーマンスへの影響を学習。幅広い年齢層の健康を支えてきた快眠コンシェルジュ講師が、日常に活かせる習慣づくりをサポートします。
合わせて読みたい
夏の労働災害の原因として上位にあるのが熱中症です。特に7~8月…
年々猛暑日が増える中で、熱中症は誰にとっても身近な健康リスクと…
⑦ヘルスケア・健康増進策
 作業時の事故防止に加え、従業員の健康増進も重要なテーマです。近年は「健康経営」への関心とも連動し、組織全体で健康づくりに取り組む動きが広がっています。
作業時の事故防止に加え、従業員の健康増進も重要なテーマです。近年は「健康経営」への関心とも連動し、組織全体で健康づくりに取り組む動きが広がっています。
生活習慣病や体調管理などの課題に対して、食生活・運動・睡眠などの基礎知識と実践的な対策・改善方法を学びます。
人気研修プラン
ゴールは健康!~今日からスタート 10年後の健康を目指して~
不調を放置すれば、労働災害や生産性低下の一因に。本研修では、肩こり診断やツボ押しなどの実技を交え、作業者自身が「気づき、予防する力」を養います。講師のケガと回復経験をもとに、ストレッチ・姿勢・セルフケアの重要性を伝え、職場全体の健康意識と安全行動の定着を図ります。
安全な現場を守る 身体と心のマネジメント
安全な現場づくりには、身体と心のセルフマネジメントが欠かせません。本研修では、生活機能低下を防ぐための簡単な運動・脳トレ・睡眠・栄養について、実技を交えてわかりやすく紹介。アナウンサーとしての発信力と防災知識を活かし、健康と安全を両立する習慣づくりを後押しします。
ミスを防ぎ、集中力を高めるための健康管理と食事法
ミスや事故を防ぐには、体と脳のコンディションが鍵です。本研修では、集中力を高める食事の選び方や、朝食・オメガ3の効果など、現場で即活かせる栄養知識をクイズ形式で楽しく学べます。料理現場での実体験も交え、健康管理と安全意識のつながりを実感できる内容です。
STOP! 転倒災害 安全は足元から~転倒予防に役立つ靴選び&履き方、歩き方~
転倒災害は全産業で最も多い労働災害の一つ。本研修では、シューズ選び・履き方・歩き方の改善を通じて、足元から安全を見直します。転倒予防指導士の講師が、実技を交えて日常歩行を“事故防止につながるウォーキング”に変える方法をわかりやすく伝授します。
合わせて読みたい
転倒災害は、休業4日以上の死傷災害全体の2割以上を占め、増加の…
心身の健康づくりなくして、職場の安全・生産性の向上なし!健康は…
⑧メンタルヘルス・ストレスマネジメント
近年、過重労働や精神的ストレスに由来する健康障害が注目を集めており、メンタルヘルス対策は安全衛生研修に欠かせないテーマとなっています。
ストレスの要因や兆候、セルフケアやラインケアの方法などを従業員に学んでもらい、心身の健康維持を促します。
人気研修プラン
100m級鉄塔で高所作業!「元現場女子が語る、安全管理術」~その事故、メンタルヘルスで防げます!~
100m級鉄塔での作業経験をもつ“元・現場女子”が、ヒヤリハットとメンタルの関係を現場目線で解説。安全管理の盲点となりがちな「心の不調」が、重大事故につながる可能性を具体例と共に紹介します。高所作業や建設現場に求められる、安全と心身のセルフケア力が学べる研修です。
~睡眠は世界でイチバン楽で楽しい自己管理~心も体も元気に働く!ハイパフォーマンス睡眠法
睡眠不足は判断ミスや労災の引き金になります。本研修では、安全とパフォーマンスの両立に不可欠な「ハイパフォーマンス睡眠法」を、リスク管理の観点からわかりやすく解説します。睡眠負債による事故リスクや、集中力を高めるコツを実例とともに学び、現場の安全意識と生活習慣を見直すきっかけを提供します。
ストレスに対抗し、仕事の能率を上げるには
救急医療の現場経験を持つ講師が、ストレス放置のリスクと向き合い、仕事の効率と安全意識を高めるための健康習慣を伝えます。脳を刺激する簡単な体操や、食事の工夫、心の整理術など、明日から使える実践法を楽しく学べる内容。ストレス対策が職場の安全文化を支えます。
ヒューマンエラーを起さないための健康管理術~3つの疲労回復と健康法でベストコンディションを保つ~
ヒューマンエラーの背景には、見過ごされがちな「疲労」があります。本研修では、肉体・脳・精神の3つの疲労に注目し、不調の正体を明確にしたうえで、姿勢改善や食習慣、ストレス対策をストレッチ実践とともに学習。事故を防ぐ“気づける健康管理”を体感的に習得します。
合わせて読みたい
健康なくして安全な仕事はできません。ストレスや疲労が原因で集中…
健康なくして安全に仕事はできません。ストレスや疲労が原因で集中…
⑨過去の労災事例
過去に実際に発生した労災の事例を掘り下げる学びは、再発防止や職場全体の安全意識向上に効果的です。
原因や対応策をケーススタディとして取り上げ、「自社の現場だったらどう応用できるか」を考える力を養います。同じ会社や業種の事例を採用するのがポイントです。
事例集は厚生労働省のwebサイトなどでも公開されており、業種やキーワードでの検索も可能です。
人気研修プラン
事例とディスカッションで学ぶ労災予防・安全対策
「事故は他人事」では済まされません。本研修では、実際の労災事例とグループディスカッションを通じて、事故の背景にあるヒューマンエラーや組織の仕組みを可視化。臨場感あるケーススタディにより、参加者が自ら気づき、現場で活かせる予防策と安全意識の定着を促します。
元災害支援チームメンバーが語る、事例から学ぶ、労災時、災害時の対応のポイントとコツ
災害現場の支援経験をもつ元看護師が、実際の労災・自然災害事例をもとに、負傷者の応急手当やトリアージ、メンタルケアのポイントを伝授。グループワークを交えて「いざという時にどう動くか」を体感的に学びます。安全意識と危機管理能力の底上げに最適な研修です。
労災かくしの顛末記
元労働基準監督官が語る、実際に捜査・送致した「労災かくし」の実態。なぜ隠され、どう発覚し、どのような結末を迎えたのか。豊富な現場経験に基づく事例紹介を通じて、労災報告の重要性と、コンプライアンス違反が企業にもたらす重大なリスクを具体的に学びます。
事例から見る建設業の損害賠償金額はどのくらいか
建設現場で起こる労働災害。その裏にある損害賠償額の現実をご存じですか?元清水建設 安全環境部長である講師が、民事責任に焦点をあて、過去の災害事例をもとに「示談金」「過失割合」などの実例を解説。管理職・経営層必聴、金額から見える安全管理の重要性が理解できる実践的な内容です。
安全大会に専門家による講演を組み込むのもおすすめ
安全大会で、参加者の学びや意識づけをより強化するなら、外部講師による講演を取り入れるのがおすすめです。
実務経験のある講師の話は現場に響きやすいという特徴があります。災害事例や5S、KYT、メンタルヘルスなど幅広いテーマで安全意識の定着に役立つでしょう。
より詳しく知りたい方はこちらもご覧ください!
効果的なカリキュラムを立てるポイント
 安全衛生研修の効果を高めるコツは、自社の目的や職場の実情に即したカリキュラムを設計することです。ここでは、実践的な4つの工夫を紹介します。
安全衛生研修の効果を高めるコツは、自社の目的や職場の実情に即したカリキュラムを設計することです。ここでは、実践的な4つの工夫を紹介します。
1.安全衛生方針や計画全体に基づく研修目的・目標の設定
安全衛生研修は、単独で実施するのではなく、企業全体の安全衛生方針や計画の中に位置づけてこそ、より効果的に機能します。
目的が「建設現場の労働災害ゼロ」であれば、元建設業の専門家による研修を実施し、「参加者が理解度テストで平均8割以上のスコアを達成する」などです。計画に基づいて、カリキュラムと研修による到達目標を設計するのがポイントです。
2.ケーススタディの活用(労働災害やヒヤリハット事例)
実際に発生した災害やヒヤリハットの事例を用いたケーススタディは、現場の作業者が「自分ごと」と捉えやすい、有効な手法です。
特にその現場特有のリスクや失敗事例は、「自分の今の職場でも起こり得る」と参加者にとって危険を身近に感じられ、対策の必要性を理解しやすくなります。
3.実践的プログラムの導入(ディスカッション・グループ演習など)
座学中心の研修は、基礎的な理解が進んでも実践に結びつかないケースが少なくありません。異常や危険な事態が発生したときに、知っていても対応できないのでは無意味です。
そこで、実際の作業場面を想定したディスカッションや、グループでの演習を取り入れるのがおすすめです。受講者同士の意見交換や相互学習で、より主体的な行動変容につなげられるでしょう。
4.学習形態の選択(オンラインやビデオ・動画教材など)
対面研修に加え、オンライン研修や動画教材を活用する企業も増えています。特に、複数の拠点に事業所を持つ企業や、対象者がなかなか集まりにくい現場には便利な実施形態です。
予習として動画教材を利用したり、反転学習(事前に各自で動画視聴+それをふまえ集合研修で実習するなど)を取り入れたりすると、学習効果を高められる可能性もあります。
自社の課題にそった研修計画を
安全衛生研修の開催は、法令対応にとどまらず、安心や健康を基盤に組織全体の生産性向上にもつなげられる点などで、企業に注目されている取り組みです。
必要なケースや自社の課題に合うテーマを理解すれば、職場全体の安全衛生水準の底上げを実現できます。まずは自社の現状をしっかり把握し、目標に合った研修計画の立案から始めてみましょう。
あわせて読みたい
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました- 投稿タグ
- 5S, KYT, Ti-ccha, カリキュラム, ストレスマネジメント, ヒヤリハット, メンタルヘルス, ヨシダヨウコ, リスクアセスメント, 中川潔, 中村俊輔, 中村昌弘, 事例, 今蔵ゆかり, 依田司, 労働災害防止, 危機管理, 危険予知訓練, 原論, 去来川敬治, 増井孝夫, 安全大会, 安全教育, 安全管理・労働災害, 安全管理者, 安全衛生推進者, 安全衛生教育, 安全衛生研修, 安全衛生責任者, 富田勉, 小久保晴代, 小林瑞穂, 小針衣里加, 山田昌芳, 島本長範, 新谷まさこ, 松本裕子, 森山佐恵, 森川あやこ, 池田ノリアキ, 池田早苗, 清原実, 渡部俊和, 熱中症対策, 特別教育, 田中咲百合, 田部良夫, 相蘇淳一, 眞橋今日子, 福島健太郎, 職長教育, 藤井恵理子, 衛生推進者, 衛生管理者, 辻太朗, Wマコト















































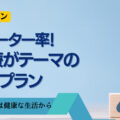




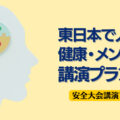
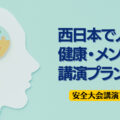
















業務外の講師への取次は対応しておりません。